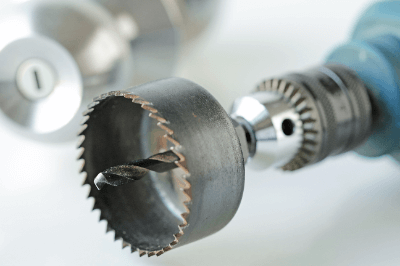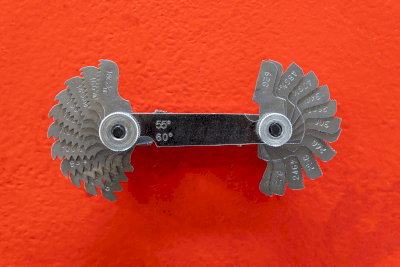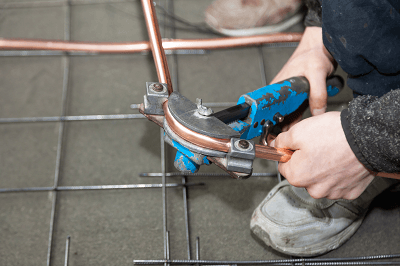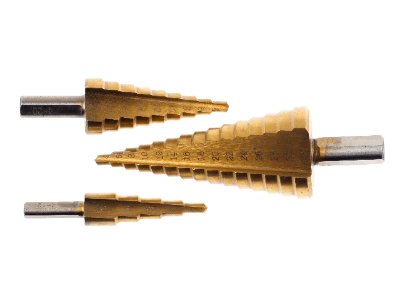すべり止めテープとは

すべり止めテープとは、スリップによる転倒防止などのために、すべりやすい床に貼りつけるテープのことです。
すべり止めテープにはシマ鋼板、すなわち側溝の蓋などに使用されている突起のある鉄製の板用や屋内用、屋外用など用途や使用場所に合わせてさまざまなタイプが販売されています。粉体が積もりやすい工場など人が転倒しやすい場所に使用すると共に、人間の歩行用のみでなく車椅子が段差を乗り越える際に滑らないようにする場合なども想定して設計されているのが特徴です。
すべり止めテープの使用用途
すべり止めテープは前述したとおり、転倒防止のために使用される場合が多いです。床は絨毯よりも表面が滑らかな方が清掃がしやすく、見た目も美しいので、建物のエントランスなど汚れやすい場所にはタイルなど滑らかな床が好まれます。
一方で、滑らかな床は摩擦が弱く、特に液体があると非常に転倒しやすい状態になり、雨の日など転倒して怪我をすることがよくあります。すべり止めテープは、これらの事故を防止することが目的です。
また、階段など足を滑らすと大怪我をする可能性のある場所にも、すべり止めテープが貼られている場合があります。特に浴室は石鹸等の界面活性剤を使用するため、水だけの状態よりもさらに滑りやすいです。屋外に限らず室内でも、危険防止のためにすべり止めテープが使用されています。
すべり止めテープの原理
すべり止めテープは、主にプラスチックのテープの表面に硬い鉱物粒子やプラスチックでできた粒状のものを貼り付けて摩擦が強くなるようにしたものです。
表面の粒は用途により異なりますが、踏みつけたり荷台などが通っても粒子が取れないように樹脂コーティングで強固に接着されています。同様に床に貼り付けるテープの粘着力も強く、剥がれにくくなっています。
屋外用は雨風に晒されるので耐水性が高く、丈夫な素材で作られているのが特徴です。特に床に油がかかった状態でもテープの上を踏む限り滑らずに歩行できるものもあります。
また、蓄光タイプのすべり止めテープもあり、急な停電の際などに蓄えた光を放出して光るため視認性が高まりより安全性が高くなります。
すべり止めテープの種類
すべり止めテープには使用箇所によって種類が分けられています。
1. 砥粒による分類
屋外での使用を想定した場合、靴を履いている状態で踏むことや歩くこと考えているためすべり止めには主に硬さがある鉱物粒子が用いられます。一方、屋内や浴室を想定した場合は素手や裸足で触れることを考慮して、やわらかいプラスチックが用いられることが多いです。
2. テープの色による分類
黒やグレー色であることが一般的です。使用する場所に応じ目立たせないよう透明のものや、あえて注意を促すグラフィックを持ったものも販売されています。
3. 基材材質による分類
すべり止めテープは、ほとんどがプラスチックでできています。貼り付ける場所が平面であれば問題ありません。しかし、凹凸のある面やシマ鋼板に貼り付ける場合には、接着面が浮き上がってきてしまいます。そのような場合には、基材がアルミでできたもので凹凸に合わせて密着させることができます。
すべり止めテープの選び方
メーカーからは、使用場面を想定して商品が区分けされて販売されていることがほとんどです。しかし、用意されている色や大きさが使用場面により限られている場合があります。
外観も重要な要素ですが、すべり止めの効果や目的を一番に優先してすべり止めテープを選定するべきです。特に屋内向けのものを屋外に使用した場合は、十分な効果が得られないことがあります。
すべり止めテープのその他情報
すべり止めテープの使い方
すべり止めテープを貼り付ける際は、ハサミなどで必要な長さに切り取り、裏紙を剥がして粘着面を出して床に貼り付けます。テープを一列のみ貼り付けるのではなく、人の足の大きさに合わせて20センチメートル程度のピッチで何列も貼り付け、テープを避けて濡れた床を直接踏まないようにするのがポイントです。
また、貼り付ける前には剥がれないよう接着面をきれいにするほか、角を丸めておくなどの工夫をすることで長期に及んで効果を発揮することができます。メーカーによっては、事前に貼り付け面へプライマーを塗布することを推奨している場合もあるので、事前の確認が必須です。
参考文献
https://www.cushiony.jp/products/list.php?category_id=982