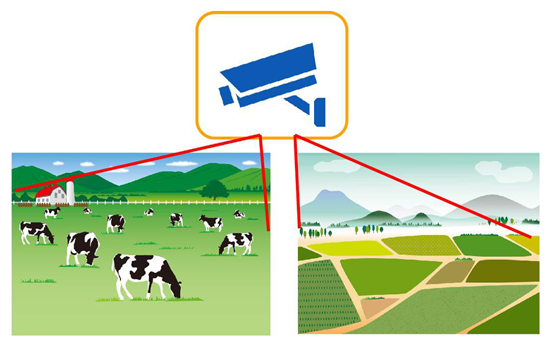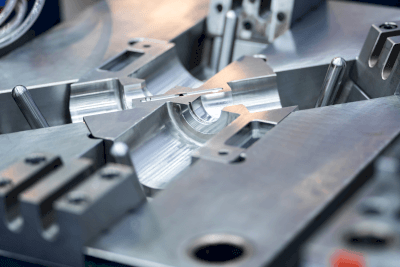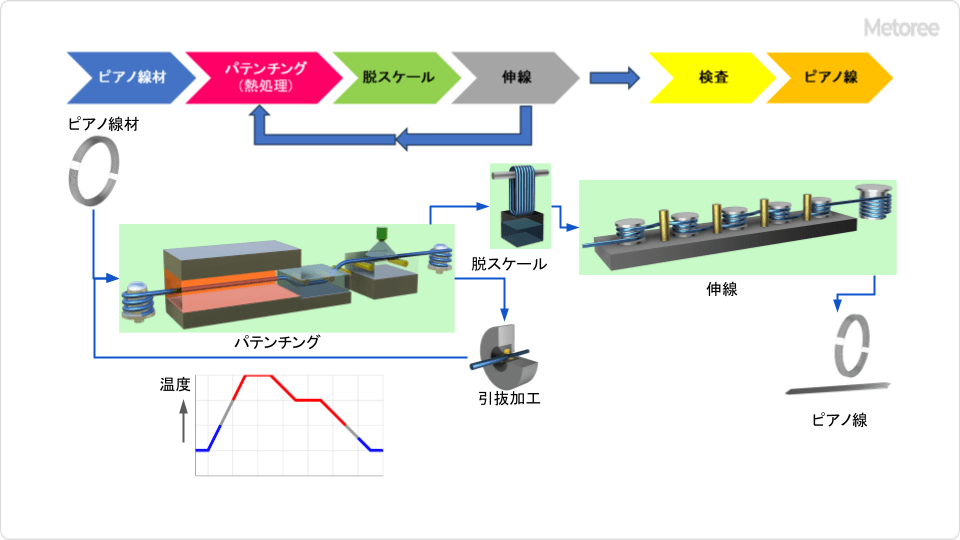亜鉛めっき鉄線とは
亜鉛めっき鉄線とは、伸線加工した軟鋼線材等に亜鉛めっきでコーティングを行った鉄線です。
亜鉛皮膜の防食効果により、フェンスやワイヤーロープ、建築資材などに使用され、高い耐食性があります。JIS G 3547上では、亜鉛めっき鉄線 (S) と亜鉛めっき鉄線 (H) の2種類が規定されており、それぞれSWMGSとSWMGHといわれます。
SWMGSは柔軟性があるためフェンスなどに適し、SWMGHは高強度でワイヤーロープや補強材向けです。 SWMGSは1~7種類、SWMGHは1~4種類の計11種類がJISで規定されています。
亜鉛めっき鉄線の使用用途
亜鉛めっき鉄線は、鉄線の表面に亜鉛めっきを施し、防錆性を上げた材料です。優れた耐食性・強度・加工性を活かし、さまざまな分野で利用されています。
1. フェンス・ネット・防護柵
亜鉛めっき鉄線は、耐久性とコストのバランスが良く、フェンスや金網、防護柵に広く使用されます。道路や工場の囲い、農業用の動物柵、スポーツ施設の防球ネットにも適しています。特にSWMGSは柔軟性があり金網加工が容易なため多用されやすい材料です。また、屋外で使用されることが多く、耐食性を確保するためにめっき厚の選定が重要です。
2. ワイヤーロープ・ケーブル
亜鉛めっき鉄線は、ワイヤーロープの素材として建設・土木・運輸業界でも使用されます。クレーンや橋梁ケーブル、エレベーターの昇降ロープなど、高強度と耐食性が求められる用途に適切な鉄線です。特にSWMGHは強度が高く、強い引張荷重に耐える特性があります。溶融亜鉛めっきを施すことで、屋外や海岸地域などの厳しい環境でも腐食を防ぎ、長期間使用できるのが特徴です。
3. 電線・架空送電線
電力・通信分野での用途例は、送電線や通信ケーブルの補強線です。特に、雷の影響を防ぐ架空送電線の地線 (アースワイヤー) は耐食性が求められるため、亜鉛めっき処理を施した鉄線が選ばれます。また、電線の心線 (ワイヤーストランド) としても使用され、電線の強度を向上している点も特徴の1つです。
4. 建築・土木分野
建築・土木分野では、鉄筋結束線、ワイヤーメッシュ、補強材として亜鉛めっき鉄線が使用されます。特にコンクリートの補強に使われるワイヤーメッシュや鉄筋を固定するための結束線として活躍します。橋梁やトンネル、港湾施設などでは、高い耐食性が求められるため、厚めのめっきを施した鉄線が適切です。また、地震対策として建築物の補強材にも活用されています。
亜鉛めっき鉄線の原理
めっき処理には、鉄の腐食を防ぐための電気化学的な作用や物理的なバリア作用が関係しています。
1. 基本原理
亜鉛めっき鉄線は、鉄の表面に亜鉛をコーティングすることで、耐食性や耐久性を向上させる技術です。鉄は空気中の酸素や水分と反応して錆 (酸化鉄) を形成しやすいため、亜鉛めっきによって外部環境との接触を遮断し、腐食を防ぎます。
めっきは、溶融亜鉛めっきと電気亜鉛めっきの2種類です。亜鉛は鉄よりもイオン化傾向が大きいため、亜鉛が先に腐食することで鉄を保護する犠牲防食作用という働きがあります。
2. 防食メカニズム
亜鉛めっき鉄線の防食メカニズムは、犠牲防食作用、バリア作用、自己修復機能の3つに分けられます。犠牲防食作用とは、鉄よりも先に亜鉛が腐食することで鉄の酸化を防ぐ現象です。特に亜鉛が水分と反応すると亜鉛イオン (Zn2+) が発生し、鉄の表面で電子を供給することで錆の進行を抑制します。
バリア作用は、亜鉛めっきが酸素や水分との接触を遮断し、腐食を物理的に防ぐことです。また、亜鉛が酸化することで酸化亜鉛 (ZnO) や炭酸亜鉛 (ZnCO3) が形成され、鉄を覆う防護膜として機能します。めっき層に傷がついても、自己修復的に新たな保護層が形成されるため、長期間の耐食性を維持できます。
3. 亜鉛めっきの付着メカニズム
密着性は、溶融亜鉛めっきと電気亜鉛めっきで異なります。溶融亜鉛めっきでは、鉄を約450℃の亜鉛浴に浸すことで、鉄表面にFe-Zn合金層が形成されます。合金層は拡散反応によって生じるため、鉄と亜鉛が強固に結合し、剥離しにくい特性です。
一方、電気亜鉛めっきでは、電解槽内で鉄を陰極とし、亜鉛イオン (Zn2+) を電気的に析出させてコーティングします。均一な薄膜を形成できますが、合金層がないため溶融亜鉛めっきほどの密着性は得られません。
亜鉛めっき鉄線の種類
亜鉛めっき鉄線は、鉄線の表面に亜鉛めっきを施すことで以下の性能を向上させます。
使用環境や用途に応じて、さまざまな種類があり、それぞれ特性が異なります。
1. JIS規格に基づく分類 (JIS G 3547)
亜鉛めっき鉄線は、日本工業規格 (JIS G 3547) に準拠し、一般用途向け (SWMGS) と工業用途向け (SWMGH) の2種類に区分されます。
SWMGS (Soft Wire for General use, Standard) は、まず鉄線を冷間加工した後、焼きなまし (熱処理) を施してから亜鉛めっきを行うのが特徴です。さらに、めっきの厚さによって1種から7種まで細分化されており、厚いほど耐食性が向上します。例えば、「SWMGS-7」は線径2.60〜6.00mmで、めっき付着量が400g/m²以上となります。
一方、SWMGH (Hard Wire for Industrial use, Heavy duty) は、冷間加工の後に焼きなましをせず、直接亜鉛めっきを施します。そのため、より高い強度が求められる用途に適しています。SWMGHもめっき厚の違いにより1種から4種に分類されており、例えば「SWMGH-4」は線径4.00〜8.00mmで、めっき付着量が245g/m²以上です。
2. めっき方法による分類
亜鉛めっき鉄線の製造方法は、以下の2種類です。
溶融亜鉛めっきは、約450℃の溶融亜鉛浴に鉄線を浸し、鉄と亜鉛が拡散して強固なFe-Zn合金層を形成するため、耐久性と密着性に優れます。一方、電気亜鉛めっきは、電解槽内で鉄線を陰極として電流を流し、亜鉛イオンを鉄表面に析出させめっきを形成するものです。均一で薄いめっきが可能で外観に優れるため、家電製品や精密部品に適していますが、耐食性は溶融亜鉛めっきよりも劣ります。
亜鉛めっき鉄線の選び方
亜鉛めっき鉄線は、用途や使用環境に応じて適切な種類を選定することが重要です。選び方を誤ると、耐久性の低下、コスト増、加工性の問題が発生する可能性があります。
1. 使用環境に応じた選定
亜鉛めっき鉄線を選ぶ際には、使用する環境が最も重要な判断基準です。屋内で使用する場合は、湿気や塩害の影響が少ないため、薄めのめっきや電気亜鉛めっきが適しています。
一方、屋外で使用する場合は、雨風や紫外線の影響を受けるため、溶融亜鉛めっきが必要です。特に海岸地域や工業地域では、塩害や化学物質による腐食が進行しやすいため、重めっきやZn-Al合金めっきなどの高耐食性製品を選ばなければなりません。
また、高温環境ではZn-Ni合金めっきが適しており、化学プラントや排ガス処理施設ではZn-Mg合金めっきが推奨されます。
2. 機械的特性を考慮した選定
亜鉛めっき鉄線は、用途に応じて求められる機械的特性が異なります。たとえば、ワイヤーロープや送電線などの高荷重がかかる用途では、引張強度が高いSWMGHが適切です。このタイプは硬度が高く、長期間の使用に耐える強度を持っています。
一方、フェンスや結束線などの用途では、加工しやすいSWMGSが適切です。また、耐衝撃性が求められる場合は、Zn-Ni合金めっきが効果的で、自動車部品や機械部品の補強材として利用されています。
3. 加工性を考慮した選定
亜鉛めっき鉄線を使用する際には、加工のしやすさも重要なポイントです。曲げ加工を行う場合、柔軟性の高いSWMGSを選ぶことで、加工時の亜鉛めっきの剥がれを防ぐことができます。切断加工する際は、線径と硬度を考慮し、柔軟なSWMGSは通常のワイヤーカッターで切断しやすく、SWMGHは高硬度のため専用のカッターが必要です。
なお、亜鉛めっきへの溶接は、気孔欠陥 (ブローホール・ピット)やスパッタが発生するため、原則推奨されません。