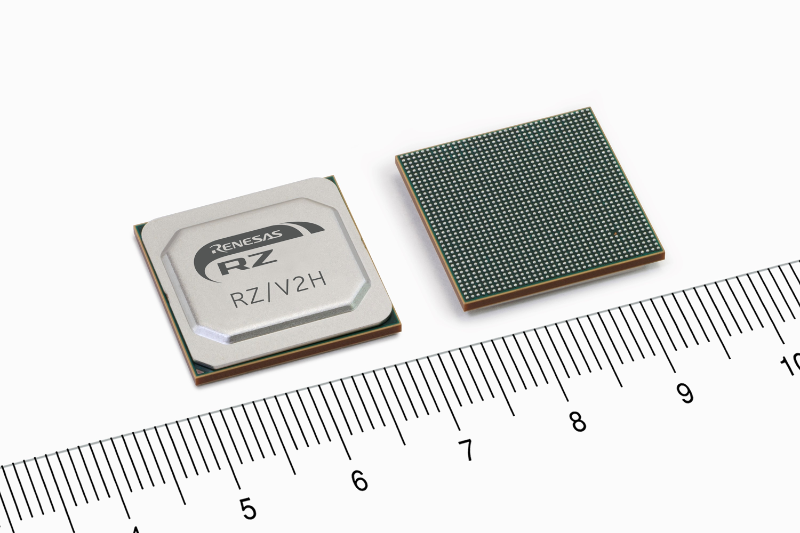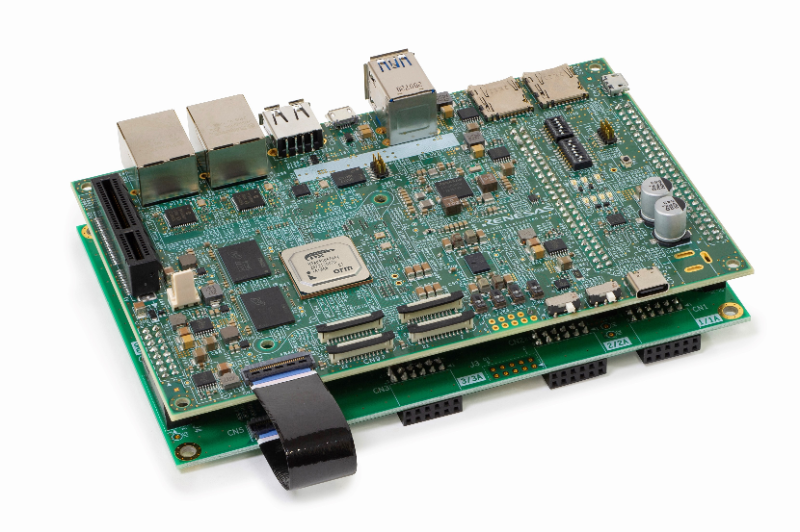監修:関東メジャー株式会社
分銅校正とは
分銅校正とは、分銅の正確な質量を測定する作業です。
分銅の質量は用することによって変化します。取り扱いや保管環境によって、経年的な変化量が異なるため定期的な分銅校正が欠かせません。
校正の結果、決められた分銅質量 (1 g, 2 g等) からの質量差が明確になります。
一般的に1年に1回再校正を行うことが多いです。分銅校正を行うことで、使用する分銅が正確な重さを示すようになり、校正された分銅を使用したはかり校正により、信頼性の高い製品・サービス提供が可能となります。
校正作業には認定事業者が行うJCSS校正と非認定事業者の行う一般校正があります。認定事業者とは国際的な規格ISOに従った校正を実施できることを経済産業省の機関である製品技術基盤機構によって審査・認定された事業者です。
認定事業者の発行するJCSS校正証明書は協定質量と不確かさが示されます。
協定質量とは提供者と受給者で簡易的な質量結果の取り交わしを目的に、温度20℃、大気密度1.2 kg/m3の環境においてつり合う、密度8,000kg/m3を条件とした標準分銅の質量です。これにより空気密度による浮力条件や対象の分銅の密度を合わせより正確な質量結果を表すことができます。
不確かさは± (プラスマイナス) といった形式で示され、例えば±1.0gであった場合、-1.0gから+1.0gまでの間の真の質量があることを約95%の確度で示します。また、認定事業者の発行したJCSS校正証明書は国の管理する質量標準からの計量計測トレーサビリティが確保されていることを保証しており、トレーサビリティが確保されていることを示す体系図などの追加資料は不要です。
分銅校正の使用用途
分銅校正の結果は様々な分野で活用されています。以下はその一例です。
1. 製造業
製造業界では、分銅は必須の道具です。製品の質量を正確に測定するために、分銅を使ってはかりが正確に測定できることを確実にする必要があります。精密な質量測定が製品品質や安全性に直結するため、分銅を利用してはかりの検証作業 (日常点検や性能確認) を事前に実施しています。
2. 化学・製薬業
製造業の中でも化学工業や製薬業では、原料や化学製品の重さを正確に測ることが必要です。特に薬品の製造においては、成分の比率や原料の分量を厳密に調整する必要があり、そのために分銅によって校正されたはかりを使用します。製造機器の校正や研究所での実験の精度を保つためにも分銅は重要な役割を果たします。
3. 医療
医療分野では、薬剤の調合や体重計及び医療器具の重さの確認において分銅が使用されることがあります。分銅を使ってはかりを校正し、正確な値を指すことを確認することが多いです。はかりの値がずれてしまうと、医療の質が低下してしまう恐れがあるため注意が必要です。
4. 物流業・商業
物流や貿易業界では、貨物の重さを正確に測定する必要があります。分銅によって校正したはかり使用することで、正確な貨物の重量に基づいて運賃を計算します。また、規制に従って適正な重量となっているか確認することも重要です。
輸出入時は貨物の正確な重量を記録することも重要となるため、分銅を使用したはかり校正が必要となります。商業分野では市場や小売店での正確な計量は消費者と販売者の間で行われる商取引に重要や役割を果たしており、法律ではかりの定期的な検査が必要となるものがあります。
5. 研究・開発
科学研究では、実験の結果に影響を与える可能性があるため、精密な計測が不可欠です。分銅校正を行うことで質量の測定が正確になり、実験データの信頼性を担保します。物理学、化学、生物学の実験で使用する器具が適切に校正されていることが、実験の成功とデータの整合性を保証します。
分銅校正の等級の選び方
分銅は国際規格OIMLにより1mgから5000kgまでの精度等級ごとに材質や構造、最大許容誤差などが規定されています。精度等級が高い分銅ほど、より小さな最大許容誤差が規定されています。分銅は使用開始以後の経年変化によって購入当時の精度等級を維持しているか (適合性評価) 、定期的な校正によって確認する必要があります。なお校正の結果、購入当時の精度等級を逸脱している場合、調整孔をもつ分銅については質量調整が可能です。以下に主な校正区分を示します。
1. E1級
E1級は分銅の中で最も高い精度の等級で、非常に厳密な質量管理が求められる場合に使用されます。非常に高価で、所有機関のE2級分銅を校正するために使用し、普段は質量変化を起こさぬよう厳重に保管します。
2. E2級
E2級はE1級に次ぐ高い精度の等級で、E1級ほどの精度は要求されないものの、依然として非常に高い精度を有します。
研究所などで使用されるような、精度の高いはかりの校正に用いることが多い等級です。
3. F1級
F1級はE2級に次ぐ高い精度の等級で、E2級ほどの精度は要求されないものの、依然として高い精度を有します。
工場などで使用されるような、はかりの日常点検で用いることが多い等級です。
4. F2級
F2級はF1級に次ぐ高い精度の等級です。精密な計測が必要な場面で使用されますが、F1級よりはやや広い許容誤差範囲を有する等級です。
5. M1級
M1級は商業的な取引や一般的な計測で使用される標準的な精度を持つ分銅です。F1級やF2級ほどの精度は求められないものの、通常の商業取引や工業上の計測において充分な精度を有する等級です。
日常的な使用に対して充分な許容誤差を持ち、長期間安定して用いることができる等級です。
6. M2級
精度がそこまで重要でない場合や、予算が限られている場合に使用されます。商業的な取引や一般的な計測で用いられ、誤差がある程度許容される状況で使用します。高精度を求められる場面では使用しません。
本記事は分銅校正を行う関東メジャー株式会社様に監修を頂きました。
関東メジャー株式会社の会社概要はこちら