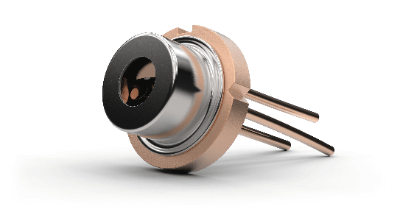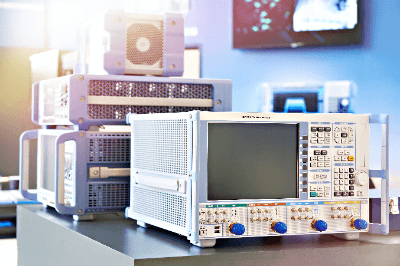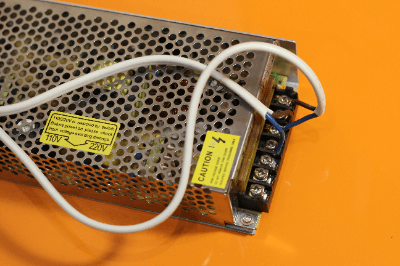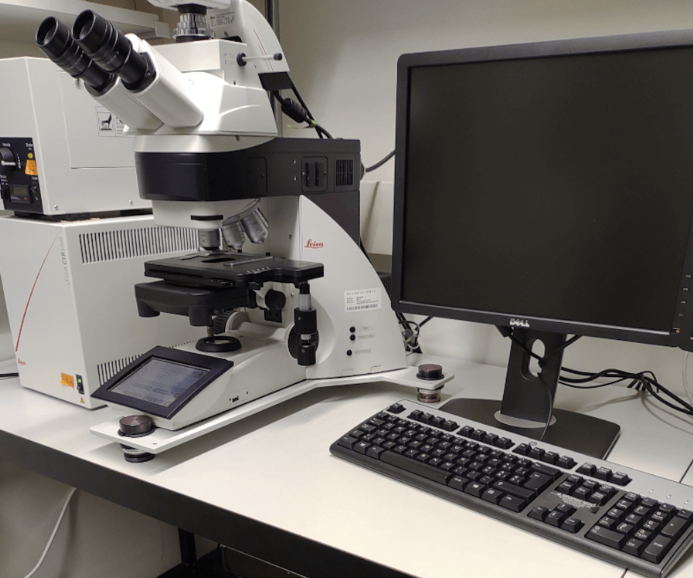漏れ電流計とは

漏れ電流計 (英語:leakage current measure) とは、電気機器からの漏電電流を測定する機器です。
一般にmA以下の微小な電流を測定できるクランプメーターのことを指します。
漏れ電流計の使用用途
漏れ電流計は、一般的に法令で定められた基準に適合するか判断することを目的として、電気設備や医療機器などに使用されます。
漏れ電流は人体への影響が大きく、微弱でも死に直結するため安全の観点から正確な測定が必要です。また、通信機器ノイズの原因につながるので、品質の観点からも重要となります。
漏れ電流計の原理
漏れ電流計は回路導体と非接触に測定可能で、銅線をクランプメータで挟むことで電流を測定します。
電流検出の原理は、電流により発生した磁界を検出して測定電流に比例した出力を取り出します。検出方法は、最も一般的なものとしてCT方式、ロゴスキーコイル方式、ホール素子方式、フラックスゲート方式などがあります。
1. CT方式
測定対象の電流を、巻線比に対応する2次電流に変換する方式です。
2. ロゴスキーコイル方式
測定対象の電流の周辺にできた交流磁界によって、空芯のコイルに誘起される電圧を変換する方式です。
3. ホール素子方式
ホール素子とCT方式を合わせることで、直流電流から測定する方式です。ホール素子とは磁界を発生させた箇所に電流が流れる際に発生する電圧を測定する素子で、直流測定ではこの方式が主流となります。
4. フラックスゲート方式
フラックスゲート (FG素子) とCT方式を合わせることで、直流電流から測定する方式です。フラックスゲートとは鉄心に2本の逆向きコイルを巻くことで発生磁界を測定する素子で、磁界から電流値に逆算します。
漏れ電流計のその他情報
1. 漏れ電流と医療機器
医療機器の発売前には厚生労働大臣の承認が必要です。その中でも、能動医療機器といわれる医療用電気機器の承認には、装着部 (患者に接続する箇所) が電気的にどのカテゴリに該当するのかを規定しなければなりません。
特に心臓など、最もシビアな環境に対して使用される医療機器では、IEC 60601-1 (JIS T0601-1) で規定される「CF型装着部」といわれるカテゴリー (漏れ電流許容限界0.01 mA) に適合する必要があります。このように、医療機器の設計検証の段階では、機器から漏れる漏れ電流の厳格な管理が重要です。したがって、医療機器の承認では規格に対応した専用の漏れ電流計 (試験装置) を用いて漏れ電流を測定します。
2. 漏れ電流計と一般的な電流計の違い
漏れ電流計の最大の特徴は分解能です。負荷電流を測定する電流計は、クランプ方式の場合は1A以上の大電流を測定します。一方、漏れ電流計は微弱な電流を計測する必要があるため、1A以下の微弱電流を測定できるのが特徴です。半導体製造工程向けに微弱電流を測定する負荷電流計も存在しますが、その用途では回路へ直列接続する機器が一般的です。
3. 漏れ電流計の使い方
クランプ型漏れ電流計は電気配線の漏電検査などに用いられ、停電不要で機器を通電状態で検査できます。
測定環境の整備
漏れ電流計は、その原理から外部磁界の影響を受けます。そのため、トランスなど外部磁界の原因となる機器から隔離した場所での測定が必要です。
計測の方法
環状のクランプを開き、測定対象ケーブルを環内に挿入してクランプを閉じます。零相による漏れ電流測定では、全相一括でクランプします。アース線による漏れ電流測定ではアース線を単独でクランプします。その後、測定レンジを計測目的に従って設定し、計測開始です。表示インターバル間隔を設定できる製品や、平均値を表示できる製品も存在します。計測対象や計測目的によって漏れ電流計を選定することが大切です。
4. 漏れ電流の種類
保護導体電流 (接地漏れ電流)
IEC 60601-1規格において、「主電源部品から絶縁体を通ってまたは絶縁体を横切って保護接地導体または機能接地接続線に流れる電流」として定義されます。
タッチ電流 (接触電流) またはエンクロージャの漏れ電流
IEC 60990規格において、「設置または機器の1つまたは複数のアクセス可能な部分に触れるときの人体または動物の身体を通る電流」として定義されます。
患者漏れ電流
IEC 60601-1規格において、「患者接続から患者を経由してアースに流れる電流」として定義されます。
患者測定電流 (医療用電気機器のみ)
IEC 60601-1規格において、「正常な使用時に,患者を介してある患者接続部と他のあらゆる患者接続部との間に流す生理的な効果を意図しない電流」として定義されます。
参考文献
https://estcj.com/%E8%A3%BD%E5%93%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%EF%BC%9A%E6%BC%8F%E3%82%8C%E9%9B%BB%E6%B5%81%EF%BC%81
https://www.panasonic.com/jp/corporate/pac/safety/safety_test/leakage-current.html
https://metoree.com/categories/leakage-current-measure/
https://www.kew-ltd.co.jp/files/jp/manual/2433R-2433RBT_IM_92-2347A_J_L.pdf
https://www.hioki.com/file/cmw/hdInstructionManual/94201/pdf/
https://www.kew-ltd.co.jp/support/knowledge/technical/clampmeter