全てのカテゴリ
閲覧履歴












近赤外カメラについての概要、用途、原理などをご説明します。また、近赤外カメラのメーカー21社一覧や企業ランキングも掲載しておりますので是非ご覧ください。近赤外カメラ関連企業の2024年6月注目ランキングは1位:株式会社ジェイエイアイコーポレーション、2位:バスラー・ジャパン株式会社、3位:株式会社渋谷光学となっています。
近赤外カメラと関連するカテゴリ
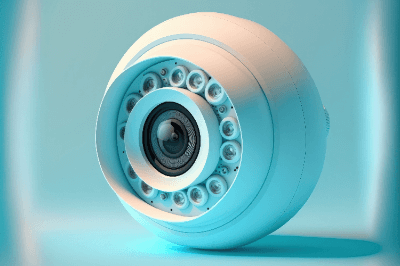
近赤外カメラ (英: near infrared camera) とは、一般的なカメラでは映すことができない赤外線波長域の光を撮影できるカメラです。
近赤外線は、波長が700nmから2,500nm (0.7~2.5μm) の電磁波の1種です。人間の目で見ることができる可視光よりも波長が長いので、肉眼で見ることができません。
物体はその組成によって光の反射や吸収の仕方が異なっているため、この特性の違いを利用し、人間の目で見えない光を近赤外カメラによって可視化することが可能です。そのため、近赤外カメラは電子部品から農産物まで幅広い製品の検査で利用されます。
近赤外カメラの使用用途は、人間の目で見ることができない近赤外線を写すことができるため、監視や検査、観察などです。被写体は様々で、医薬品や電子部品などから、農産物や食品など多岐にわたります。
具体的には、農作物の鮮度を判別したり、食品に異物が混入していないかを検査したり、医薬品の成分や肌の水分を分析したりする際に使用されます。また、塩・砂糖・調味料の区分が可能です。
果実のキズや木材の割れの検出、水と油の分別、ICカード内の回路読み取りなどの用途があります。今後も更なる使用領域の拡大が期待されます。
近赤外カメラは、物質ごとの近赤外光の吸収量を画像として表示するものです。近赤外線は赤外線をさらに分別した中で、可視光線よりも波長が長く、電波よりも短い赤外線です。
近赤外線は太陽光中にもあるような日常に身近なので、人体や食物などに照射しても影響のない安全な光と言えます。色や熱には特徴を示しませんが、光の中で物体に一番吸収されやすい光です。
近赤外カメラの原理は、物質によって光の反射や吸収の度合いが異なることを利用する方法です。波長域の異なる光によって見え方が違うので、その違いのコントラストを強調させることで、異なる物質同士でも可視化することができます。
被写体に近赤外線が含まれた光を投射すると、異なる物質で光の反射や吸収の違いが特徴として画像に表れ、これを映すことで可視化しています。
赤外線は、さらに細かい波長域で3分類されます。
近赤外カメラと遠赤外カメラは、可視化出来る波長の範囲が異なります。また、カメラの検査対象となる被写体も近赤外カメラと遠赤外カメラとで異なっています。
近赤外カメラの対象は、食料品や医薬品、化粧品などの不良品検査に対し、遠赤外カメラは防犯セキュリティや車のドライビングアシスト用に、暗部での人や動くものが対象です。<近赤外カメラは、自ら熱を発するような物体の検知はできません。
そのほとんどが日中の太陽光下や照明器具による反射光を利用して観測を行います。近赤外カメラでのノイズ対策は比較的容易です。余計な反射を行う箇所を反射しない黒い布で覆えば改善できます。
遠赤外カメラは、熱を発するものをほとんど検知できるため、どんなに暗闇でも被写体と背景の間に温度差があれば、観測が可能です。ただし、日中は熱を発する物体が多くあるため、検査対象ではない物体は、すべてノイズとして観測されます。
近赤外線は電磁波の1種なので、人間の肉眼では見ることができない光です。しかし、可視光下で見分けがつかない被写体に対して、近赤外カメラで撮影すると、通常見分けができない被写体に対しても見分けることができるようになります。
例えば、食塩、砂糖、調味料は可視光下ではほとんど見分けがつきませんが、1.5μmの近赤外カメラで撮影すると、それぞれを見分けることが可能です。3種類の粉体の赤外光吸収度が、可視光下ではほぼ同じなのに対して、近赤外線下では異なることが理由として挙げられます。
塩は約1.1μmの吸収波長ですが、砂糖は約1.3μm、調味料は約1.5μmの赤外光吸収波長を有しています。そのため、1.5μmの近赤外カメラで撮影すれば3種類の粉体を見分けることが可能です。
参考文献
https://www.avaldata.co.jp/solution_imaging/near_infrared/near_infrared_camera.html
https://www.avaldata.co.jp/products/imaging/near-infrared-camera
https://www.asanumashoukai.co.jp/sanki/industry/photographic-equipment/ingaas
https://www.ko-pro.tech/200317marutto/

*一部商社などの取扱い企業なども含みます。




















2024年6月の注目ランキングベスト10
注目ランキング導出方法| 順位 | 会社名 | クリックシェア |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ジェイエイアイコーポレーション |
20.0%
|
| 2 | バスラー・ジャパン株式会社 |
16.4%
|
| 3 | 株式会社渋谷光学 |
7.3%
|
| 4 | ビットラン株式会社 |
7.3%
|
| 5 | 浜松ホトニクス株式会社 |
7.3%
|
| 6 | 株式会社ティー・イー・エム |
5.5%
|
| 7 | オプティカニクス株式会社 |
5.5%
|
| 8 | 株式会社アイ・アール・システム |
5.5%
|
| 9 | 株式会社アバールデータ |
5.5%
|
| 10 | 株式会社ビジョンセンシング |
3.6%
|
注目ランキング導出方法について
注目ランキングは、2024年6月の近赤外カメラページ内でのクリックシェアを基に算出しています。クリックシェアは、対象期間内の全企業の総クリック数を各企業のクリック数で割った値を指します。社員数の規模
設立年の新しい会社
歴史のある会社
製品の閲覧数をもとに算出したランキング
電話番号不要
何社からも電話がかかってくる心配はありません
まとめて見積もり
複数社に何度も同じ内容を記入する必要はありません
返答率96%以上
96%以上の方がメーカーから返答を受け取っています
平均返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話がかかってくる心配はありません
まとめて見積もり
複数社に何度も同じ内容を記入する必要はありません
返答率96%以上
96%以上の方がメーカーから返答を受け取っています
19 点の製品がみつかりました
プライムテックエンジニアリング株式会社
150人以上が見ています
返信のとても早い企業
100.0% 返答率
2.2時間 平均返答時間
■概要 GigEインターフェースを採用した産業用InGaAsカメラです。GigEVision規格に準拠しユーザーがシステムの構成を検討するにあたり選択しやすいデバイスで...
4種類の品番




プライムテックエンジニアリング株式会社
130人以上が見ています
返信のとても早い企業
100.0% 返答率
2.2時間 平均返答時間
■概要 USB3.0インターフェースを採用した産業用InGaAsカメラです。USB3Vision規格に準拠しユーザーがシステムの構成を検討するにあたり選択しやすいデバイス...
株式会社日本レーザー
50人以上が見ています
最新の閲覧: 9時間前
返信のとても早い企業
100.0% 返答率
3.0時間 平均返答時間
■ハイパフォーマンス短波長赤外 (SWIR) カメラ ・InGaAs FPA (ファーカルプレーンアレー) 640×512、900nm – 1,700nm ・高ダイナミックレンジ > 120dB (lin/lo...
株式会社アプロリンク
30人以上が見ています
最新の閲覧: 1日前
■概要 ・Chunghwa社InGaAsセンサ搭載 ・フルウェルが非常に大きく、ハイダイナミックレンジや高いSN比を必要とするアプリケーションに最適 ・FWC:3,500ke- ・...
株式会社アプロリンク
40人以上が見ています
最新の閲覧: 5時間前
■概要 ・一台で広帯域、可変レンジをカバーする光検出器、可視400nm (VIS) 光から近赤外2,000nm (SWIR) ・新しいCMOSおよび光吸収ナノ結晶材料ベースの光検...
3種類の品番



株式会社ブルービジョン
30人以上が見ています
最新の閲覧: 1日前
BVC6XXXは、M52マウントを使用した筐体に、新開発のラインセンサ用大型プリズムを搭載。 4KのCMOSラインセンサを4個搭載したモデルと4KCMOS ラインセンサを3...
2種類の品番


株式会社サイバネテック
10人以上が見ています
最新の閲覧: 8時間前
12MPのパンクロマチックセンサー、旧型モデルの2倍のGSDの新サーマルセンサー、5つの個別のスペクトルバンドを持ち合わせています。 その高解像度により、作...
株式会社サイバネテック
RedEdge-Pは、高解像度のマルチスペクトルカメラです。マルチスペクトル画像をパンシャープン処理することで高度60mで空撮した画像の解像度を2cmのGSDにしま...
株式会社サイバネテック
10人以上が見ています
農業向けに設計されたマルチバンドセンサーです。新バージョンのSequoia+ (セコイアプラス) カメラでは、取得したマルチバンドの空撮画像をPix4DソフトでNDV...
株式会社サイバネテック
10人以上が見ています
最新の閲覧: 1時間前
Sentera 6Xマルチスペクトルセンサーは、合理化された使いやすいデータ処理ワークフローを介して、科学グレードのマルチバンドおよび高解像度のビジュアルバ...
株式会社サイバネテック
10人以上が見ています
最新の閲覧: 8時間前
高性能NDVIシングルセンサは、独自の技術によるスペクトルバンドの高精度分離方法 (特許申請中) により精度の高い植生指数の測定を行う事を可能にします。 N...
3種類の品番



Metoreeに登録されている近赤外カメラが含まれるカタログ一覧です。無料で各社カタログを一括でダウンロードできるので、製品比較時に各社サイトで毎回情報を登録する手間を短縮することができます。
カタログを企業ごとに探す
カタログを種類ごとに探す

プリズムとトライリニアラインカメラの技術に関するウェビナーを開催しております。無料で登録・参加可能です。マシンビジョンにおいて適切なカメラ技術の選...
2022年8月24日

JAIは幅広い分野に高性能・高解像度のエリアスキャンとラインスキャンカメラを中心に幅広い製品を取り揃えています。単板式と独自のプリズム技術をベースに開...
2022年12月6日

『WA-1000D-CL』は、900nm~1700nmで2波長を同時に撮像可能なSWIR領域で高い感度を持つInGaAsカメラです。SWIR領域から2波長を同時に撮像可能。R、G、Bカラー...
2022年12月7日

・プリズム分光式4CMOSカメラ・R・G・B・近赤外域(NIR)を同時に撮像・単一光軸・4096画素×4ライン・7.0 µm×7.0 µm画素・最大18,252ライン/秒LT-400CLは、3...
2022年12月22日

2024年の新製品情報です。気になるものがあればお気軽にお問い合わせください。
2024年2月1日

AgEagle(旧MicaSense)社が提供するALTUM-PTは狭帯域で高解像度のマルチスペクトルバンドの取得に加え、従来のALTUM製品と同様に熱赤外画像の取得も可能なハイ...
2023年9月14日

AgEagle(旧MicaSense)社が提供するRedEdge-P(Standalone/PSDK)は高解像度マルチスペクトル画像の取得が可能でパンクロマチックセンサが付属した唯一無二のマ...
2023年9月14日

エドモンド・オプティクス売れ筋の光学関連製品が見やすく掲載されたカタログ。アプリケーションノート(技術解説)や10以上の選定ガイドも掲載。※エドモンド...
2023年3月29日

Allied Vision はドイツに本社を持つ、産業・工業用カメラメーカーです。当社では主に以下製品を手掛けております。◆Alviumカメラシリーズ:ALVIUM®テクノロ...
2024年1月17日

Alvium カメラシリーズの小型・軽量・堅牢性を持ちながら、Sony社製のInGaAsセンサ:IMX990を搭載したSWIRカメラです。様々な筐体バリエーションをお選び頂く...
2024年1月24日

1200-2200nmの波長領域をカバーした、SWIRカメラです。一般的なSWIRカメラよりも高い波長帯域の2200nmまでをカバーしており、今まで撮影が不可能だった画像の...
2024年1月23日

Alvium カメラシリーズは、お客様の多様なニーズに対応できるよう6つの異なるインターフェースをご用意しています。Alvium プラットフォームは、豊富な高品...
2024年1月24日

Sony製IMX992, 993を搭載した、Alvium SWIRカメラの新製品です。従来機種同等の波長範囲400-1,700nmを持ち、3M, 5Mの高画素に加えて更に低ノイズを実現した次...
2024年2月14日
近赤外カメラのカタログ14件分をまとめてダウンロードできます!お迷いの方は便利な無料の一括ダウンロード機能をご利用ください。














企業
株式会社ジェイエイアイコーポレーション オムロンセンテック株式会社 株式会社ジェピコ プライムテックエンジニアリング株式会社 エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社 Allied Vision Technologies ASIA PTE.LTD