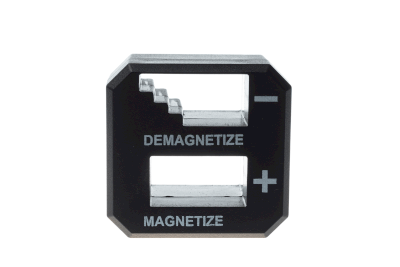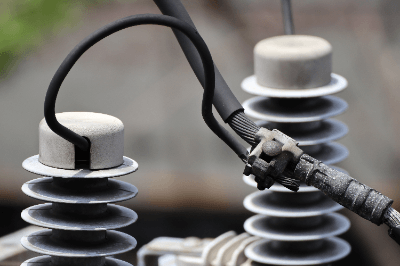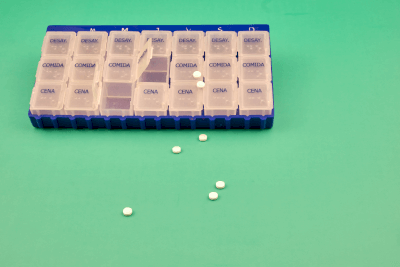背抜き手袋とは

背抜き手袋(英: Rubber Coated Safety Work Gloves) は、手のひら側にゴム素材で滑り止めを施した手袋です。
物を掴んだり、運ぶ作業に適しています。背抜き手袋の手の甲側には空気が抜けるようにナイロンやポリエステルのメッシュ素材の繊維が残っているため、通気性が高く長時間の作業でも蒸れにくいです。手のひら側は天然ゴムやニトリル、塩化ビニール、ポリウレタンなどでコーティングされています。
背抜き手袋の使用用途
背抜き手袋は土木、建築、運送、農業、園芸、機械整備、自動車関連、金属部品加工、組立塗装、精密組立、検査、梱包、倉庫作業など、長時間に渡ってしっかり握って持つ作業を行う分野で使われています。
主な背抜き手袋の使用例は以下の通りです。
- 室内工事作業時
- ガーデニング・DIY・荷運びなど
- 木材運搬時、ハードな荷作業
- 機械部品組立などの油を伴うハードな作業
- ウッドデッキの解体や組み立て、庭の木の剪定、掃除、雑草抜きなど
- 自転車やバイク整備
- 山林での仕事
- 薪の積み込み
- 金属の鑢がけ・穴あけ作業
- 塗装作業時、足場組立解体
背抜き手袋の原理
背抜き手袋は、手のひら側と手の甲側で繊維のコーティング有無が異なることにより、機能性が高められています。
手のひら側は樹脂やゴムでコーティングされており、物を掴むために強化・保護されています。手の甲側はコーティングされていません。生地は繊維のみで、通気性が高く、蒸れにくいことが特徴です。
背抜き手袋の種類
背抜き手袋はコーティング素材によって特徴が異なるため、使用用途に合ったものを選びます。
1. 天然ゴム
ナイロン素材の手のひら側に天然ゴムがコーティングされている背抜き手袋は、軟らかくて低温でも硬くなりません。薄くてフィット性が良く作業性も高いため、細かな作業に役立ちます。耐久性と強力なグリップ力がメリットですが、耐油性や耐溶剤性が低いことがデメリットです。
2. ニトリル
耐油性や耐摩耗性に優れたニトリルでコーティングされている背抜き手袋は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、薄くてグリップ力に優れています。細かい作業や自動車整備など油を使う作業に適していますが、低温では硬くなります。
3. 塩化ビニール
塩化ビニールでコーティングされた背抜き手袋は油や洗剤に強く、耐摩耗性や耐久性もあります。フィット性が良いため、手が疲れにくいです。安価で匂いも少ないですが、熱に弱いです。
4. ポリウレタン
ポリウレタン製の背抜き手袋は耐油性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
手の甲側の繊維部にポリエステルを使ったポリウレタンコーティング手袋は繊維ホコリが出にくいため、精密機械の組立作業などクリーンな作業にも使われます。
背抜き手袋のその他情報
背抜き手袋の特徴
一般的な軍手と比較して値段が高いですが、機能性は高いです。ただしコーティング素材によって特徴が異なる場合もあります。
1. グリップ力
手のひら側にコーティングが施されているため、軍手と比べて握る力が強いです。
2. 滑り止め
コーティングが施されているため、滑り止め効果が高いです。コーティングする素材によって様々な用途に適用可能です。
3. 通気性
背抜きのため、通気性に優れています。手の甲もコーティングされたオールコートタイプよりも蒸れず、快適に着用できます。
4. 薄手
軍手よりも薄手なため、動かしやすいです。
5. プリント
必要に応じてコーティングがない手の甲にデザインを印刷し、販促品やノベルティとして利用可能です。
参考文献
http://www.ss-sangyo.co.jp/back-gloves/
https://www.p-mizuho.com/
https://www.showaglove.co.jp/professional/type