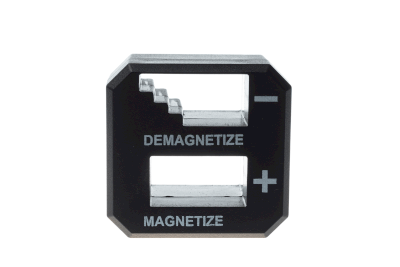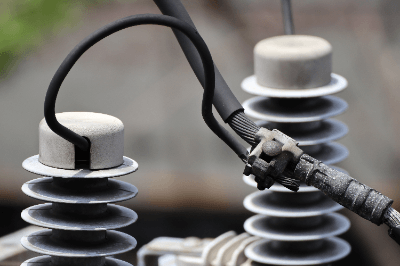下げ振りとは

下げ振りとは、構造物の垂直精度を確認するために用いる道具です。
紡錘形のおもりを糸の先端に有しており、下げ振り保持器から吊るした錘の垂直をみることで確認します。液体の入ったガラス容器中の気泡をみる水準器でも垂直を測ることができますが、重力を利用した原始的な下げ振りの方が比較的正確に垂直をみることができます。
また、糸とおもりの代わりにレーザーを使用した下げ振りも存在します。レーザータイプは風の影響を受けにくい構造になっており、糸の巻き取りも不要というメリットがありますが、取り付け面が傾いているとレーザーも傾いてしまうというデメリットもあります。精密な測定のため、補正機能の搭載された製品もあります。
下げ振りの使用用途
下げ振りは、建築や測量の分野で幅広く活用されています。その主な用途は以下の通りです。
1. 柱や壁の垂直確認
下げ振りは、建物の柱や壁が垂直に立っているかを確認するために使用されます。建築工事の際、下げ振りを用いて垂直を確認しながら施工することで、建物の安全性と美観を保てます。
2. 地墨上げ
下げ振りは、建築工事で基準となる垂直線を決める地墨上げにも用いられます。地墨上げとは、建物の基準となる位置を決めるために、垂直方向の基準線を設定することです。この測定具で鉛直基準を設定することで、正確な位置に建物を立てられます。
3. 配管工事での活用
下げ振りは、配管工事においても重要な役割を果たします。配管が垂直に設置されていることを確認するために、下げ振りが使用されます。これにより、配管の機能性と耐久性の確保が可能です。
4. 下げ振りの原理
下げ振りの原理は、重力の原理に基づいて鉛直方向を特定しています。吊り下げ部から延びる糸の末端におもりを取り付けており、重力の作用により、おもりが垂直方向に吊るされます。
糸の頂点と基部における座標を計測し、その距離が等しければ、測定対象は垂直であると判断できます。距離に差がある場合は、測定対象が傾いていることを示します。
下げ振りの構造
下げ振りは、下げ振り保持器、糸、おもりの3つの部分から構成されています。
1. 下げ振り保持器
下げ振り保持器は、糸を吊るすための部品です。壁面に固定するタイプと、三脚に固定するタイプがあります。
2. 糸
測定用の糸材には、耐久性と伸縮性に優れたものが選ばれます。一般的にはナイロン製の糸が用いられます。
3. おもり
おもりは、糸の先端に取り付けられ、重力により垂直方向に吊るされます。おもりの質量は製品の大きさや用途により様々で、一般的には100g〜1,000gの範囲のものが多く使用されています。
下げ振りの特徴
下げ振りは、以下の特徴を持っています。
1. 高い精度
重力を利用して垂直を測定するため、高い精度で垂直を確認できます。水準器と比較しても、より正確な測定が可能です。特に、長い距離での測定において、下げ振りの精度が発揮されます。
2. 簡単な操作
下げ振りは、取り付けが簡単で、特別な技術を必要としません。糸を吊るし、おもりを静止させるだけで、誰でも簡単に垂直を測定できます。一方、レーザータイプの下げ振りでは、ボタン操作だけで測定が可能であり、より簡便に使用できます。
3. 風の影響を受けやすい
下げ振りは、風の影響を受けやすいという特徴があります。特に屋外での使用では、風によっておもりが揺れ動き、正確な測定が難しくなるので注意が必要です。
下げ振りの選び方
下げ振りを選ぶ際は、以下の点に注意が必要です。
1. 用途に合ったタイプの選択
下げ振りには、糸タイプ、レーザータイプ、自動巻き取りタイプなど、様々なタイプがあります。使用する環境や目的に合わせて、適切なタイプを選択することが重要です。野外作業が中心の現場では、気流の干渉を抑制できるレーザータイプや、おもりにカバーが付いたものがおすすめです。
2. 精度の確認
下げ振りの精度は、製品によって異なります。高い精度が要求される現場では、より高精度の下げ振りを選ぶ必要があります。メーカーの公表する精度を確認する必要があります。
3. おもりの重量の選択
おもりの重量は、下げ振りの測定精度に影響します。重いおもりほど、風の影響を受けにくく、素早く静止します。ただし、重すぎると下げ振り保持器への負担が大きくなるため、適切な重量を選ぶことが大切です。
4. 糸の長さの確認
下げ振りの糸の長さは、測定可能な高さに影響します。高い場所での測定が必要な場合は、十分な長さの糸を持つ製品が必要です。また、糸の交換が可能な製品であれば、用途に応じて糸の長さを調整できます。