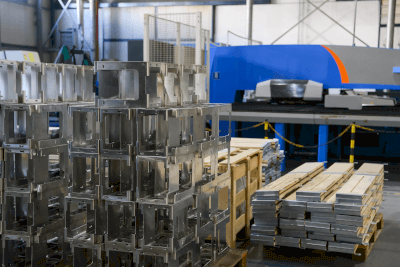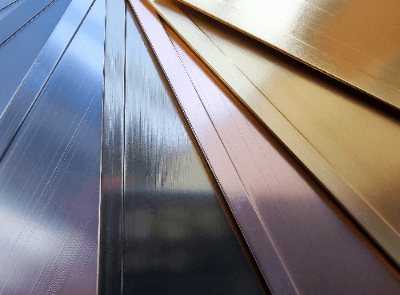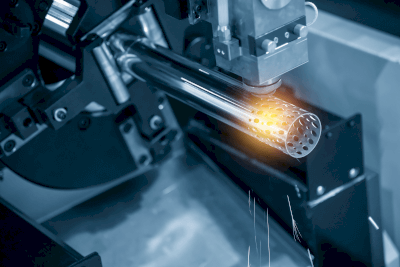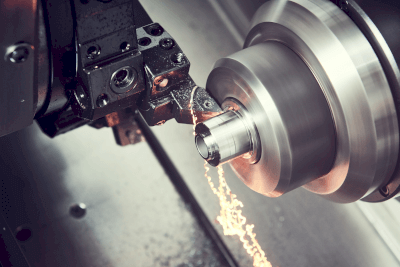PDFソフトとは

PDFソフトとは、PDFの作成や編集を行うアプリケーションソフトウェアのことです。現在では、さまざまなメーカーからPDFソフトに関連する製品が販売されています。
*PDF: 「Portable Document Format」の略称で、アドビシステムズ社(現:アドビ社)が開発した電子文書のファイル形式です。2008年に国際標準化機構(ISO)によって標準化されました。
PDFソフトの使用用途
PDFソフトを使用すると紙への出力が不要となるため、圧迫している書類の保管場所を紙使用時と比較して大きく削減できます。
2022年現在においては、コンピューターやスマートフォン、タブレット端末があれば、ウェブブラウザーやオペレーティングシステムなどにとらわれることなく、PDFソフトを利用することが可能であり、PCのみならず、端末のアプリ上でiOSやAndroid端末でPDFソフトは比較的多く利用されています。
PDFは「長期保管用のPDF/A」「エンジニアリング用のPDF/E」「印刷用のPDF/X」など、さまざまな種類があり、特定の目的に対応した規格にも適合しています。
また、障がいがあるユーザーが使いやすいように、あらゆるアクセシビリティ標準に準拠したPDFを作成することも可能です。PDFを作成する上で、セキュリティーは非常に重要な要素です。PDFは比較的利便性が高いため、公式な文書にも使用されています。
そのため、情報の漏えいや文書の改ざんなどに非常に注意しなければなりません。セキュリティーの例としては、パスワードによる文書の保護や公開鍵証明書(デジタルID)による文書の照明、電子封筒による暗号化、秘匿情報の削除、受信者側のセキュリティー対策などがあります。
PDFソフトのメリット
最近ではテレワークを推進する上で、文書の電子化が課題となりました。課題を解決するために最も安全な対策の一つは、紙文書のPDF化です。下記では、PDFソフトを活用するメリットを3つ解説します。
1. テレワークを推進する上で発生する問題を解決できる
PDFソフトの活用により、テレワークを推進する上で必要となる円滑なコミュニケーションやソフトウェアからの独立、セキュリティーに対する問題を解決できます。例えばPDFは、仮想のプリンターを用いてMicrosoft Wordなどの印刷機能から作成ができるため、極めて利便性に優れており、早急に資料を準備できるほか、PDFを共同で編集することも可能です。
また、円滑なコミュニケーションを妨げまげず、作成したPDFはソフトウェアに依存しないため、PDFリーダーがあれば、どこからでもPDFの閲覧と印刷ができます。
2. セキュリティー対策に効果的
PDFは、セキュリティー情報として、さまざまな設定をファイルに付加することが可能です。PDFは配布と閲覧が比較的簡便なため、重要な書類に対して閲覧や変更、複製、印刷制限を設定する必要があります。
これらを設定し、意図しない閲覧者を制限することで、重要な機密情報を守ることができます。さらに、PDFは電子署名を付加することも可能で、改ざんを防ぐ仕組みを取り入れられます。
3. 既存書類をPDF化できる
PDFは、既存の紙による書類も手軽にPDF化することが可能です。まず、印刷機のスキャン機能を利用して書類のデータを画像化し、PDFソフトウェアの光学文字認識機能(OCR)を用いて画像データから文字情報を抽出します。この2ステップにより、文字の検索や比較編集が可能となります。
以上のメリットはPDFソフトのクラウド化との併用により、より効果が期待され、昨今のソフト開発メーカーにおけるおすすめとなっています。
PDFソフトの選び方
PDFソフトを選ぶ際には、PDFファイルをどのように編集したいのかについて検討することが大切です。例えばPDFを社内で共有しながら共同で編集したいといった場合には、共同編集機能が付属した製品を選ぶ必要があります。
また、PDFを直接編集できるのかといったこともポイントになります。なぜなら、業務の効率化を図っているはずが、PDFに画像を差し込みたいのに画像を差し込めないといった問題や文字を直接入力できないといった問題が生じるからです。
さらに、おすすめのPDF編集ソフトとして販売されていても新しくテキストを追加するだけのような製品もあるため、機能面の確認はその詳細な内容を含めて、実際に何ができるのかを必ず比較しチェックすることをおすすめします。
最後のポイントとして、パスワード保護機能やOCR機能の付属有無が挙げられます。パスワード保護機能は、PDFファイルを暗号化して権限を付与する機能です。この機能により第三者への情報の漏洩リスクが減少します。
そして、OCR機能は、ファックスで受信した資料やPDFを画像化した資料などをPDFファイルとして編集できるようにする機能です。この機能があることで、メールで送られてきた資料などもPDFファイルとして編集可能になります。
PDFソフトのその他の情報
1. PDFソフトの価格
PDFソフトの価格は、オンライン版かダウンロード版かによって異なります。一般的にオンライン版は、月額課金方式の支払いで、価格は1,000円から1万円ほどです。
一方で、ダウンロード版はソフトウェアをコンピューターにダウンロードして利用するため、買い切り方式の支払い方法が一般的です。価格は、1,000円から5万円までと月額課金方式と比較して値段に差があり、内包しているおすすめ機能によって大きく異なります。
2. PDFソフトの機能
PDFソフトの機能には、主にPDF内の文章を修正する編集機能やPDFファイル同士を結合する機能が組み込まれています。そのほかにもPDFソフトには、さまざまなおすすめ機能が付加されている製品があります。例えば、PDFを分割する機能やPDF本体を圧縮する機能、PDFの順番を入れ替えたり、差し替えたりする機能などです。
PDFの分割に関しては、標準機能として備わっていることが多いです。しかし、PDF本体を圧縮する場合には、専用のPDF圧縮機能により、PDF容量を圧縮する必要があります。
一般的なZIP形式にする場合には、専用ソフトを使用せずに圧縮できますが、この方法では、PDF自体の容量を圧縮できません。また、多くのPDFソフトは、PDFをまとめることができてもPDFの順番を入れ替えたり、差し替えたりすることができないため、PDFの順番を変更できる機能があることで利便性が向上します。
3. PDFソフトのクラウド化
先に述べたようにコロナ対策なども含め、昨今のテレワーク化の推進に伴い、在宅勤務でのPDFソフトの活用が増えています。テレワークにおいては会社のLANやサーバー環境にアクセスする場合の利便性の向上とソフトウェアを使用するためのセキュリティー確保が課題の一つであり、この課題解決のため、ソフトウェアのクラウド化を進める企業も増えています。
なぜなら、クラウド化によってデバイスやネット環境などの外部環境に左右されずに、WEBにさえ接続できていれば、基本的にはどこででもセキュリティーに守られた環境下でソフトウェアの活用ができるためです。つまり、PDFソフトのクラウド化は、ソフトウェアの提供サービス全般における流れの一つと言えます。
よって最近ではクラウドを利用しデバイスにソフトをインストールすることなく、ブラウザのみでPDFを閲覧するだけではなく、PDFの作成や編集、OCR機能や共有まで備えテレワークでの使い勝手を向上させたPDFソフトウェアの製品も出てきました。
4. PDF SDKについて
クラウド化とともに、PDFソフトのもう一つの流れとしてPDF SDKがあります。SDKとは(Software Development Kit)の略であり、PDFソフトをWebソフトや自社のツール等に組み込みたいときにソフト開発キットとして活用されます。
PDF SDKでは、ソフト開発キットの機能としてプラグイン(機能拡張)機能や、外部ソフト間の通信でのPDFを制御する機能、Javaなどのスクリプトサポート、署名や検索および注釈、自社ソフトへのPDF編集埋め込み機能など、多彩な機能を豊富に用意されたアプリケーションライブラリやサンプルコードなどから活用することが可能です。
以上述べたようにソフト開発メーカーの昨今のPDFソフトのおすすめは、PDF SDKとクラウド対応版です。