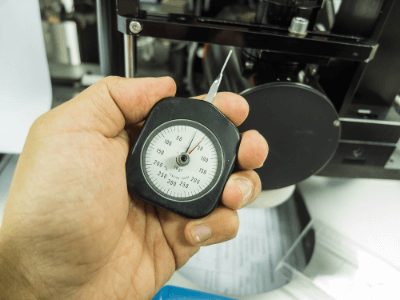エアーソーとは
エアーソーとは、空気を動力源として使用する切断工具です。
空気圧を利用して鋸刃を振動させ、さまざまな素材を切断するために使用されます。工業用途や金属加工などの分野で使用されることが多いです。エアーコンプレッサーなどの空気供給装置に接続され、圧縮空気を利用して動作します。
鋸刃が高速で振動することで、素材を効果的に切断することが可能です。一般的に小型で操作性が高く、精密な切断作業に向いています。エアーソーは高速で鋸刃を振動させるため、素材を迅速に切断できる点が特徴です。
これにより、作業効率が向上します。また、比較的シンプルな構造を持ち、少ない部品で構成されているため、耐久性が高い傾向があります。
エアーソーの使用用途
エアーソーはその高速で効率的な切断能力と精密性から、さまざまな産業および作業用途で使用されています。以下はエアーソーの一般的な使用用途です。
1. 金属加工
エアーソーは、金属製品の切断に広く使用されます。鉄やアルミニウムなどの金属シートや配管を切断するのに役立ちます。また、溶接作業の前に金属の形状を整えたり、不要な部分を切り取ったりする際にもエアーソーを使用することが可能です。
2. 建設現場
建設現場では、鉄筋を必要な長さに切断するためにエアーソーが使用される場合もあります。建設工事では木材や金属などの建材を切断する必要があり、エアーソーは多くの種類の建材を切断することができます。
3. 自動車
自動車修理において、エアーソーは排気パイプなどの切断に使用されます。古いパーツの取り外しや新しいパーツを取り付けする際に有利です。また、配管や樹脂、板金などの部品を手軽に切断したい際にもエアーソーが便利です。
4. 林業・木工
エアーソーは林業および木工業界でも使用されることがあります。特に大型の木材パネルや丸太の切断に便利です。木材切断において高速で効率的な切断を実現します。
エアーソーの原理
エアーソーの原理は、圧縮空気を利用して鋸刃を振動させ、切断作業を行う仕組みです。コンプレッサなどの圧縮空気供給装置から高圧の圧縮空気を供給されて動作します。
エアーソーには、圧縮空気を動力源とするエアーモーターが内蔵されています。エアーモーターは、供給された圧縮空気を受けて動力を生成することが可能です。鋸刃はエアーモーターに接続された振動機構に取り付けられ、高速で前後に振動することで切削が行われます。
切断対象の素材にエアーソーの鋸刃を接触させ、振動によって素材を切断します。鋸刃は素材を削り取るように振動し、切断面を形成することが可能です。刃の動作速度は空気圧によって変化しますが、調整つまみなどによってエアーの流入量を調節し、動作速度を変化させることが可能な製品も多いです。
また、切断できる材質はのこぎり刃によって異なります。木材用の刃でステンレスなどの硬い素材を切断すると、刃が劣化するため注意が必要です。
エアーソーの選び方
エアーソーを選ぶ際に考慮すべき要素が存在します。以下はエアーソーの選定要素です。
1. 切断能力
エアーソーの切断能力は、特定の素材をどれだけ深く切断できるかを示す指標です。作業に応じて必要な切断能力を確認し、エアーソーの仕様に注意し選定します。また、切断したい素材によってエアーソーを選ぶことも必要です。
2. 使用空気圧
エアーソーは最小必要空気圧が指定されています。エアーコンプレッサーが必要な圧力を供給できることを確保することが重要です。使用空気圧が不足すると、エアーソーの性能が低下します。
また、使用空気圧を大きく超えた圧力を印加した場合、エアーソーが破損する恐れがあります。エアーソーの最大圧力も確認することが必要です。一般的にはMPaなどの単位で表されます。
3. ストローク数
エアーソーのストローク数は、鋸刃が1分間に何回振動するかを示す指標です。高いストローク数は素材を迅速に切断しますが、低いストローク数のエアーソーは精密な作業に向いています。作業要件に合わせて選択します。

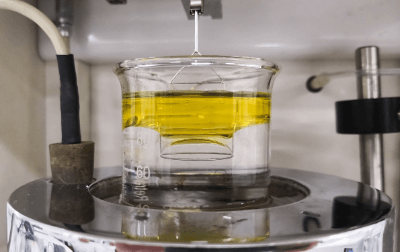
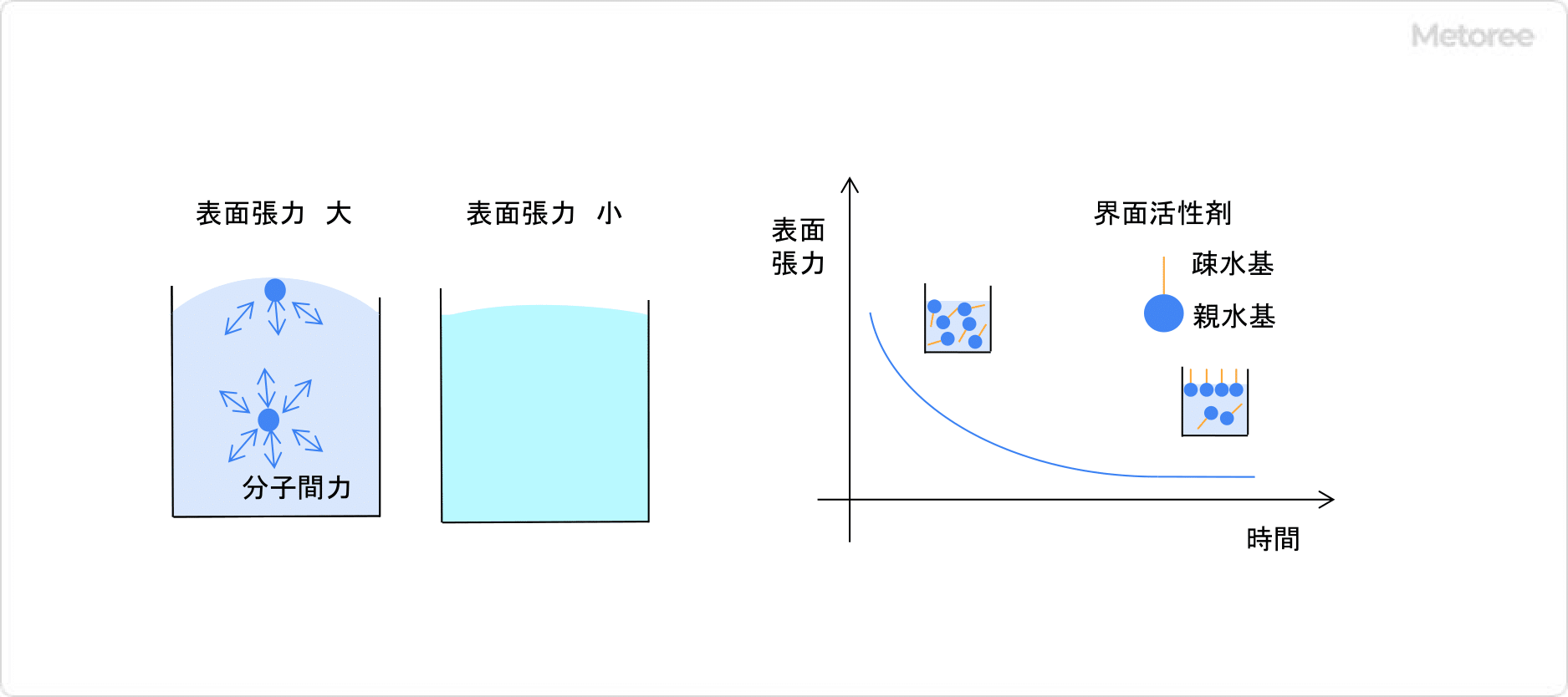
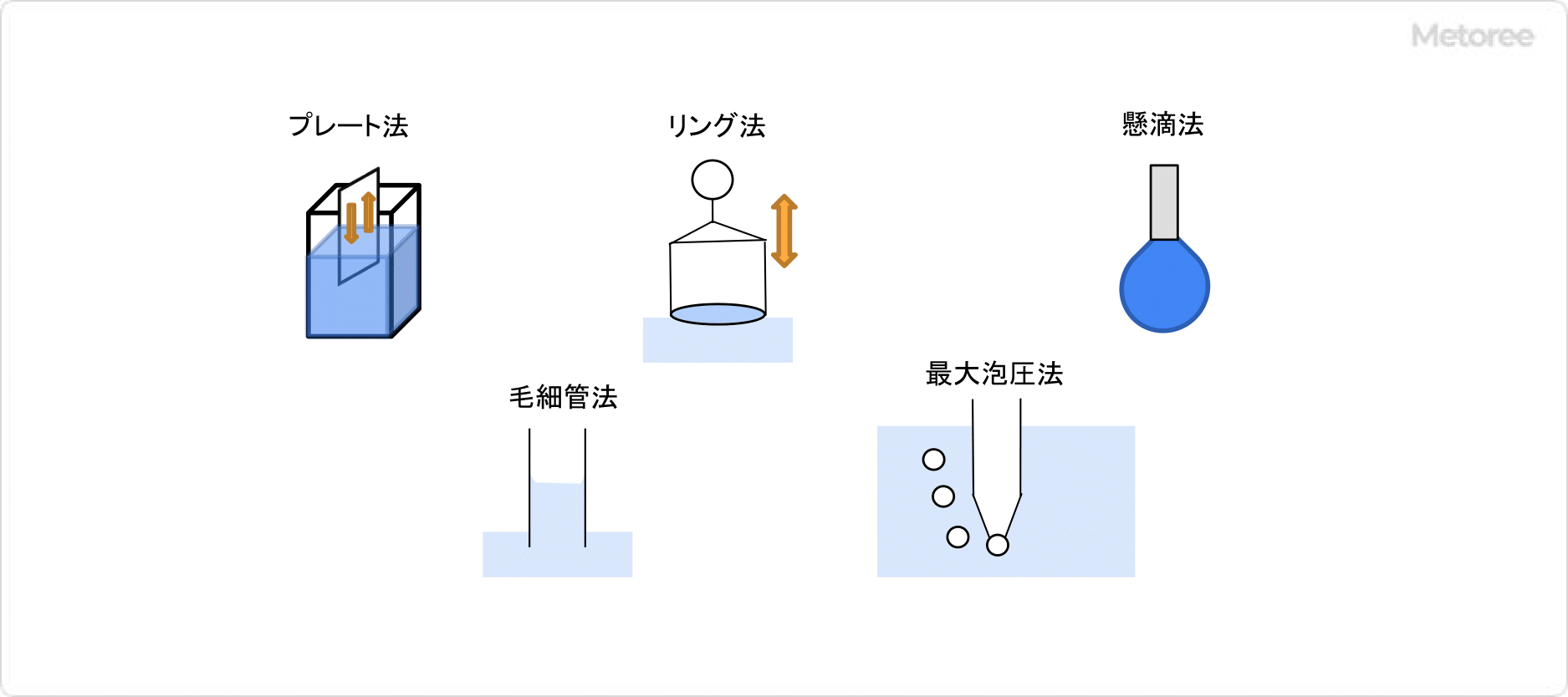
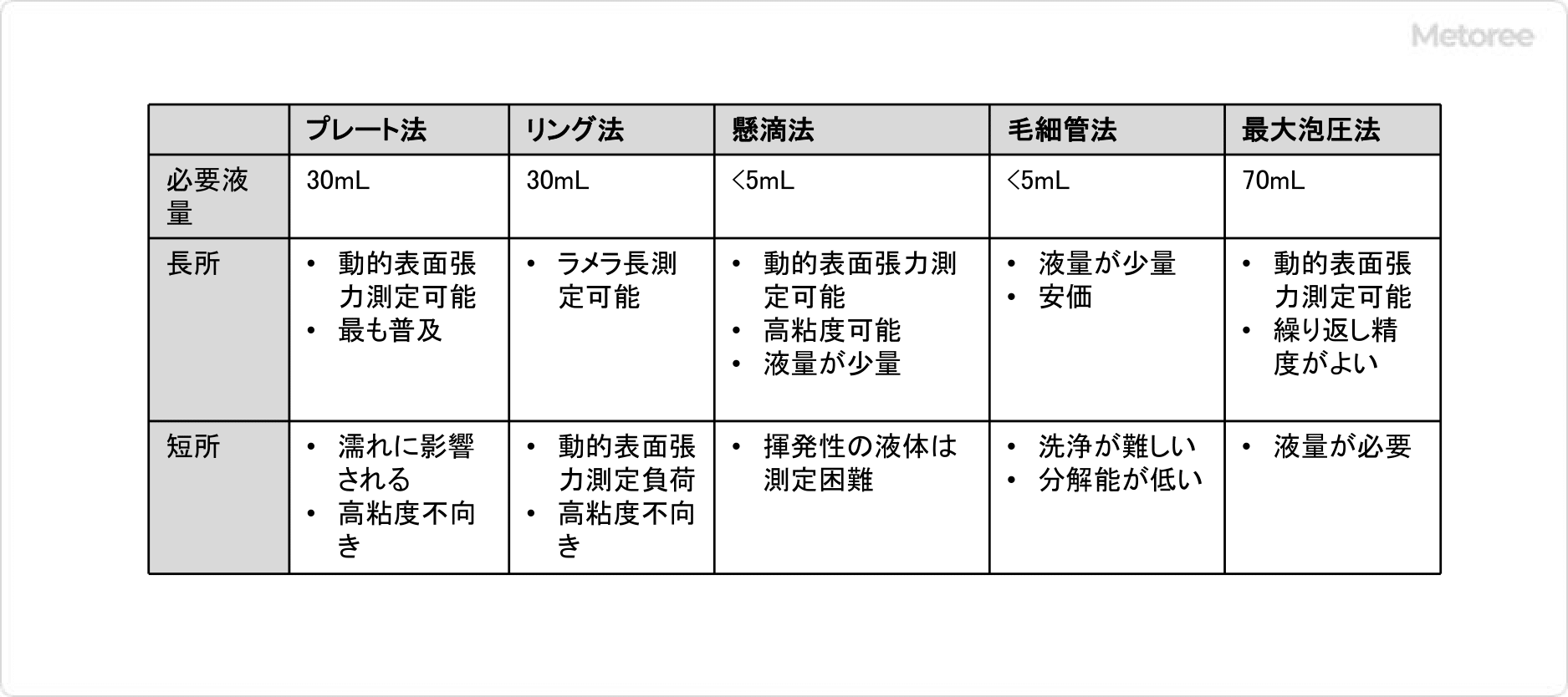



 かしめ工具とは、金属などの物体を塑性変形させることで2つの部品を密着させる工具です。
かしめ工具とは、金属などの物体を塑性変形させることで2つの部品を密着させる工具です。