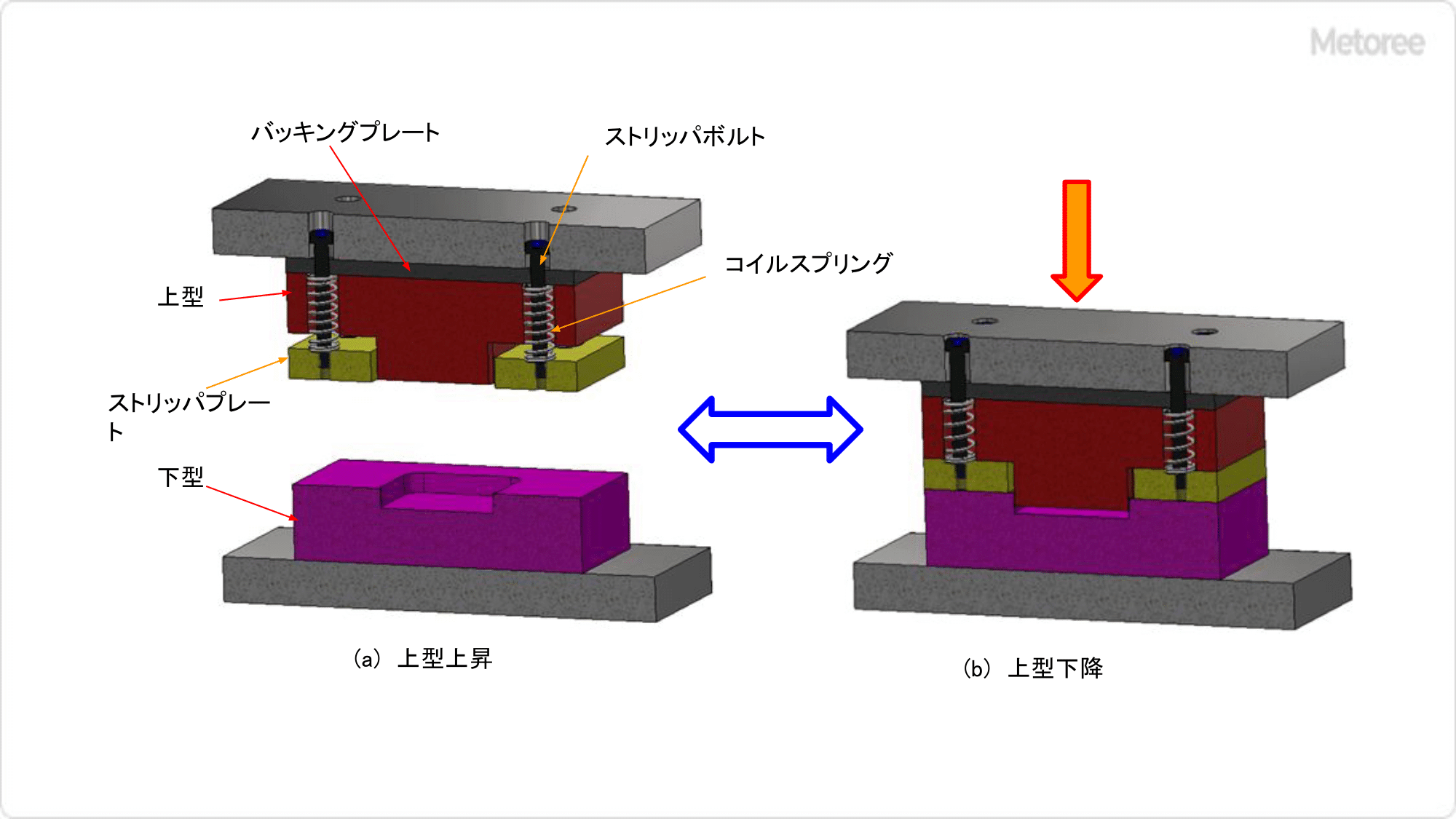ラバーシールとは
ラバーシールとは、ゴム製のシール材です。
ゴムの特性を活かしてパッキンやガスケット、オイルシールなどがあります。気密性が要求される分野では、クッション性が要求されます。一方、液体の漏れの防止が主目的であれば、強度が高く耐久性の優れた材質が使用されます。
ラバーシールの材料は主に、シリコン、NBR (ニトリルゴム) 、EPDM (エチレンプロピレンゴム) 、FKM (フッ素ゴム) などです。材質選定だけでなく設計によっても、密閉性能や耐久性が変わります。
ラバーシールの使用用途
ラバーシールは、各種特性のバランスがとれたニトリルゴム (NBR) を使ったものが多いですが、用途に応じて多くの品種が製造されています。主な使用用途は次のとおりです。
1. 自動車産業
自動車のエンジン、トランスミッション、ブレーキシステムには、高温・高圧・振動環境に耐えるラバーシールが不可欠です。
Oリングはエンジン内部でオイルや冷却水の漏れを防ぎ、リップシールは回転軸周りで潤滑油を保持しながら外部からの異物侵入を防ぎます。ガスケットはシリンダーヘッドや排気系で密閉性を確保し、排ガスの漏れ防止が可能です。特に、フッ素ゴム (FKM) やシリコンゴムなどの耐熱・耐油性に優れた素材が多用されます。
2. 産業機械・設備
産業機械の油圧・空圧システム、ポンプ、バルブには、高い耐久性と密閉性能を持つラバーシールが選定されます。
油圧シリンダーでは高圧作動油の漏れを防ぐパッキンが使用され、バルブシールは化学薬品や高温流体に耐えながら漏れ防止が可能です。軸シール (メカニカルシール) はポンプやモーターの回転部分に設置され、摺動部の摩耗を最小限に抑えながら密閉性を確保します。
3. 航空宇宙産業
航空機や宇宙機器では、極端な温度変化や高圧・真空環境に耐えるラバーシールが必要です。
フッ素ゴム (FKM) シールは耐熱性・耐薬品性に優れ、燃料系統や油圧システムでの密閉に適用されます。シリコンゴムシールは極低温環境でも柔軟性を維持し、航空機の窓枠やドア周辺での気密保持に最適です。また、宇宙開発ではPTFEコーティングを施したシールが採用され、高真空環境でのガス漏れ防止に貢献しています。
4. 医療・食品産業
医療機器や食品加工機器では、化学的に安定したラバーシールが求められます。
シリコンゴムは無毒性・耐熱性に優れ、オートクレーブ滅菌可能であるなど、医療機器のシール材として適切です。食品産業でも安全性の認められたラバーシールのみが使用可です。たとえば、アメリカに輸出する食品の保管には、FDA (米国食品医薬品局) 認証を受けたゴム材が使用されています。また、PTFE (テフロン) コーティングシールは強酸・強アルカリ環境でも劣化しにくく、化学薬品を扱う設備にも適しています。
5. 建築・インフラ
建築やインフラ設備では、防水性・気密性・耐久性を兼ね備えたラバーシールが使用されます。
窓枠やドアシールは、外部からの雨水や風の侵入を防ぎ、省エネルギー性能を向上させます。配管ジョイントシールは水道・ガス管の接合部で漏れを防止し、耐候性・耐薬品性のあるEPDMやNBRが一般的です。また、橋梁や高速道路などの伸縮継手にもラバーシールが活用され、温度変化や振動による構造へのダメージを軽減します。
ラバーシールの性質
ラバーシールの性質は気体や液体の漏れ防止に寄与します。
具体的な性質は以下のとおりです。
- 弾性
- 復元性
- 密閉性
- 耐久性
- 耐環境性
弾性によりシール面に密着し、微細な凹凸を埋めることで高い密閉性を確保します。復元性が高いほど、圧縮や変形後も元の形状を維持しやすく、長期間の使用が可能です。また、ラバーシールは温度変化、圧力、化学薬品、摩耗に対する耐性も求められます。
ラバーシールの形態には、あらかじめ成形されたゴムを隙間に押し込んで使用するものだけではなく、液体状のゴムを隙間に注入し、固化させることで用いるものもあります。僅かなすき間が許されず、取り外しを前提としない用途では、充填型のラバーシール材が多く採用されています。
ラバーシールの種類
ラバーシールの主な種類は、ガスケット、パッキン、Oリングです。
1. ガスケット
ガスケットは、静的なシール用途に用いられる固定型シール材で、フランジ接続部や配管継手、エンジンのシリンダーヘッドなどの密閉に使用されます。
ボルト締結により均等な圧力を加え、シール面の微細な凹凸を埋めることで流体の漏洩防止が可能です。耐熱・耐薬品・耐圧性に優れた素材を選ぶことで、過酷な環境下でも長期的な密閉性を維持できます。
2. パッキン
パッキンは、可動部の密閉に使用されるシール材で、回転運動や往復運動を伴う部位での流体漏れを防ぎます。
接触シールとして機能する場合は、シール面との適度な摩擦により密閉性を維持しながら、摺動性を確保する必要があります。耐摩耗性や低摩擦特性を持つ材質を選ぶことで、長寿命化とシール性向上が可能です。
3. Oリング
Oリングは、円形断面を持つシンプルな形状のシール材で、静的・動的シールの両方に対応可能です。
部品内の溝に装着され、圧力による自封作用で流体の漏洩を防ぎます。材質選定により、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性を向上させることができ、特定の流体や環境条件に最適化したシール性能を発揮します。
ラバーシールのその他情報
ラバーシールは、材質によって特徴が異なります。具体的な材質は下記のとおりです。
1. ニトリルゴム (NBR)
ニトリルゴム (NBR) は、耐油性、耐摩耗性、機械的強度に優れ、幅広い産業で使用される汎用性の高いシール材です。主成分であるアクリロニトリルの含有率を調整することで、耐油性や柔軟性を最適化できます。
一般的な鉱油やグリース、燃料油に強く、特にオイルシールやOリングに多用されます。また、耐熱温度は約-40℃~120℃と比較的広範囲に適応可能です。コスト面でも優れており、性能と価格のバランスが取れたゴム材料として、機械、車両、工業設備で多く採用されています。
2. アクリルゴム (ACM)
アクリルゴム (ACM) は、耐油性や耐熱性、耐オゾン性に優れており、トランスミッションなど駆動系機器に使用されています。特に、アクリルゴムはエステル系や鉱油系の潤滑油に強く、150℃以上の高温環境下でも安定した性能を維持します。
また、耐オゾン性・耐候性にも優れており、長期間の使用でも劣化しにくい特徴があります。ただし、アクリルゴムは-20℃以下の環境では硬化しやすいため、寒冷地での使用には適していません。価格はNBRより高いですが、高温・高負荷環境での耐久性を重視する用途に適しています。
3. ふっ素ゴム (FKM)
ふっ素ゴム (FKM) は、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れ、過酷な環境での使用が可能なシール材です。ふっ素ゴムはエンジンオイルや燃料、酸・アルカリなどの化学物質に強く、自動車のエンジンやトランスミッション、航空宇宙産業でのシール材として利用されます。
耐熱温度は約-20℃~250℃と非常に広く、高温下でも弾性やシール性を維持できます。一方で、低温環境では硬化しやすく、コストも高いため、用途に応じた慎重な選定が求められます。
4. エチレンプロピレンゴム (EPDM)
エチレンプロピレンゴム (EPDM) は、耐熱性・耐オゾン性・耐候性に優れ、水系流体やブレーキ液に適したシール材です。特に、冷却水システムや蒸気ラインのシール材として広く採用されており、150℃程度までの高温環境下でも優れた耐久性を発揮します。
また、電気絶縁性にも優れ、自動車のウェザーストリップや電気部品のシールにも使用されます。ただし、鉱油系の潤滑油や燃料には適さず、エンジンオイルやガソリンが接触する用途には使用できません。
5. スチレンブタジエンゴム (SBR)
スチレンブタジエンゴム (SBR) は、耐摩耗性に優れ、コストパフォーマンスの良い汎用ゴムの一つです。自動車のブレーキシステムに使用されるシール材として採用されており、摩耗しやすい部位でも長期間の使用に耐えられます。
また、耐衝撃性や弾性にも優れていますが、耐油性や耐薬品性には劣るため、工業用油や化学薬品を扱う用途には適していません。耐熱温度は約-50℃~100℃程度で、寒冷地でも比較的柔軟性を維持できる点が特徴です。
6. ウレタンゴム (AU)
ウレタンゴム (AU) は、耐摩耗性・耐熱性・耐オゾン性に優れた高強度のシール材で、特に建設機械や油圧システムのシールとして使用されています。他のゴムと比べて高い機械的強度を持ち、圧縮永久歪みが少なく、長期間の使用でも劣化しにくいのが特徴です。
また、硬度調整範囲が広く、用途に応じた最適な弾性を実現できます。耐油性にも優れていますが、水分や湿気の多い環境では加水分解を起こす可能性があり、適切な環境での使用が求められます。