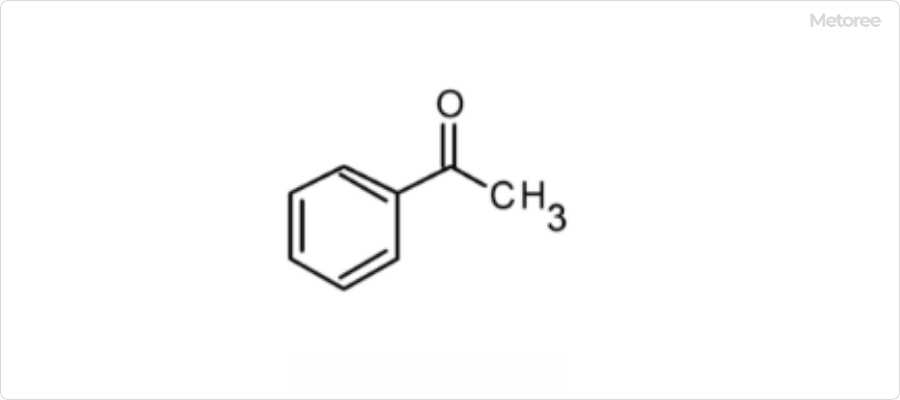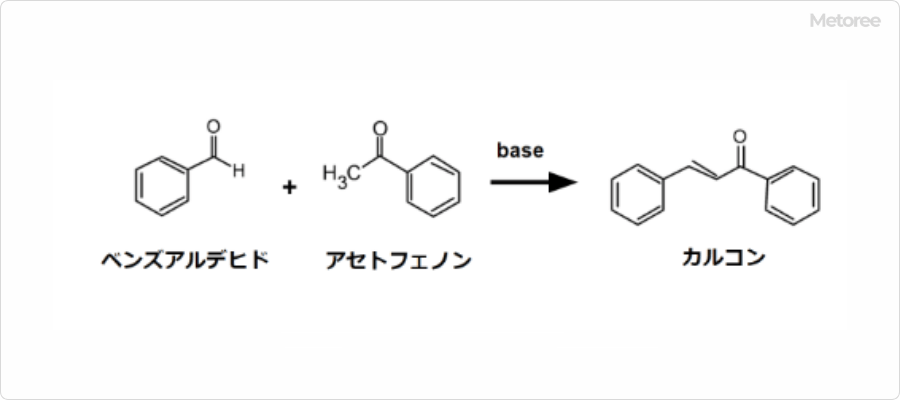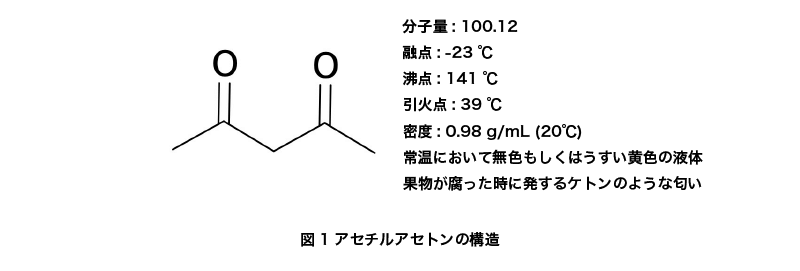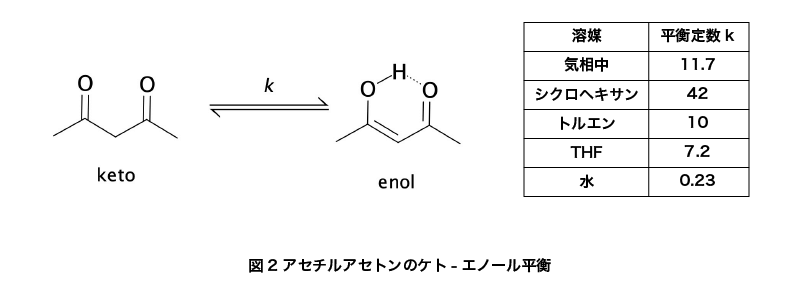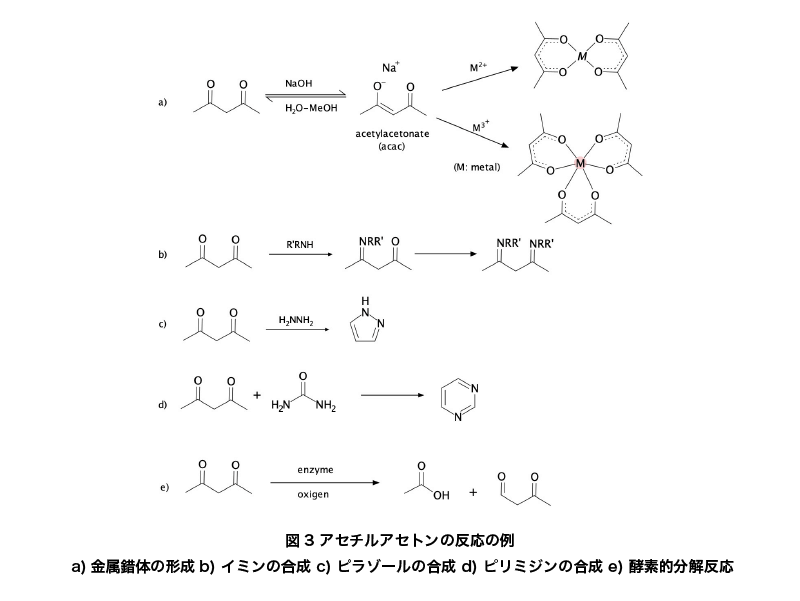アニリンとは
アニリンとは、 有機化合物の1種であり、化学式が C6H5NH2の芳香族アミンです。
別名として、アミノベンゼン、フェニルアミン、ベンゼンアミンなどがあります。
室温において無色透明な液状の化学物質ですが、徐々に澄紅色に変化し、空気中では赤褐色になります。人体に対し毒性があり、蒸気の吸入あるいは皮膚からの吸収により中毒を起こすので、取り扱いおよび保管には注意が必要です。
アニリンの使用用途
アニリンが単独で何らかの素材として用いられることはほとんどなく、他の化学物質の原料として用いられた後、多種多様な用途で使用されています。
1. 工業分野
工業分野においては、染料、顔料の原料や、ゴムの硫化促進剤、合成樹脂、プラスチックなどの原料として使用されます。
また導電性高分子であるポリアニリンの原料として用いられます。ポリアニリンは、高い電気伝導性や電気化学的安定性を持つことが特徴です。これらの性質から、電気化学センサーや電池やコンデンサなどの用途で使用されています。
2. 医薬分野
アニリンから合成された化合物が鎮痛薬、解熱薬、化膿疾患薬、抗アレルギー薬、ビタミンの調製に用いられます。
3. 農業分野
農薬、除草剤、殺菌剤の原料にも使用されます。
その他、火薬原料の原料や香料調薬、化粧品原料のハイドロキノンや、ウレタン樹脂の原料であるメチレンジフェニルジイソシアネートの原料として用いられています。また、ガソリンのアンチノック性を高める用途にも用いられます。
アニリンの性質
アニリンは分子量が93.13で、弱塩基性を示し、アミン臭があある物質です。また比重が1.022、融点は-6℃、沸点184℃で、水には難溶ですが、エーテル、エタノール、ベンゼンなどの有機溶剤に溶けやすい性質を持ちます。アルカリ金属、アルカリ土類金属と反応して水素を発生、アニリドを生成します。
アニリンのその他情報
1. アニリンの製造方法
アニリンの工業的な製造方法としては、以下の3種類があげられます。
ニトロベンゼンを塩酸で還元する方法
ニトロベンゼンに鉄の微粉と塩酸を混合して加熱し還元します。反応後、消石灰、硫酸アルミを加えて中和し、ろ過することで粗アニリンが得られます。これを減圧蒸留することでアニリンが得られます。
ニトロベンゼンを水素で接触還元する方法
水素気流中で銅、ニッケル、白金触媒の存在下で加熱還元します。水洗した後、油相側を減圧蒸留することでアニリンが得られます。
クロロベンゼンのアンモニア置換反応
クロロベンゼンを銅触媒の存在下、加圧加熱してアンモニアと反応させることで、塩酸が脱離してアニリンが生成します。
2. アニリンの安全性
アニリンは、皮膚や粘膜から吸収されます。皮膚からの吸収は速やかであり、短時間で血液中に吸収されることが知られています。また、吸入による毒性も報告されています。
毒性の症状 アニリンの毒性による症状には、貧血、腎臓障害、肝障害、神経障害、皮膚炎などがあり、暴露基準値や許容濃度が定められています。
アニリンを取扱う場合には、適切な防護対策が必要です。皮膚や目を保護するための防護具を着用すること、作業場所を換気すること、取り扱いや処理の際には、適切なマニュアルに基づいて作業することが重要です。
3. ポリアニリンについて
アニリンの主要用途として、導電性高分子のポリアニリンがあります。ポリアニリンはアニリンを電解重合することによって得られます。電解重合する際の溶液のpHによって、生成するポリアニリンの化学構造が変わり、性質の異なるポリアニリンが得られます。
塩酸や硫酸などで酸性にした水溶液中で電解酸化すると導電性の高いポリアニリンが得られます。この方法で得られたポリアニリンは、青色から緑色を呈しており、N-メチルピロリドンなどの有機溶媒に可溶で、塗工したりすることが可能で成型性に優れた材料です。
一方、中性やアルカリ性水溶液中での重合では絶縁性のポリアニリンが生成します。