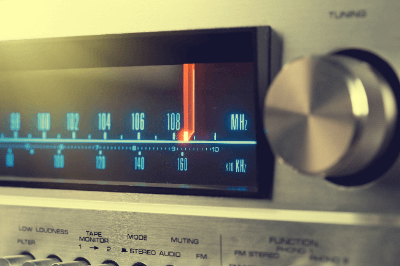超音波加工機とは
超音波加工機とは、超音波を使用して切削や研磨などの作業を行う機器のことです。
超音波加工機を使用した加工方法は、工具と工作物の間に切削油やスラリー状の砥粒を提供し、工作物の表面を少しずつ脆性破壊させて材料を除去することで行われます。硬脆材料に対して三次元形状の加工が可能であり、材料の導電性がなくても加工ができる点が特徴です。
超音波加工機は、超音波振動する振動子、振動子を駆動する発振器、刃物から構成されています。振動子は、高周波の電力を超音波振動に変換できる素子であり、工具と工作物の接触部分で高周波振動が発生します。高周波振動によって、工具が工作物に接触する瞬間に高いエネルギーが発生し、材料の加工が可能です。
金属加工やセラミックス加工などの分野で広く使用されており、高精度な加工が必要な場合にも適しています。また、導電性のない材料に対しても加工が可能であるため、難削材料や高価な材料の加工にも有用です。
超音波加工機の使用用途
超音波加工機は、硬脆材料や切削が難しい材料の加工に威力を発揮し、セラミックやカーボン繊維の切断、石英ガラスの加工、金型の研磨などに使用されています。また、超音波振動による微細な切断が可能なため、パンやケーキ、ピザの切り分けなど、超音波フードカッターとして商品化されています。超音波振動により刃と食材の摩擦抵抗が小さくなり、綺麗な切断面に仕上がります。
また、医療分野も用途の1つです。骨や歯の切削や摘出、白内障の手術において、超音波を利用した加工が行われます。また、超音波振動により組織や細胞を破壊する効果があり、がん治療や脂肪吸引などにも応用されています。
さらに、食品加工では、超音波振動を利用した乳化や分散、抽出、殺菌などが行われ、乳製品や調味料、ジュースや酒の生産でも、超音波加工は欠かせない技術です。
超音波加工機の原理
超音波加工機の原理は、超音波振動を利用して切削抵抗を低減させ、大きな加工スピードと高精度な切断をすることで成り立ちます。超音波振動を刃物に加えることで、摩擦抵抗を小さくし、硬い材料や一般的な機械加工では加工が難しい材料の加工が可能です。
超音波加工には、スピンドル加工と砥粒加工という2つの方式があり、それぞれ異なる原理で動作する点が特徴です。スピンドル加工は超音波振動を加工ジグに与え、ジグを回転させながら加工を行います。砥粒加工は超音波振動している加工ジグに砥粒を流し込み、少量ずつ粉砕加工します。
発振器は電力を超音波振動に変換する装置であり、振動子の作動周波数は刃物や砥石で変わるため、最適周波数に調整する電子回路が搭載されている点も特徴です。振動子は超音波振動を発生させるBL振動子や、振幅を拡大させる固定ホーン、振動を伝える刃物等で構成されています。刃物は用途に応じて使い分けることができます。
超音波加工機の種類
超音波加工機には主にカッター型超音波加工機、研削・研磨用超音波加工機、溶着用超音波加工機の3種類が存在します。
1. カッター型超音波加工機
カッター型超音波加工機は、刃物に超音波振動を与えて材料を切削する方式です。食品加工やプラスチックの裁断、医療器具の加工など、幅広い用途に利用されています。超音波振動によって、材料が溶着したり、熱変形したりすることが少なく、精度の高い切断が可能です。
2. 研削・研磨用超音波加工機
研削・研磨用超音波加工機は、砥粒を超音波振動させながら砥石を回転させることで、材料表面を研削・研磨する方式です。砥粒を微小に振動させることで、研削・研磨の効率を高め、表面粗さを減らせます。金属加工やセラミック加工などの精密な研削・研磨に利用されます。
3. 溶着用超音波加工機
溶着用超音波加工機は、超音波振動を利用してプラスチックや金属を溶着する方式です。接着剤を使用しないため、環境負荷が低く、接着剤を使用した場合よりも高い強度が得られます。自動車部品や電子部品などの組立に利用されます。
参考文献
http://usmaj.o.oo7.jp/kezuru.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasj/74/4/74_219/_pdf/-char/ja