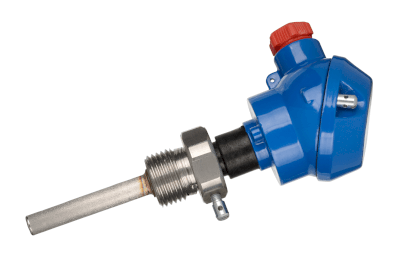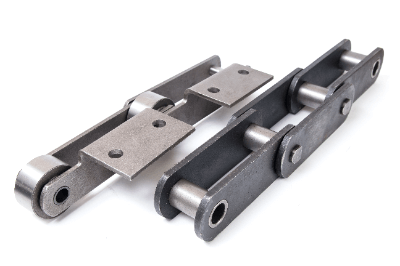ねじりばねとは
ねじりばね (英: torsion spring) とは、ねじり力を受けてねじれることによってエネルギーを蓄えるばねです。
ねじりコイルばねまたはトーションばねとも呼ばれます。洗濯ばさみなどの日用品から産業機器まで、広く使用されています。ねじりばねは小さな空間に収められるため、コンパクトな設計に適しています。
これにより、機械や装置のデザインに柔軟性を持たせることが可能です。また、適切な材料と設計のねじりばねは長い寿命を持ち、繰り返しのねじれと解放にも耐えられます。
ただし、ねじりばねは用いられるばね線の一部が強くねじれるため、その部分で応力が集中する可能性があります。これにより、一部に疲労や破損が発生する場合もあるので注意が必要です。
ねじりばねの使用用途
ねじりばねはさまざまな用途で使用されています。その特性を活かして、エネルギーの蓄積や制御、機械の動作などに利用されます。以下は使用例の一例です。
1. DVDドライブ
CDやDVDプレーヤーの蓋を手で軽く押すと、反動で開く仕組みに使われています。そのため、本体の電源を入れなくても開閉することが可能です。ばねを配置するだけで、モーターの配置が不要です。
2. 時計
機械式時計では、振り子やバランスホイールの振動が時計の正確な動作を保証します。ねじりばねはこの振動を制御する役割を果たす部品です。時計のメカニズムがねじりばねからエネルギーを受け取り、それを振り子やバランスホイールの振動に変換します。
3. 建築
ドアや窓の開閉機構にねじりばねが使われることがあります。ドアクローザーや自動ドアの動作制御に利用され、ドアの開閉をスムーズかつ簡単に制御することが可能です。
また、地震などの外部力に対して建物を安定させるため、ねじりばねが用いられる場合もあります。建物の構造に組み込まれ、地震時のねじれや振動を吸収する役割を果たす部品です。
4. 工業機械
工業プロセス内で多く存在するバルブの開閉制御に応用される場合もあります。ねじれ具合を制御することで、弁の開閉速度や力のバランスを調整し、プロセスの正確な制御を行います。
また、機械装置内で特定の部品の位置を調整するために利用される場合も多いです。部品の微調整や位置合わせを行う際に、ねじりばねを介して調整が可能です。
ねじりばねの原理
ねじりばねの原理は、ねじれによるエネルギー蓄積と解放に基づいています。ねじれはばねのばね線に圧力をかけ、その材料がねじれることでエネルギーが蓄積されます。その後、ねじれが解放されるとその蓄積されたエネルギーが解放されるプロセスです。ねじりばねは、捻じれることで材料に応力が加わります。
この応力によって分子間の結びつきが変化し、材料内部にエネルギーが蓄積されます。ねじりが進行するにつれて分子間の相互作用が変化し、ねじり圧力を蓄え貯めることが可能です。ねじりが蓄積されたねじりばねは、ねじりを解放する機構が作用することで解放しようとします。
このとき、ねじれエネルギーが材料内部から外部に向けて放出される仕組みです。ねじりが解放されると、エネルギーはばねの材料を元の形状に戻そうとする力として現れます。これによってねじりばねは元の形状に戻り、その過程で振動や運動を生じることが多いです。
ねじりばねの選び方
ねじりばねを選ぶ際には、さまざまな要素を考慮することが重要です。
1. 材質
ばねに採用される材質は、弾性率や耐久性に影響を与えます。一般的に高品質なばね鋼が材料となる場合も多いです。適切な材質を選ぶことで、ねじりばねが所望の性能を持つかどうかが決まります。
2. ばね定数
ばね定数は、応力とねじり角の関係を示す指標です。高いばね定数を持つねじりばねは、同じねじれ角でより大きな応力を発生させます。ばね定数はねじりばねの性能や用途に合わせて選定することが重要です。
3. 線径
線径は、ねじりばねのワイヤー太さを示します。線径が太い製品は一般に強い応力を持ちますが、同時に剛性も高くなります。適切な線径を選ぶことで、ねじりばねの強度や振る舞いを調整することが可能です。
4. ねじれ角
ねじれ角は、ねじりばねの角度です。ねじれ角が大きいねじりばねは多くのエネルギーを蓄積できる一方、そのねじれを解放するのに必要な力も大きくなります。本部品の用途や動作要件に応じて選択します。
5. 巻数
ねじりばねの巻数は、ねじりばねのワイヤが巻かれている回数です。巻数が多いねじりばねは同じ長さのワイヤをよりコンパクトに収めることができますが、それにより本部品の剛性も高まります。用途やスペースに応じて巻数を選ぶことが重要です。
参考文献
https://www.monotaro.com/s/pages/readingseries/kikaikiso_0306/