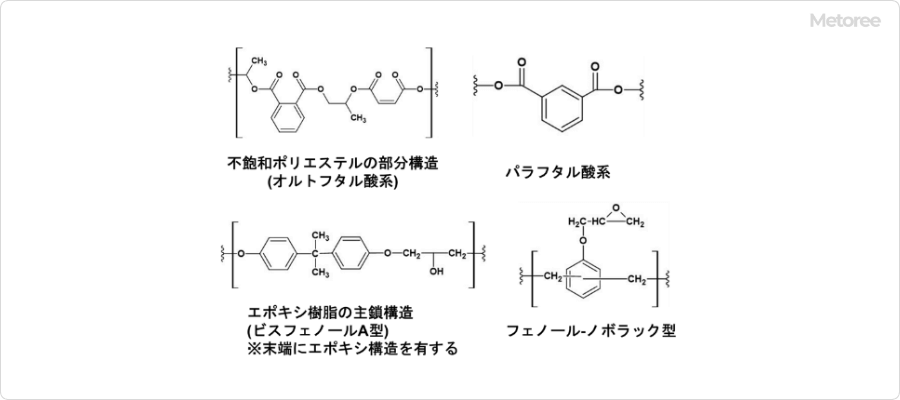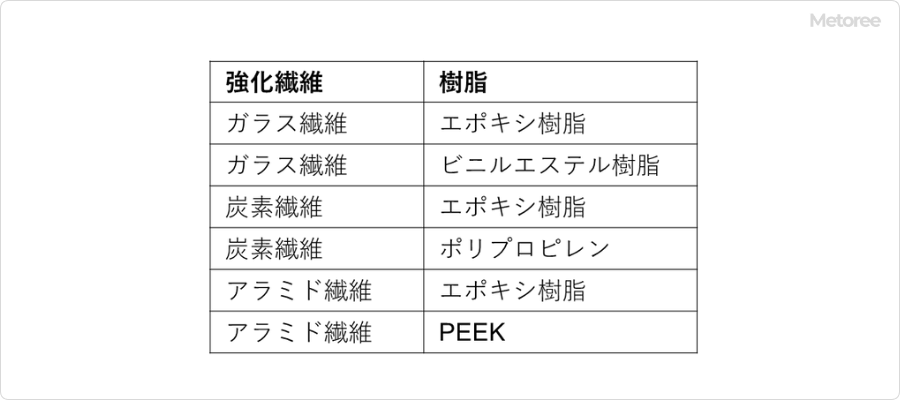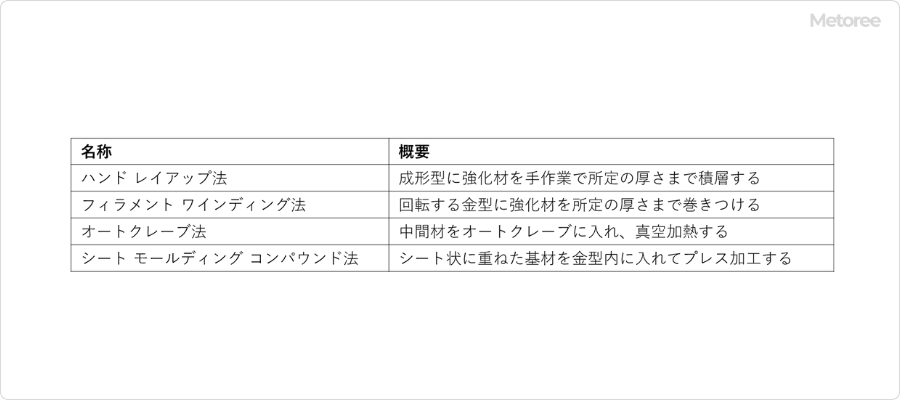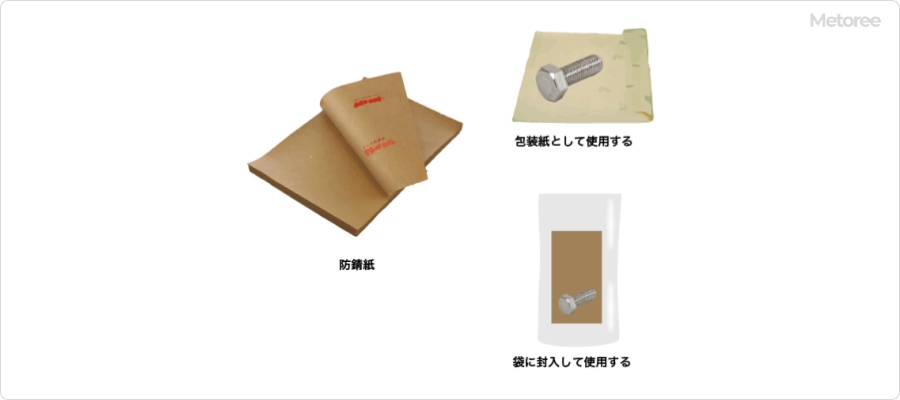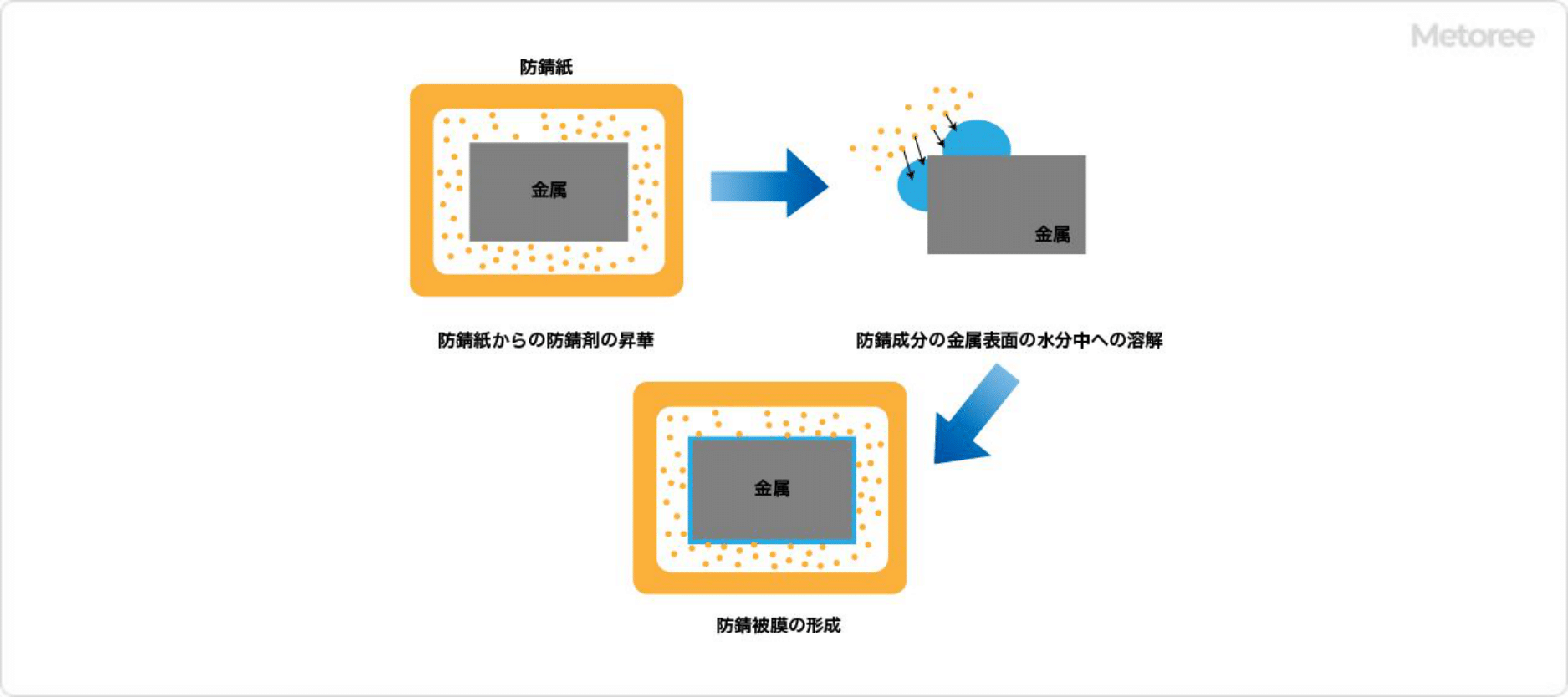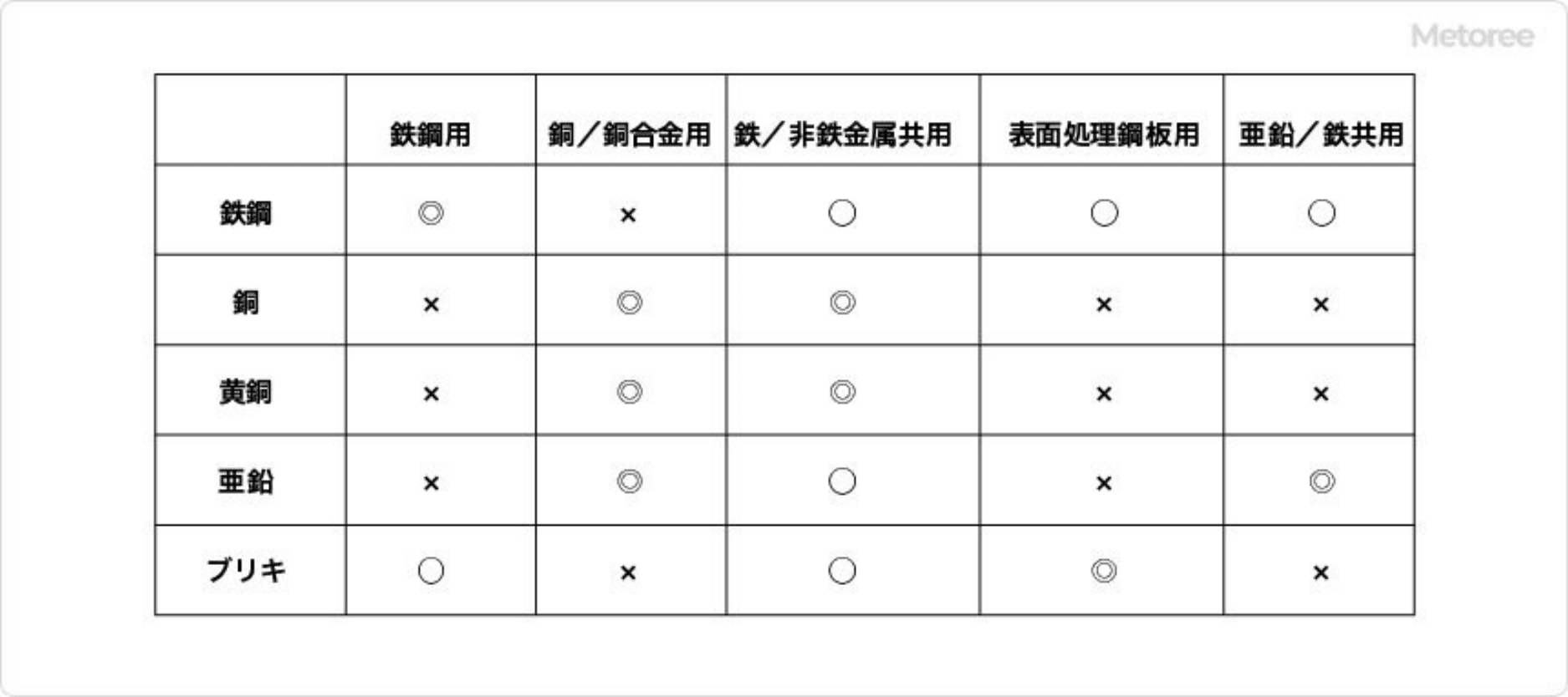鉄筋探査機とは
鉄筋探査機とは、コンクリート内部の鉄筋や水道管、電気配線などの位置や表面からの深さを測定する装置のことです。
鉄筋コンクリート造の建物の壁面内部は、施工された後で調べるためには、壁の一部を壊すか外部から非破壊で検査しなければなりません。鉄筋探査機は、非破壊検査に用いる検査機の一つであり、建物の構造や施工状態を確認したり、配線の切断などがないか確認したりするために使われます。
鉄筋コンクリート造の建物においては、鉄筋が上手く結合していなかったり配線が適した位置になかったりすると、事故の原因になりかねません。鉄筋探査機による調査は非破壊検査のため建造物を傷つける心配がないのはもちろん、比較的容易に検査をすることができます。
鉄筋探査機の使用用途
鉄筋探査機は、一般的にコンクリート建造物の中にある鉄筋や、それを覆う厚み (かぶり厚) を測定するために使われます。
1. 建物の品質管理
鉄筋コンクリート造の建物の主に強度に関する品質確認として、鉄筋の配置を把握するために使用されます。施工後の品質確認が主な利用目的です。
2. 建物改修時の調査
鉄筋コンクリート造の建物を改修する際に、実際に埋め込まれた鉄筋の位置や太さなどを知るために、鉄筋探査機が用いられます。古い建物の場合は図面が残っていなかったり、図面通りに鉄筋が配置されているとも限りません。建物改修時の現場調査として鉄筋の配置を知ることは、重要な工程になります。
3. 地下施設の調査
地下室には周囲の地面から大きな圧力が作用するため、鉄筋コンクリートで作られることが一般的です。地下施設の壁内には鉄筋以外に塩ビ管などのパイプが配置されていることもあり、鉄筋探査機による調査が行われます。
4. 耐震化工事の調査
地震に備えて耐震補強をする際にも、現状の鉄筋の配置を正しく知ることが重要です。鉄筋探査機によって、鉄筋や空洞についても正確に調べることによって、建物の耐震性能を正しく把握することができます。
鉄筋探査機の原理
鉄筋探査機は、鉄筋コンクリートなどの内部を調べるための非破壊検査機です。非破壊検査は対象物を傷つけることなくその内部の様子や状態を知るために、超音波、渦電流、放射線、電磁波など、私たちの目では見えない波動などを用いています。
現在の鉄筋探査機においては電磁波、または電磁誘導という現象を利用するのが一般的です。
鉄筋探査機の種類
鉄筋探査機は、測定方法により大きく次の2つに種類が分かれています。
1. 電磁波レーダー法
電磁波を用いてコンクリート内部を調べる方法です。電磁波とは、電界 (電場) と磁界 (磁場) が互いに作用しながら、空間を伝わっていく波のことです。空間は真空、気体や物質中を含みます。
電磁波は物質内部を固有の速度で直進するという性質がありますが、異なる物質同士が接する境界面があると、反射する性質があります。電磁波の異種材料の境界面で反射する性質によって、コンクリートと鉄筋との境界に関する情報を得ることが可能です。
電磁波レーダー法による鉄筋探査機には車輪が付いた駆動型のものが多く、コンクリート表面を移動させながら測定することで、より立体的な計測が可能となります。また電磁波はエックス線などの放射線のような危険性がないのも、広く用いられている理由の一つです。
2. 電磁誘導法
電磁誘導の原理を用いてコンクリート内部を調べる方法です。電磁誘導とは、金属線を束ねたコイルに磁石を近づけると、コイルに電気が流れる現象のことです。
電磁誘導法による鉄筋探査機では、電圧の変化を利用しています。電磁誘導の原理によって試験機のコイルに交流電流を流して磁場を生じさせると鉄筋にも電流が流れ、磁束が発生します。この変化を検出する事で内部の様子を確認することができます。
正確な精度で測定できる方法ですが、磁界の中に複数の磁性体が含まれると誤差が発生する可能性があります。
鉄筋探査機のその他情報
測定方法による違い
電磁レーダー法と電磁誘導法は、目的に応じて使い分ける必要があります。
電磁レーダー法は、コンクリート内部にある鉄筋はもちろん、空洞や塩ビ管の有無を調べることが可能です。電磁誘導法では調査対象は鉄筋のみに限られます。
電磁誘導法の特徴は、鉄筋径の推定ができることです。鉄筋コンクリートの強度は鉄筋の量や場所以外に、鉄筋の太さも重要な要素となります。
測定可能範囲にも違いがあります。電磁波レーダー法が表面から200mm~300mm程度であるのに対して、電磁誘導法は比較的浅い範囲の調査に適した方法です。
参考文献
https://www.rgk.jp/electromagnetic/