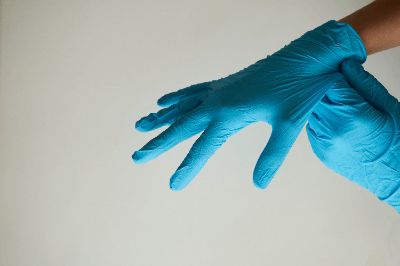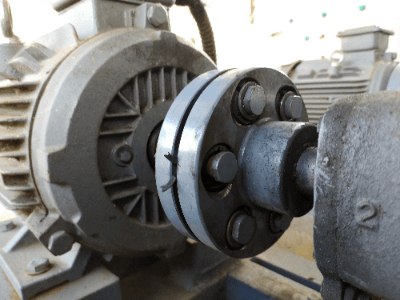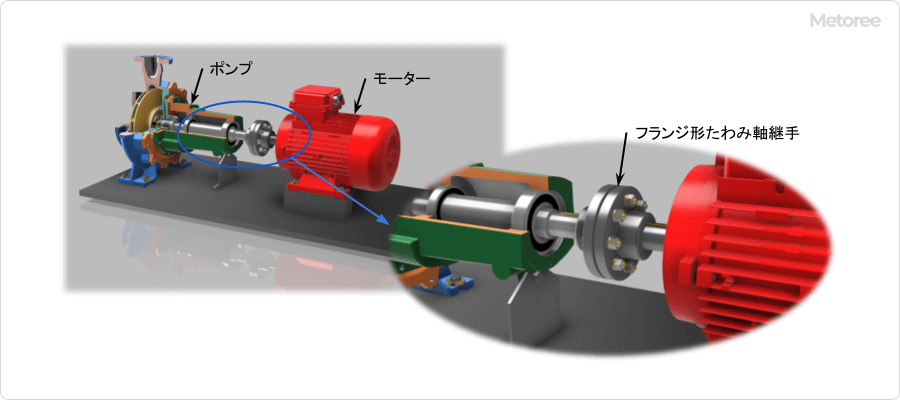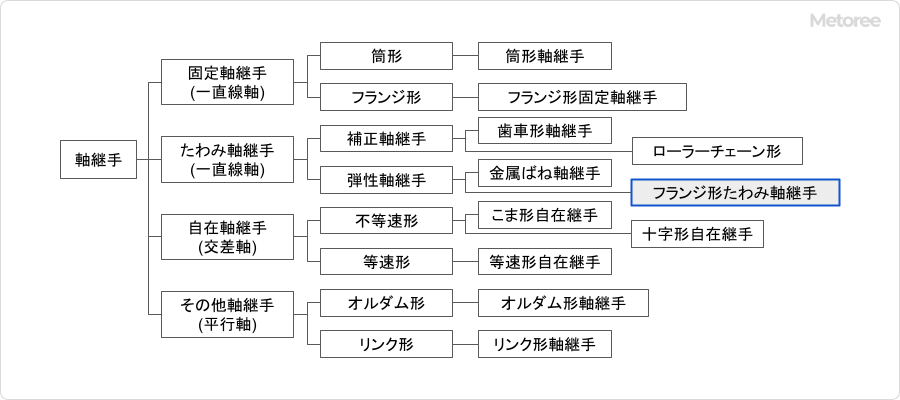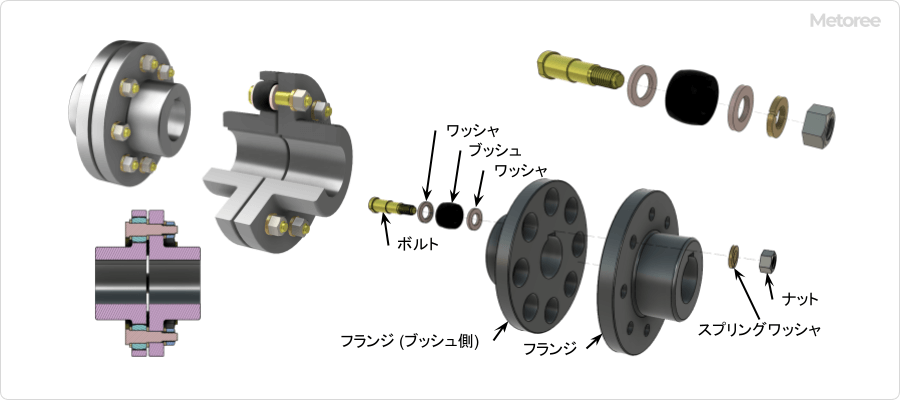はつり工具とは

はつり工具とは、コンクリート・石材の粉砕や、塗膜・タイルの床・錆・接着剤などを剥がしたり、木を彫刻するための工具です。
はつり (斫り) とはコンクリートや石材の壁などの建設物を粉砕する工事作業のことで、主に人手での作業を指します。はつり工具は、電動ハンマー、はつりハンマー、コンクリートブレイカーなどとも呼ばれます。電動剥離機は超高速の微小振動で粉塵が少なく、下地を傷めずに剥離や除去作業が可能です。電動彫刻機は彫刻ができる工具で、モーター内蔵型と軽いタイプのモーター別置型があります。
はつり工具の使用用途
はつり工具は人手で「はつる」作業用に用いる工具であるため、その使用用途は多岐に渡ります。
建築構造物や道路などの工事現場におけるコンクリートや石材、外壁の粉砕が、はつり工具の最も多い用途です。ただし工事の規模や粉砕する対象物によっては、よりパワーが必要な建機を活用する場合も多いです。
彫刻やタイル外壁の補修など、細かいはつり作業のための工具としての用途もあります。この場合は電動式のドリルが最も良く活用されています。日曜大工向けの電動ドリル工具もこの用途で用いられます。
はつり工具の原理
はつり工具を用いた加工対象物の剥離のさせ方には、ドリルなど工具先端の刃先の振動や打撃、回転の与え方が関わっています。一般に電動式は振動の周波数やドリルの回転数を広範囲に制御することに長けており、人手の作業で適した出力を得やすいため、電動式のはつり工具が多く存在します。
飛散する粉塵を削減したい場合には、振動数をあげたり刃先を対象物に押し付ける工法が効果的ですが、そのために必要な電力確保にはAC電源が良く活用されます。持ち運びに便利な電池式の充電タイプも多くあります。
はつりの工法としては、回転や振動以外に打撃で穴をあける場合も多いです。繊細な作業とコンクリート塊の粉砕などの比較的パワーが必要な作業とで、工具は使い分けられています。
はつり工具の種類
はつり工具の代表的な種類を以下で解説します。
1. 電動剝離機
電動剥離機は超高速の微小振動で剥離する工具です。粉塵が少なく、下地を傷めずに塗膜やタイル、さび、接着剤などの剥離や除去作業を実施したい場合に良く使用されます。専用の替刃を使うことにより、ビルの外壁など広範囲に利用することができます。ただし下地 (鉄かコンクリートか等) の確認が重要です。
2. 電動木彫機
電動木彫機は、振動する刃先を押し付けると彫刻できる工具です。飛び散りがなく、金属やガラス、木材、プラスチックなどの材質に彫刻が可能です。切れ味が悪い場合故障の原因になるため、刃先の状態には注意する必要があります。
3. たがねとチゼル
広義のはつり工具には、たがねやチゼルも含まれます。鋼鉄製の古くから用いられている鑿の工具です。チゼルの先端は尖った板状であり、刃の反対方向をハンマーで打ち付けて使用します。コンクリートなどの構造物に使用可能なものと、木材など比較的柔らかい構造物に使用可能なものに区分されているため、用いる工具の仕様には注意が必要です。
はつり工具のその他情報
1. コンクリートブレーカー
電動式ハンディタイプのドリルや打撃ではつり作業を行えないような、広範囲かつ厚みの厚い構造物を粉砕する場合には、コンクリートブレーカーと呼ばれる工具が用いられています。
コンクリートブレーカーはその名の通りコンクリートを破壊するための工具であり、粉砕のための大きなパワーを得るために、エアーホースでコンプレッサーからの空気を送って動作する工具です。道路工事で比較的多く用いられますが、エアーコンプレッサーやエアーホースなど現場に持ち込まないといけない備品も多いです。
より大規模なコンクリート粉砕には、ショベルカーやバックボウと呼ばれる専用の建機が用いられます。人手でのはつり作業の範疇外であるため、一般にははつり工具とは呼ばれません。
2. シュミットハンマー
コンクリートブレーカーと対比される用語に「シュミットハンマー」があります。シュミットハンマーはコンクリートハンマーとも称されますが、用途がコンクリートブレーカーと異なります。
シュミットハンマーはコンクリートの強度を計測するための工具です。内蔵されているばねの力で構造物 (コンクリート) の表面を打撃し、その反発係数を利用してコンクリートの圧縮強度を計測します。非破壊で対象となる構造物の強度を解析可能であることから、建築現場や土木現場で広く用いられている構造物の強度品質の試験解析用工具です。
参考文献
https://jp.misumi-ec.com/vona2/fs_processing/T0700000000/T0730000000/
https://www.monotaro.com/s/c-21932/
https://www.bildy.jp/mag/hammerdrill-guide/
https://diytools1.com/2016/06/30/post-15653/#i-3