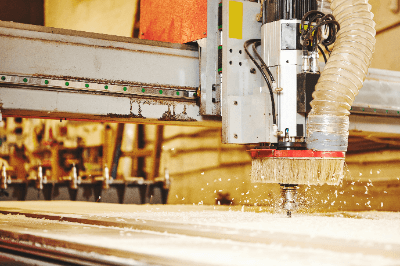ケーブルテスタとは
ケーブルテスタとは、通信機器を接続するケーブルが正常に性能を発揮しているかをテストする機器のことです。
たとえばLANケーブルテスタの場合、ネットワークケーブルの導通・断線・結線ミスなどをテストできます。
配線技術者が使う場合、工事の後にケーブルが正しく配線されているか、仕様で定めた伝送性能を満たしているかどうかを確認します。配線技術者にとり、ケーブルが適切に導通していることを証明する手続きに欠かせない機器です。
ケーブルテスタの使用用途
ケーブルテスタの主な用途は、通信機器を接続するケーブルの導通具合をテストすることです。断線などの問題がないかどうかを確認するためにも使われます。具体的には、次のような用途があります。
- 建物内の配線工事後の確認
- 通信設備の確認
- 複雑な配線に発生する異常箇所の特定
- 通信機器のネットワークスピードの確認
- 異常発生時のトラブルシューティング
通信機器の接続状態に不具合が発生すると、原因を判別するための時間がかかります。機器本体に問題があるのか、ケーブルに問題があるのかを見分ける必要があります。
ケーブルテスタがあれば、すぐに異常箇所を特定できます。そして、余計な工数をかけることなくトラブルシューティングが可能です。
ケーブルテスタの原理
ケーブルテスタは、ケーブルの物理特性を測定します。測定対象は、導通・損失・反射などです。ケーブルの種類によって原理もさまざまです。銅線などのメタル素材の物理特性を測定するのが一般的です。
光ケーブルの通信接続をテストする機器は、ロステスタあるいはOTDR (Optical Time Domain Reflectometer) と呼ばれますが、ここでは詳しく取り上げません。
ケーブルテスタは、電気量を可視化することで通信機器の接続状態を表示します。以下に2つの測定モードをとりあげ、ケーブルテスタの原理を説明します。
1. 抵抗測定モード
断線が疑われる場合によく使われるのは「抵抗測定モード」です。断線しやすい箇所を前後左右に折曲げ、抵抗値の変化を見ます。テスターが「0.L」や「0.F」、あるいは「∞(無限)」を表示すれば、それが断線箇所です。
あるいは、断線箇所が一時的に接触すれば抵抗値が変化するため、ケーブルを慎重に折り曲げて変化を確認します。抜き差しできる場合やプラグ付きのケーブルは、クリップ付きのケーブルで段階的にプラグ間を短絡させ、断線を確認します。
2. 静電容量測定モード
ほかに「静電容量測定モード」という測定方法もあります。ケーブルには長さに比例した静電容量があるため、標準ケーブルの静電容量よりも著しく低下する箇所を見つけ、断線を特定する方法です。
この測定モードは静電容量を比較するため、微量な差しかでない短めのケーブルには向いていません。一方、長めの同軸ケーブルなどには適しています。
ケーブルテスタの種類
ケーブルテスタを使用する頻度が多いのはLANケーブルです。このLANケーブルの性能を見極めることに特化した試験器を「LANケーブルテスタ」といいます。
LANケーブルには1本のコードに8本の信号線が入っており、4組の「より対線」構成です。「より対線」とは、2本の信号線をねじり合わせて1組にしたものです。
4組の「より対線」うち何組を使うかは、イーサネットの規格 (1000BASE-T、10GBASE-T、100BASE-Tなど) により決まります。また、規格により信号の送り方も異なります。
そのため、LANケーブルの両極を適切な「より対線」で接続することが不可欠です。接続方法を間違えると、たとえ電流が流れたとしても、適切に信号を送受信できません。
適切に信号を送受信できているかを調べるため、LANケーブル専用のLANケーブルテスタが必要になります。LANケーブルテスタの他にもHDMIケーブルテスタやUSBケーブルテスタなど、ケーブルに応じたテスタがあります。
長距離を結ぶケーブルが複数存在するため、ケーブル同士の対応関係が判断できない場合でも、同種のケーブルを識別できるケーブルテスタが利用可能です。
ケーブルテスタの選び方
ケーブルテスタにはコストパフォーマンスが良いものから数十万円という高価なものまであります。ケーブルテスタの使用目的をよく考えて選ぶことが大切です。
複雑な配線や線種の接続性を同時にチェックできるものや、手動ではなく自動でテストできるものといった、多機能なテスタは高価です。最低限のチェック機能があればよい、ある一定のケーブルを扱えればよい場合は、安価なものですみます。
しかし、取り扱うケーブルの種類が多い、テストしたい項目が複雑であるなどの理由で、結果的に所持する機器の数が増えてしまうと、維持管理に工数がかかります。余計な工数や費用がかからないよう、使用目的を明確にした上で、予算に合ったケーブルテスタを選ぶことが必要です。
参考文献
https://xtech.nikkei.com/it/atcl/column/17/030700071/030700001/
https://xtech.nikkei.com/it/atcl/column/17/012300631/