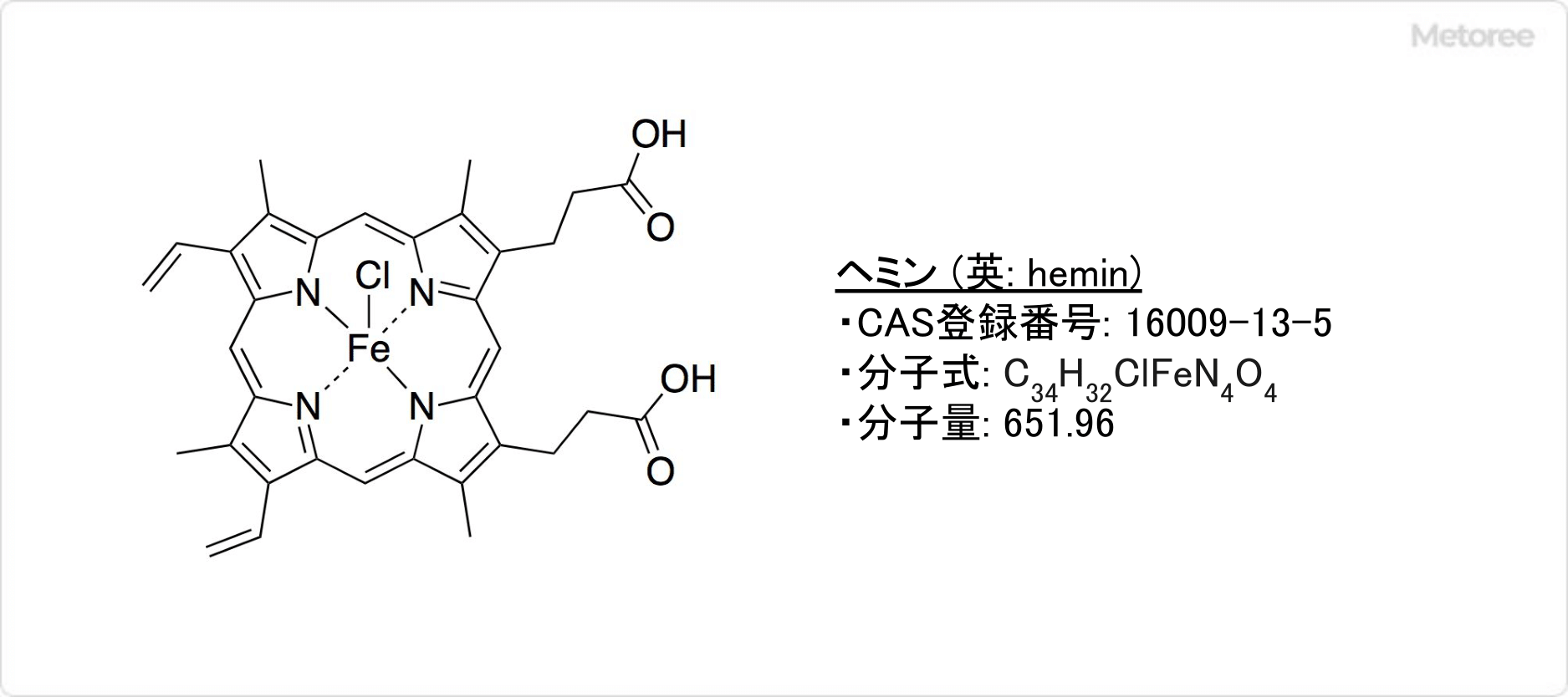ペリルアルデヒドとは

ペリルアルデヒドとは、シソ科の植物に豊富に含まれる有機化合物で、無色かうすい褐色の澄明な液体です。
ペリルアルデヒドはシソ属の学名であるPerillaに由来した名称であり、由来のとおりシソ特有の香りを放つことが特長です。香り特性だけでなく、抗菌・抗炎症作用といった性質も有しています。
抗菌作用を持つペリルアルデヒドは、食中毒予防や解熱を目的として食品添加物や生薬などに応用されています。日本やアメリカなどで食品添加物の認可が下りており、安全性が担保されている物質です。
ペリルアルデヒドの使用用途
ペリルアルデヒドは特徴的な香りを持ち、抗菌・抗炎症作用を有する化合物であるため、さまざまな用途で使用されています。
1. 食品添加物
食品添加物は、ペリルアルデヒドの主要用途の1つです。ペリルアルデヒドは抗菌作用を持ち、食品に添加すると防腐剤として働きます。お刺身のパックによくシソが添えられているのは、ペリルアルデヒドによる防腐効果 (食中毒予防) のためです。ペリルアルデヒドは肉の加工品やアルコール飲料などに使われています。
2. 香料
シソ特有の香り成分を持っており、香料としても使用されています。シソの香りはペリルアルデヒド、リモネン (英: limonene) 、ピネン (英: pinene) などの精油成分によるものですが、大半はペリルアルデヒド由来です。スッキリとした爽やかな香りであり、アロマオイルのような香料産業の製品に活用されています。
3. 医薬品原料
生薬や漢方薬も用途の1つです。ペリルアルデヒドは抗菌・抗炎症作用を持っており、解熱や解毒、鎮咳、整腸などの効果があります。嘔吐腹痛や気管支炎、神経痛などの処方生薬として配合されます。
ペリルアルデヒドの性質
ペリルアルデヒドは、以下に示すさまざまな性質を持っています。
1. 抗菌作用
ペリルアルデヒドの主な特長の1つが抗菌作用です。ペリルアルデヒドは、酵母菌や納豆菌などの増殖を抑える効果が報告されています。直接的に菌の増殖を抑制するだけでなく、腸の炎症を抑える作用もあり、腸環境を整えられます。
2. 香り特性
ペリルアルデヒドは、シソを連想させる生葉の香りを放つことが特長です。ペリルアルデヒドが持つシソの香りは臭覚を刺激し、食欲を増進させる効果があります。一方、昆虫・害虫はシソの香りが苦手なため、防虫剤としても活用可能です。
ペリルアルデヒドの構造
ペリルアルデヒドは立体的異性性のある化合物であり、以下に示す化学構造を持ちます。
1. ペリルアルデヒドの基本構造
ペリルアルデヒドは化学式がC10H14O (分子量150.22) で、シクロヘキサン環の4位にイソプロペニル基 (CH2=C(CH3)-) 、1位にホルミル基 (-CHO) が結合した構造です。ペリルアルデヒドは、シクロヘキサン環に2つの官能基が結合したことで、芳香性という物理的特性を発揮します。
2. ペリルアルデヒドの立体異性性

図2. ペリルアルデヒドの鏡像異性体の構造
ペリルアルデヒドは、 (-) -ペリルアルデヒドと (+) -ペリルアルデヒドの鏡像異性体があります。鏡像異性体とは、鏡に映し出された像のように互いに重ね合わせられない構造のことです。鏡像異性体となる物質同士の物理的化学的特性は同じですが、光に関する性質が異なります。
ペリルアルデヒドの鏡像異性体のなかで、天然のシソ中に含まれるものは (-) -ペリルアルデヒドです。
ペリルアルデヒドのその他情報
1. ペリルアルデヒドの物理的化学的性質
ペリルアルデヒドは、以下のような物理的化学的性質を持ちます。
ペリルアルデヒドのCAS登録番号は2111-75-3です。国内法規上の適用法令は消防法のみで、「危険物第四類 第三石油類 危険等級Ⅲ」に指定されています。
2. ペリルアルデヒドの関連化合物

図3. ペリルアルデヒドの関連化合物の構造
ペリルアルデヒドの主な関連化合物は、以下のとおりです。
- ペリラアルコール
- ペリラルチン
ペリラアルコールはペリルアルデヒドから合成される化合物であり、香料として使用されます。
ペリラルチンは、ペリラ・シュガーの名前でも知られる物質で、紫蘇糖の主成分です。砂糖の主成分であるスクロースの2,000倍の甘みをもち、日本ではタバコ用の甘味料にも使用されていました。
参考文献
https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0116-2416JGHEJP.pdf
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/dt/html/GI_10_001/GI_10_001_2111-75-3.html