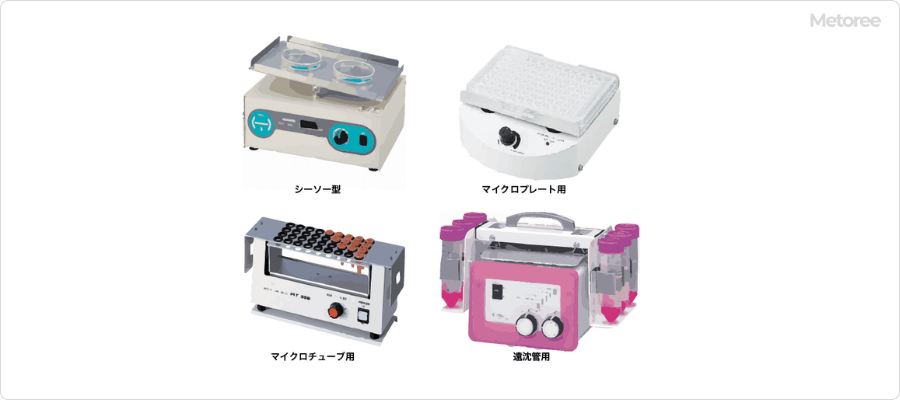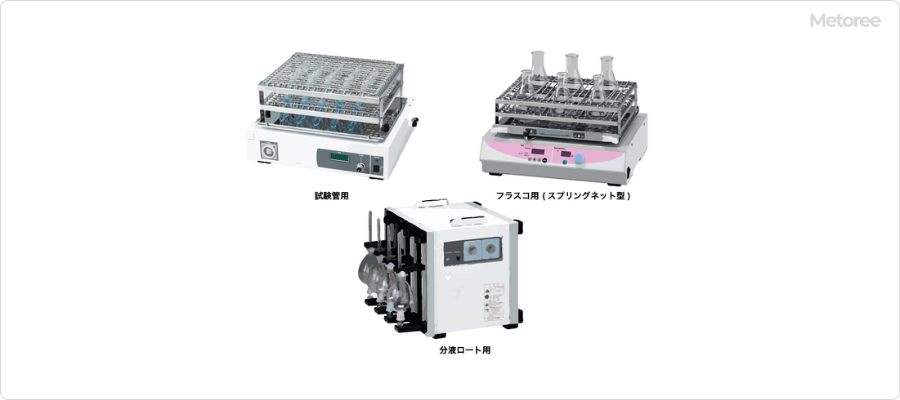積分球とは
積分球とは、光を均一に反射させる球状の装置のことです。
内部は酸化チタンなどの高い反射率を誇る光散乱材でコーティングされており、入射した光は様々な方向に多重反射します。積分球内で繰り返し光が反射することで、空間的に積分された均一な光を取り出すことができるのです。
大きさ数十センチの小さなものから数メートルの大きなものまで種類が豊富で、レーザーや光源の品質評価や研究機関の実験装置として広く用いられています。
積分球の使用用途
積分球は光を均一にして取り出す使い方と均一な光を放出する使い方があります。例えば、積分球で均一化された光は光源の強度の検出に適しています。また、反射率や透過率を測定する場合は、直接照射される光以外にも拡散による反射や透過を検出することができるのです。
さらに、積分球で均一化された光を放出する光源としても利用することもできます。球の内部で反射を繰り返すことによって強度が一定な光源を作り出すことが可能です。
積分球の原理
積分球の構造は非常にシンプルです。しかし、使用用途に応じて光が入射される方向や検出される部分が異なります。ここでは特徴的な反射率や透過率の測定原理についてご紹介します。
試料の反射率や透過率を測定する場合に、積分球は重要な装置です。積分球を使用することで直接サンプルに当たる光以外にも拡散によって生じた光の反射や透過を検出することができます。構造としては片側から光を入射させ、もう片側に試料を設置します。検出器は下部に設置し、直接光源からの光が入射しないようにすることが大切です。しかし、この方法は基準試料からの相対的な評価となるため、基準を正確に設定しておく必要があります。
これ以外にも光の検出や、光源としての利用方法があります。光は方向によって強度が異なる場合が多いため、反射と拡散を利用して均一化を図ることができる積分球は様々な場所で活躍します。主に大学などの研究機関で広く使われている装置です。
参考文献
https://www.systems-eng.co.jp/column/column02.html
https://www.ushio.co.jp/jp/technology/glossary/glossary_sa/ulbricht_sphere.html
https://www.an.shimadzu.co.jp/uv/support/lib/uvtalk/uvtalk5/basic.htm