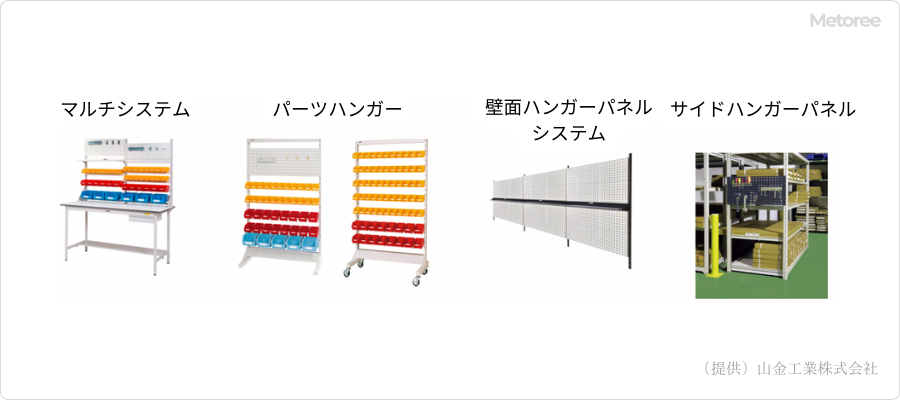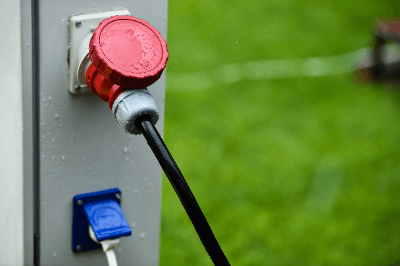パワーICとは
パワーICとは、パワー半導体を内蔵する集積回路 (IC: Integrated Circuit) の総称です。
パワー半導体は一般的に、大電力回路に使用される半導体を指します。パワー系の半導体にはパワートランジスタやパワーMOSFET、IGBTなどがあります。半導体材料の中で、特に1Aを超える大電流を制御する半導体部品をパワー半導体と呼びます。
パワー半導体には、トランジスタやサイリスタなどの電子部品も含まれます。
パワーICの使用用途
パワーICは、産業用機器や民生品機器の制御用ICとして非常に広く使用されています。大電力を扱うパワーICは低消費電力化が強く要望されており、半導体材料やデバイス技術、回路技術を中心に技術革新が進んでいます。
以下がパワーICの使用用途の例です。
- 太陽電池の駆動モジュール
- LED照明の点灯回路
- 電動自動車の制御用ユニット
- インバータエアコンのインバータユニット
昨今の電気自動車 (EV) やハイブリッド自動車 (HEV) の普及に伴い、車載ユニットの需要向上が顕著であり、今後パワーIC市場は拡大すると予想されています。
パワーICの原理
IC内部の回路により電圧や電流を制御し、各種機器への電力制御をおこなうのがパワーICの主な役割ですが、その機能は非常に多く多岐にわたります。例えば交流 (AC) 電圧を直流(DC)電圧へ変換する働きや、モーターの駆動、蓄電池への充放電を実現します。
その実現のためのIC内部の回路は、整流作用や、コンデンサや抵抗、インダクタ特性を回路素子の組み合わせをもとに利用する場合が多いです。アクティブ素子である半導体デバイスを使用して電源を高速スイッチングしたり、コンデンサで増幅・平滑化したりすることでACやDCの電源を制御しています。この種の機能を有するICはパワーマネージメントICとも呼ばれます。
パワーICならではの特徴として、その扱う電力の大きさから、パッケージや放熱設計には特に注意が必要です。放熱の悪い実装状態だと、電子部品としての信頼性を損なうばかりか、特性劣化を招くために、IC動作に際して十分な電気的な特性を期待できないためです。
低消費電力化の向けたICの回路面の取り組みとしてはインバーター回路があります。「インバーター」とは商用のAC電圧や交流周波数を自由に可変させるための回路でのことであり、モーター駆動やエアコンなどの変化する負荷状態に合わせた制御を低消費電力化させるため、よく用いられる回路です。
パワーICのその他情報
1. パワーIC用半導体デバイス
パワーICが内蔵する半導体デバイスには次のような素子が挙げられます。
ダイオード
- 一般整流ダイオード
- ショットキーバリアダイオード
- ツェナーダイオード
トランジスタ
- バイポーラトランジスタ
- MOSFET
- IGBT
最近では耐圧が高く高速スイッチングに優れたシリコンカーバイド (SiC) を使用したものもあります。その他、トランジスタや高耐圧ドライバーなどの各種ICを1パッケージに内蔵したインテリジェントパワーモジュール (IPM) も存在します。
2. パワーIC材料としてのSiCやGaN
SiC (シリコンカーバイド) は、シリコンと炭素から構成される化合物半導体です。
絶縁破壊電界強度がSiの約10倍、バンドギャップがSiの約3倍あり、次世代のパワー半導体材料として期待されています。これは同じ耐電圧であればSiよりも10倍ほど半導体層を薄くできることを意味します。薄型化によって抵抗が低減され、低消費電力で動作できるので、パワーIC材料としてSiCを使うことにより、低消費電力かつ高耐圧なICを作成できます。
その他パワー半導体材料としてGaN (ガリウムナイトライド) もPC向けの電源変換ケーブル向けなどに実用化されており、次世代向けにはGa2O3なども期待されています。
参考文献
https://www.shindengen.co.jp/products/semi/column/basic/semi/power_semi.html
https://www.fujielectric.co.jp/products/semiconductor/about/
https://eetimes.jp/ee/articles/2007/28/news027.html
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/semicon/1219080.html