リードフレームとは
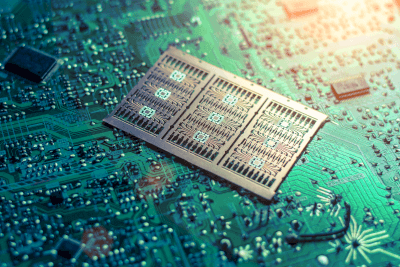
リードフレームとは、半導体デバイスのパッケージ内部に使われる金属製の接続薄板です。
トランジスタやIC、LSI、フォトカップラー、LEDなどのパッケージの内部に使われます。半導体素子の固定およびケース端子までの接続端子と放熱の役割も担うようにパターン設計されています。一般的に銅合金系や鉄合金系素材が使用され、プレス加工やエッチング技術によって配線パターンや外形形状が作られます。
リードフレームは、半導体デバイスの高集積化と高機能化を支える部品です。リードフレームがICや半導体デバイス特性を左右する側面もあり、導電率や熱伝導性の優れた金属材が使用されています。
リードフレームの使用用途
リードフレームは、電子部品を中心に、プリント基板に実装するためのパッケージの主要部品として非常に幅広く使用されています。主な用途を以下に記載します。
1. 半導体素子
トランジスタ、IC、LSI、フォトカップラー、LED、ダイオードなどが挙げられます。フォトカップラーは、光を用いて電気信号を伝送する部品のことです。トランジスタやダイオードは、半導体素子の一種で、電気信号を制御するために使用される電子部品のことです。ICは集積回路、LSI (英: Large Scale Integration) とは、大規模集積回路を指します。
2. 電子部品
コンデンサ、抵抗器、センサー、スイッチなどが挙げられます。センサーは圧力センサー、温度センサー等で、スイッチはタクトスイッチ等でリードフレームが使用されます。
3. 電気機器
リレー、モーター、バッテリーなどが挙げられます。
リードフレームの種類
1. リードレスパッケージ用リードフレーム
リードレスパッケージはQFN (Quad Flat Non-leaded package) とも呼ばれ、半導体パッケージのリードがないタイプのパッケージです。このパッケージ向けのリードフレームが該当します。上面からはリード端子は見えず、パッケージ裏面の端子から電気的な導通を取る構造です。実装面積を縮小したい場合に良く用いられています。
2.リ ードパッケージ用リードフレーム
最も多く普及しているタイプの一般的な半導体のパッケージ用リードフレームです。ICの外形サイズやピン数、形状等に応じて様々な形状のリードフレームがあります。ICを内部に搭載し、レジンモールドから外に出ているリード端子で電気的な導通を取るという点に特徴があります。
3. かしめリードフレーム
飛躍的な放熱性向上の為、ICを搭載するダイパッドとヒートシンクと呼ばれる放熱板をかしめ加工で固定したリードフレームです。放熱性を改善し高い信頼性を得るために用いられ、車載用にも使われている特殊リードフレームです。
リードフレームの原理
リードフレームの役目は、半導体素子と外界との電気的、機械的接続の確保です。リードフレームは主に金属の薄板で作られ、その中に複数の電極が配置されています。半導体素子はリードフレーム上に直接接続され、半導体素子の電気的接続を リードフレームを介して外部に伝えられます。
熱伝導性に優れ、半導体素子から発生する熱を外部に放出することも重要な役割です。素材自体の熱伝導性が高いため、半導体チップの発熱を吸収して効率的に放熱できます。またリードフレーム自体も表面積が広いため空気の流れを利用して熱を放出できます。
リードフレームに使われる金属は、主に銅合金や鉄合金です。これらの金属は優れた導電性能を持っているため、電気信号を効率的に伝送できます。またリードフレーム自体が電気回路の一部として働くこともあるため、高い導電性能が必要です。リードフレームの表面はめっきによってさらに導電性を向上できます。
リードフレームのその他情報
1. 信頼性
リードフレームは、半導体デバイスの高信頼性化に大きく貢献しています。デバイスの信頼性を確保するためにリードフレームの製造には高い精度が必要です。リードフレームは複数の機能を持ち合わせており、それらの機能を発揮するために、製造工程では高い品質管理が求められます。またリードフレームは繰り返し使用されることが多いため、信頼性を確保することが重要です。
2. 経済性
リードフレームは金属シートをプレス加工で製造できるため一度に大量生産が可能です。また表面処理や加工技術が進歩したことで高精度での製造が可能になり、高い信頼性を確保しつつも部品単価を抑えられます。このため多くの電子機器で利用されています。
3. 多様な形状
リードフレームは、金属板をプレス加工やエッチング技術を用いて形成することで、非常に多様な形状に対応できる部品です。よってリードフレームは非常に柔軟性が高く、様々な形状の半導体デバイスに適用できます。このような形状の自由度の高さは、半導体デバイスの設計自由度を高めて高機能化や高集積化に寄与しています。
エッチング技術は、材料の表面を化学的または物理的に削り取る加工技術のことです。主に金属や半導体などの薄膜の加工に用いられます。


