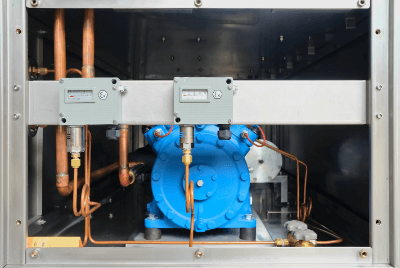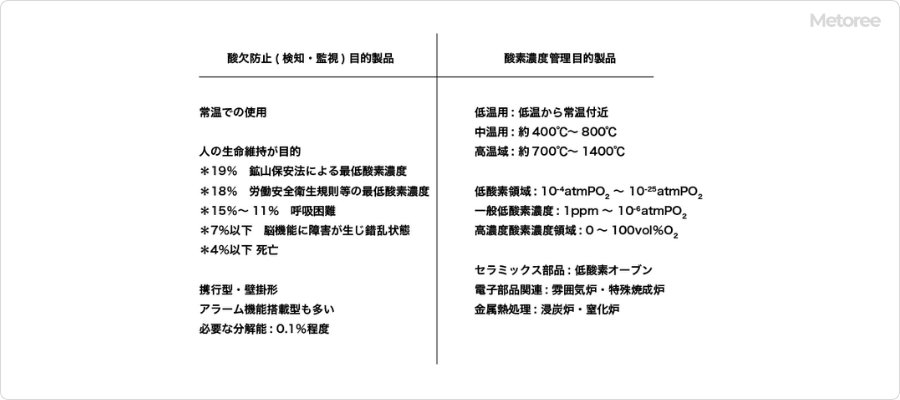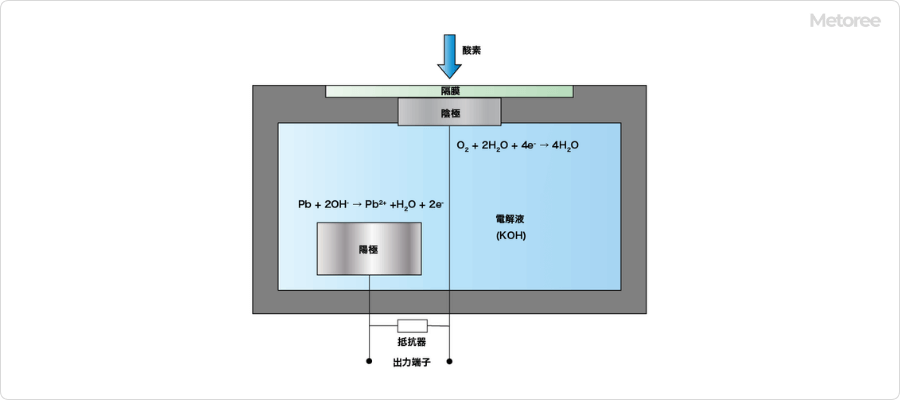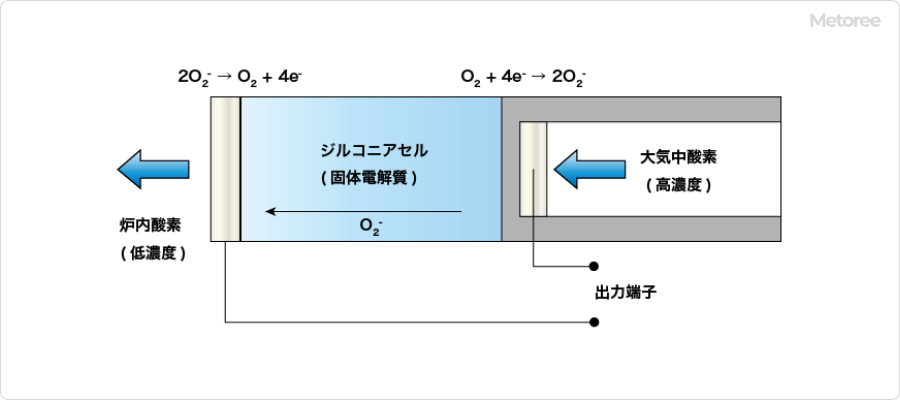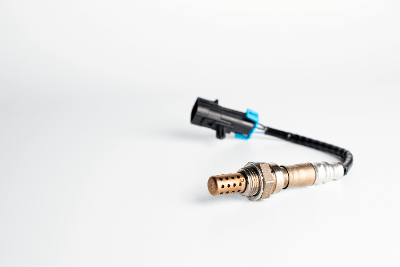離型剤とは
離型剤とは、金型を使った成形加工において、成形物の金型からの脱型性を軽くするための薬剤です。
金型は同じ形のものを素早く大量に製造するのに役立ちます。ただし、金型に材料を流し込んで成形するだけでは、綺麗に製品を金型から外すことができず、金型に張り付いてしまうトラブルが発生します。
離型剤は金型成形の際に、金型からの離型性を上げて、生産効率を改善するために使われます。
離型剤の使用用途
主な用途は、製造ラインで製品を作成するための金型成形作業です。その他、以下の用途が挙げられます。
1. 医療分野
人体からの剥離を容易にするために、手術用具や医療機器に使用されています。
2. 建築現場
コンクリートや石材の製造で、汚れや錆を防止できます。
3. 食品業界
食品の形状を作る金型や、容器や包装材料を製造するために使用されます。
4. 製造業界
プラスチックやゴム製品、鉄鋼製品、紙製品などの製造にも使用されています。これらの分野で使用される離型剤は、それぞれの材料に合わせて選択されます。
離型剤の原理
離型剤が金型と成形物との間に存在することにより、成形物が金型から外れやすくなります。離型剤は、金型成形する際には必ず使用するものです。なお、使い方と構成成分によって分類できます。
1. 使い方による分類
外部離型剤
金型に塗って使用するタイプの離型剤です。食品用途では、パン焼き用の型やフライパンにあらかじめ塗っておく油やマーガリンなどに相当します。塗るだけのタイプをはじめ、焼き付け型やスプレー型などがあります。
内部離型剤
成形する材料にあらかじめ混ぜて使用するタイプです。これは成形の際に材料が溶けて流動性が上がった状態で、金型と材料の界面に移行し、脱型時に離型性を向上させる効果を発揮します。用途によっては、外部離型剤、内部離型剤の両方を併用することもあります。
2. 構成成分による分類
組成面では、離型剤成分以外に含まれる成分から、水型、乳化型、溶剤型、ペースト型、オイル型などに分けられます。一般的に外部離型剤は、脱型後の製品本体への離型剤付着を防止するため、金型表面には極めて低濃度になるように塗布する必要があります。このため、溶媒により希釈された、水型、乳化型、溶剤型が用いられることが多いです。
離型剤の種類
離型剤成分の種類としては、大きく分けてワックス系、シリコーン系、フッ素系があります。成分により効果は大きく変わります。フッ素系は、手間が少ない分潤滑性が低いです。シリコーン系は、潤滑性が良いですが洗浄手間がかかります。
1. ワックス系
離型剤成分として、ワックスを使用したものです。ワックスとは油脂のことですが、主に低分子のポリエチレンなどが挙げられます。
金型と成形品との間に層を形成し、層の間で剥離を起こしますが、これを層間剥離と呼びます。塗装性に優れるのが特徴です。しかし、製品への転写量が多く、金型が汚れやすい不具合があります。
2. シリコーン系
ワックス関係と同様に層間剥離を行います。シリコーンオイル特有の優れた潤滑性を利用しているため、離型性が非常に高いです。こちらも同様に転写量が多く、金型が汚れやすい不具合があります。
3. フッ素系
フッ素の非粘着剤を利用しています。界面剥離を起こすことで離型性を向上させます。少ない使用量で離型効果を発現できるのが特徴です。
単独として高い潤滑性を持たせることが困難なので、シリコーンと合わせて利用される場合が多いです。
離型剤の選び方
まずは使用目的に応じて選ぶ必要があります。食品や医療品など特殊な用途には、特殊な離型剤が必要となるため、選定の際には使用目的をしっかりと把握しておくことが重要です。
1. 成形品の素材
離型剤は、成形品の素材によって選ぶ必要があります。成形品によっては特定の離型剤の使用が適している場合があるため、素材に合わせた選定を行うことが重要です。
2. 脱脂・洗浄の容易さ
離型剤の使用により成形品から剥離しやすくなりますが、逆に金型表面の離型剤が原因で汚れが発生する場合があります。特に大量生産を行う際は、脱脂・洗浄の容易さも考慮することが大切です。
3. 健康・環境への影響
離型剤によっては、健康や環境に悪影響を与える場合があります。特に医療用品や食品包装材料には注意が必要です。安全性や環境性に配慮した離型剤を選ぶことが求められます。
参考文献
http://www.seimichemical.co.jp/product/fluoro/mold/
https://www.sankyo-chem.com/wpsankyo/2516