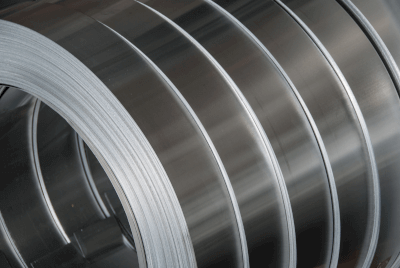快削黄銅とは
快削黄銅とは、主に銅と亜鉛を主成分とする黄銅合金に鉛やリンなどの添加物を混ぜ合わせて作られる、切削性に優れた材料のことです。
快削黄銅は、削りやすく機械加工に適しており、切削時の熱や摩擦による変色や変形が少ないため美しい仕上がりになります。快削黄銅は、JIS (日本産業規格) でC3601からC3605までの5種類が規定されています。快削黄銅は自動車部品、建築金物、電気製品の部品などに使用されています。また、装飾品や楽器などにも広く用いられています。
快削黄銅の使用用途
快削黄銅の主な使用用途は下記の通りです。
1. 自動車部品
エンジン部品、ブレーキ部品、燃料噴射装置などが挙げられます。自動車のエンジン部品では,インジェクターコネクタ、シリンダーヘッドガスケットなどが使用例です。
インジェクターコネクタは燃料噴射装置の一部で、燃料をシリンダー内に噴射するための部品です。シリンダーヘッドガスケットはシリンダーヘッドとシリンダーブロックを密着させるための部品で、高温・高圧力に耐える必要があります。
2. 電気・電子機器
コネクタ、端子、スイッチなどが挙げられます。
3. 建築用部品
ハンドル、ドアノブ、錠前などが挙げられます。
4 . 食品加工機械の部品
ミキサー、シュレッダー、カッターなどが挙げられます。
5. 航空機部品
エンジン部品、軽量な構造部品などが挙げられます。航空機のエンジン部品では、燃料噴射器、ターボチャージャー などが使用例です。
燃料噴射器は、燃料をエンジンに送り込むために使用される部品です。ターボチャージャーとは、エンジンに空気を送り込むための部品で、黄銅製のブローオフバルブを含む場合があります。ブローオフバルブとは、エンジンの運転中に発生する過剰なブースト圧力 (ターボチャージャーなどよってエンジンに送り込まれる圧力) を排出するために使用されるバルブです。
快削黄銅の種類
快削黄銅は、JIS H 3250にて5種類が定められていて、製法により下表のように分類されています。
| 合金番号 | 製法 | 記号 |
| C3601 | 引抜 | C3601BD |
| C3602 | 押出 | C3602BE |
| 引抜 | C3602BD | |
| 鍛造 | C3602BF | |
| C3603 | 引抜 | C3603BD |
| C3604 | 押出 | C3604BE |
| 引抜 | C3604BD | |
| 鍛造 | C3604BF | |
| C3605 | 押出 | C3605BE |
| 引抜 | C3605BD |
快削黄銅の性質
1. 切削性
快削黄銅は、銅合金の中でも最も切削性能が高い材料です。理由は適度な硬さがあることから、切削刃が容易に材料に食い込み、切削力を効率的に伝達できるためです。また、耐摩耗性が高く、切削時に発生する摩擦による刃先の劣化が少なく、切削性能を維持できます。さらに、切削時の熱変質が少ないため、加工物や切削刃を過度に加熱しないようにでき、美しい仕上がりになります。
2. 加工性
加工性とは、材料を機械加工する際に、どの程度加工しやすいかを示す指標です。快削黄銅は適度な硬さと柔軟性を持っているため、機械加工に適しています。特に切削加工においては、刃先が快削黄銅に容易に食い込み、切削力を効率的に伝達できます。また、快削黄銅は比較的軟らかいため、曲げ加工や穴あけ加工なども容易です。
加工後の表面仕上げに関しては、表面についた切削屑やバリを簡単に取り除けるため、非常に滑らかで美しい仕上がりになります。
3. 耐食性
快削黄銅は耐食性に優れた材料であり、腐食に強い特性を持っています。快削黄銅の耐食性が高い理由には、銅の特性が関与しています。
銅は、表面に酸化被膜を形成するため、通常の条件下で腐食に強い材料です。酸化被膜は、銅と空気中の酸素が反応して形成されるもので、表面を保護します。また、銅は自己修復性を持っているため、酸化被膜が割れた際には、銅が再び酸化して表面を覆い、再び保護します。
快削黄銅は、銅に亜鉛を加えた黄銅合金であり、亜鉛もまた酸化被膜を形成します。よって、快削黄銅は銅と亜鉛の特性を合わせ持ち、耐食性に優れた材料です。
4. 導電性
銅は電気の導電性に優れていることから快削黄銅を導電性を持つため、電気部品や電気回路によく使われています。
5. 耐磨耗性
快削黄銅は摩耗に対して非常に強い材料です。理由は快削黄銅が硬さや強度が高く、表面が滑らかであるためです。銅と亜鉛を主成分とする黄銅合金に、鉛やリンなどの添加物を混ぜ合わせて作られるため、硬さや強度が高く耐摩耗性に優れています。
快削黄銅が摩耗に強い理由の1つに、表面が滑らかであることが挙げられます。表面が滑らかであるため、接触面積が小さくなり、それに伴って摩耗が起こりにくくなります。また、快削黄銅は自己潤滑性が高く、潤滑剤を使用しなくても摩耗を軽減できる材料です。
6. 溶接性
快削黄銅は溶接性に優れている理由は、銅の特性によるものです。銅は加熱によって柔らかくなり、溶接に適した状態になります。また、快削黄銅は鉛やリンなどの添加物によって溶接時に生成する酸化物を減少させられるため、溶接面の酸化を防止し、より強力な接合が可能になります。
7. 加熱性
快削黄銅は加熱によって形状を変えられるため、冷間加工後に加熱して形状を修正できます。
8. 熱伝導性
快削黄銅は熱伝導性に優れてるため、加熱された箇所から熱が均等に伝わり、素早く冷却されるため、変形や歪みが少ないです。
9. 美しい色合い
快削黄銅は黄色い色合いが美しく高級感があることから装飾品やインテリア用品にも使用されます。
10. 錆びにくい
快削黄銅は、銅の特性により錆びにくいです。銅は空気中の酸素と反応して酸化しますが、酸化物が形成されるとその表面が酸化物で覆われ、次の酸化を防止するために、錆びにくくなります。また、酸化物は通常緑青色の酸化銅と呼ばれる物質で、これは銅の特徴的な緑色の色合いを与えることがあります。
快削黄銅に含まれている鉛やリンは、快削黄銅の加工性や切削性を向上させるために用いられる元素です。しかし、鉛やリンは、錆びにくい性質を与えるという効果も持っています。さらに、快削黄銅は、塩分や酸性物質に対しても耐性があり、湿気の多い環境でも錆びにくく、屋外での使用にも適しています。
快削黄銅のその他情報
1. 鍛造加工
快削黄銅は、鍛造加工にも適した材料です。鍛造加工によって、快削黄銅の耐久性や強度を高められます。
2. 熱処理
快削黄銅は、熱処理によって硬さや強度を変えられるため、熱処理によって、快削黄銅の加工性や耐久性を改善できます。