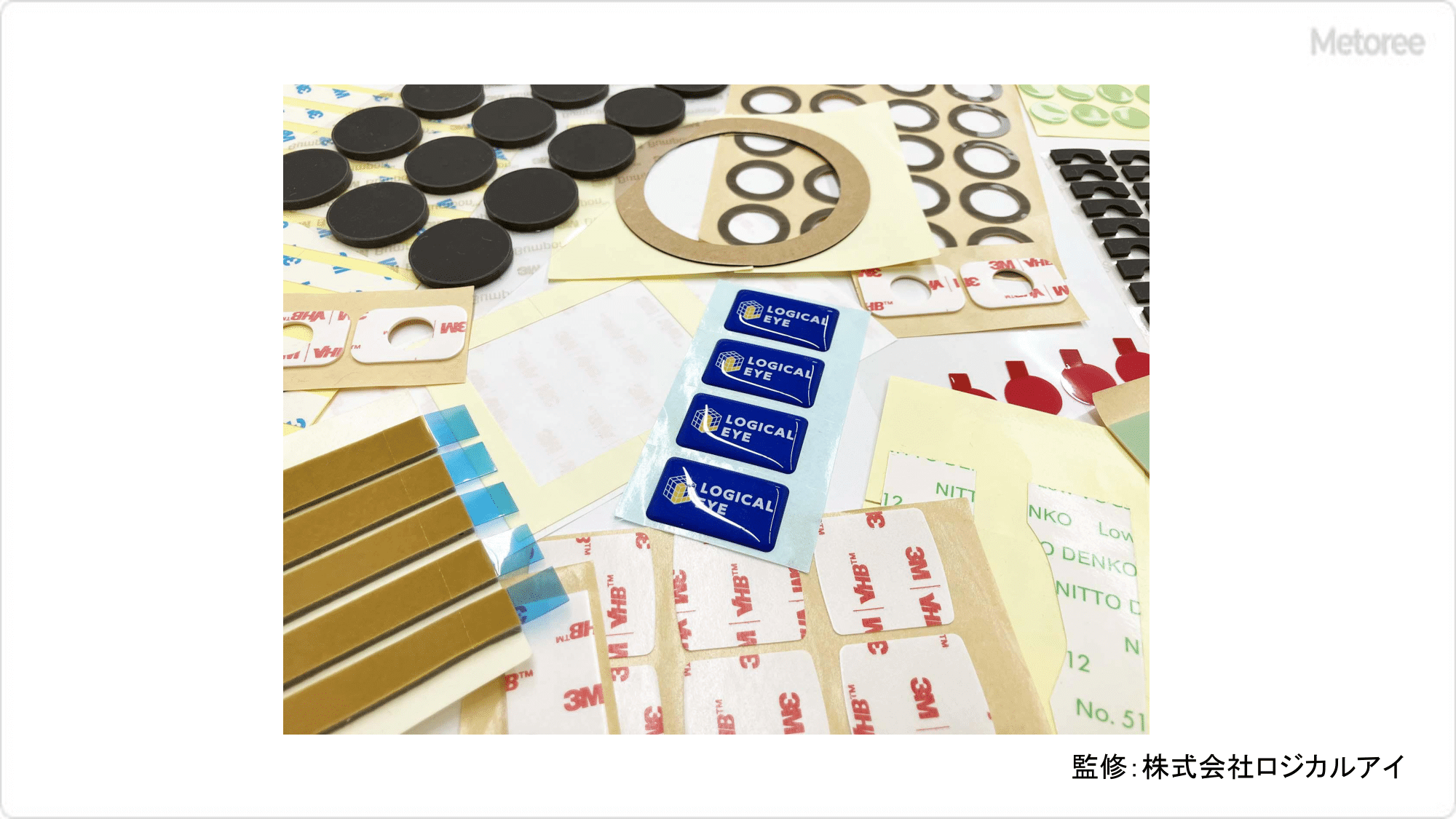ハードボードとは
ハードボードとは、木材の繊維を細かく解きほぐし、水分を含ませた状態で加圧・加熱して成形して製造される木質ボードです。
木材に本来含まれるリグニンが熱によって軟化し、繊維同士の結合材として働くため、接着剤の使用量が比較的少なく、木材資源を有効活用できます。
製造過程で高い圧力がかかるため、密度は中質繊維板 (MDF) よりも高く、薄い板材でも硬さと表面平滑性を兼ね備えている点が特徴です。細かな繊維が表面に均質に分布することから、印刷・塗装・化粧紙貼りなどの仕上げ加工がしやすく、仕上げ面の見栄えを整えたい用途に適しています。また一般的に、厚さ2~6mm程度の薄物製品が多く、軽量で取扱いが容易です。一方で、繊維が水分により膨潤しやすい性質をもつため、湿気の影響を受けやすいという弱点があります。
ハードボードの使用用途
ハードボードは、硬さ・薄さ・表面平滑性・加工性といった特性が要求される幅広い用途に使われます。
1. 家具の背板および引き出し底板
ハードボードは、家具の部材として使用されます。多く用いられるのは、収納家具の背面や引き出し底など、補強を必要としつつも重量を抑えたい部位です。例えば、カラーボックス・整理棚・テレビボードなどでは、背面材が構造強度を支えつつ、家具全体の歪み防止に役割を果たします。ハードボードは、薄くても面方向の剛性があるため、強度を確保しながら軽量化にも貢献します。
2. 室内建材の下地および仕上げ基材
内装壁の下地材や化粧板の基材としても利用されます。内装工事の仕上げ作業では、壁紙や化粧シートの貼り付けや塗装などがありますが、ハードボードの凹凸の少ない均質な表面は貼りムラを抑え、壁面の精度を高めます。また軽量で加工しやすいため、現場での切断・調整作業が容易です。仮設展示パネル・掲示板・店舗什器の背面ボードなど、施工性と仕上げ性を両立したい空間設計の場でも多用されています。
3. 工作・模型・デザイン教育用ボード
ハードボードは、学校教材・模型制作・DIY用途でも用いられる素材です。ノコギリ・糸鋸・カッターなど一般的な工具で切断しやすく、加工時の破損も比較的少ないため、扱いやすい点が教育用途に適しています。