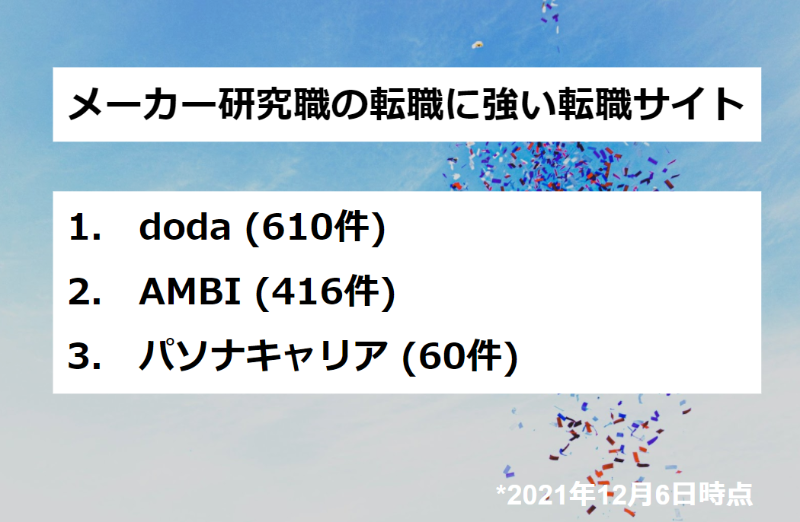作業ベルトとは
作業ベルトとは、作業着を着るときに腰に巻きつけるベルトのことです。
作業ベルトは普通のベルトよりも頑丈に作られているため、工具類を入れた作業袋をぶら下げたり、工具類をくくりつける際に役立ちます。普通のベルトにあるような穴はなく、ベルトをバックルで挟んで固定するタイプが一般的です。
作業ベルトは上下が分かれている作業着を着用している場合に、作業着のパンツがずり下がることを防止し、パンツの裾を踏んで転倒するなどの事故や怪我から作業者を守ります。ただし安全帯や命綱として作業ベルトは使えません。
作業ベルトの使用用途
ズボンがずり落ちないように固定する目的でベルトがよく使用されますが、作業現場では重要性がさらに高いです。ズボンが下がって裾が余っていると動きにくく、裾が引っ掛かって転倒する危険性が高くなり、裾が機械に巻き込まれると大事故につながる可能性もあります。作業時の安全を確保するためにも作業ベルトの着用が推奨されます。
世の中には様々なベルトが販売されていますが、ほとんどのベルトがファッション用途です。作業用ベルトには伸縮性や耐久性などが備わっており、作業現場で使う場合には激しい動きにも耐えられるものが適しています。
作業ベルトの原理
作業ベルトを作業着のベルトループに通し、バックルで固定します。バックルのタイプによって固定の方法が異なります。
1. ワンタッチ式
バックルのロック箇所とベルトの長さを調節する箇所が別々になっているため、装着前に身体の大きさに合わせてベルトの長さを調節しておきます。腰骨の上の位置でしっかりと締まる長さが適切です。装着時にはベルトの長さを調節してからベルトループに通してバックルをはめます。
2. ローラー式
ベルトループにベルトを通してからバックル部分にあるローラー芯を動かし、ベルトの生地を軽く挟み込み締め付け度合いを調節します。ベルトの生地を引き絞り、ローラー芯をしっかりと嚙みこませてベルトを固定します。
3. フィンガー式
スライドバックル部分を開き、ベルトの先端部分を通した後、バックル部分の穴にベルトを差し込みます。余ったベルトはベルト通しに通すことが重要です。くくりつけたい工具類の数が多くて重くなる場合には、クッション入りのサポートベルトを作業ベルトの内側に巻くと、腰の痛みを緩和できます。
作業ベルトの種類
素材によって特性は大きく違うため、使用用途に合ったものを選ぶ必要があります。
1. ナイロン
ナイロン素材のものは濡れてもすぐに乾きやすく、摩擦に強く、耐久性が高いです。軽いため腰への負担も軽減できます。
2. 綿
綿素材は吸水性に優れ質感も柔らかいため、腰に良くフィットします。長時間つけることが多い場合に腰の負担を軽減できます。
3. レザー
レザーはしなやかで腰にフィットしやすく、丈夫で長年使えます。しかし水に弱く汗などの匂いも残りやすいため、作業用としてはあまり適していません。
4. エナメル
革の表面を樹脂でコーティングしているため、革に比べて耐水性が高いです。暑さや熱に弱く高温で使用すると表面が溶ける可能性もあるため、作業用にはあまり向いていません。
5. ゴム
ゴムには伸縮性があり、腰にしっかりと巻き付きます。良く水をはじき匂いも付着しにくいため、水中や水辺で作業する場合に適しています。
6. ポリエステル
ポリエチレンテレフタレートを繊維状にした素材です。引っ張りや摩擦に強く、クセが付きにくいです。耐薬品性や耐熱性も高く、熱がこもりやすい場所や薬品を使う環境でも耐久性を失いません。
作業ベルトの選び方
選択のポイントを以下にまとめます。選んだものによっては作業効率が落ちたり、トラブルにつながる可能性もあるため、適切なものを選択する必要があります。
1. 長さ
自分のウエストに合った長さを選ぶことが大切です。締め付けがきつすぎると作業中に体調不良になる危険性があり、事故や怪我につながります。人のウエストのサイズは変わりやすいため、すぐにサイズを調整できるものが適しています。
2. 幅
作業着のベルトループの幅を調べて、ベルトループにスムーズにベルトが通るものを選ぶことが重要です。ベルトとベルトループの幅が合っていないとフィット感に欠け、安全性も低下します。
3. 重量
軽量のタイプが理想的ですが、軽さにこだわりすぎると耐久性が低い可能性もあります。機能と重量のバランスを考えることが重要です。
4. 固定方法
ワンタッチ式
装着前にあらかじめ身体の大きさに合わせてベルトの長さを調節し、バックルの位置を決めることで、ワンタッチで着脱可能です。不意に外れる可能性も低く、安全に使用できます。
ローラー式
バックルにベルトを挟み込んで固定するため、ベルトの長さを無段階で調節できます。わずかなサイズ調整も可能なため、より作業者の体形にフィットした状態で装着できます。
フィンガー式
作業着の状況に応じてすぐにベルトの長さを調整できます。作業状況によって作業着の厚みや形態が変わる現場や、頻繁に着脱する現場に適しています。