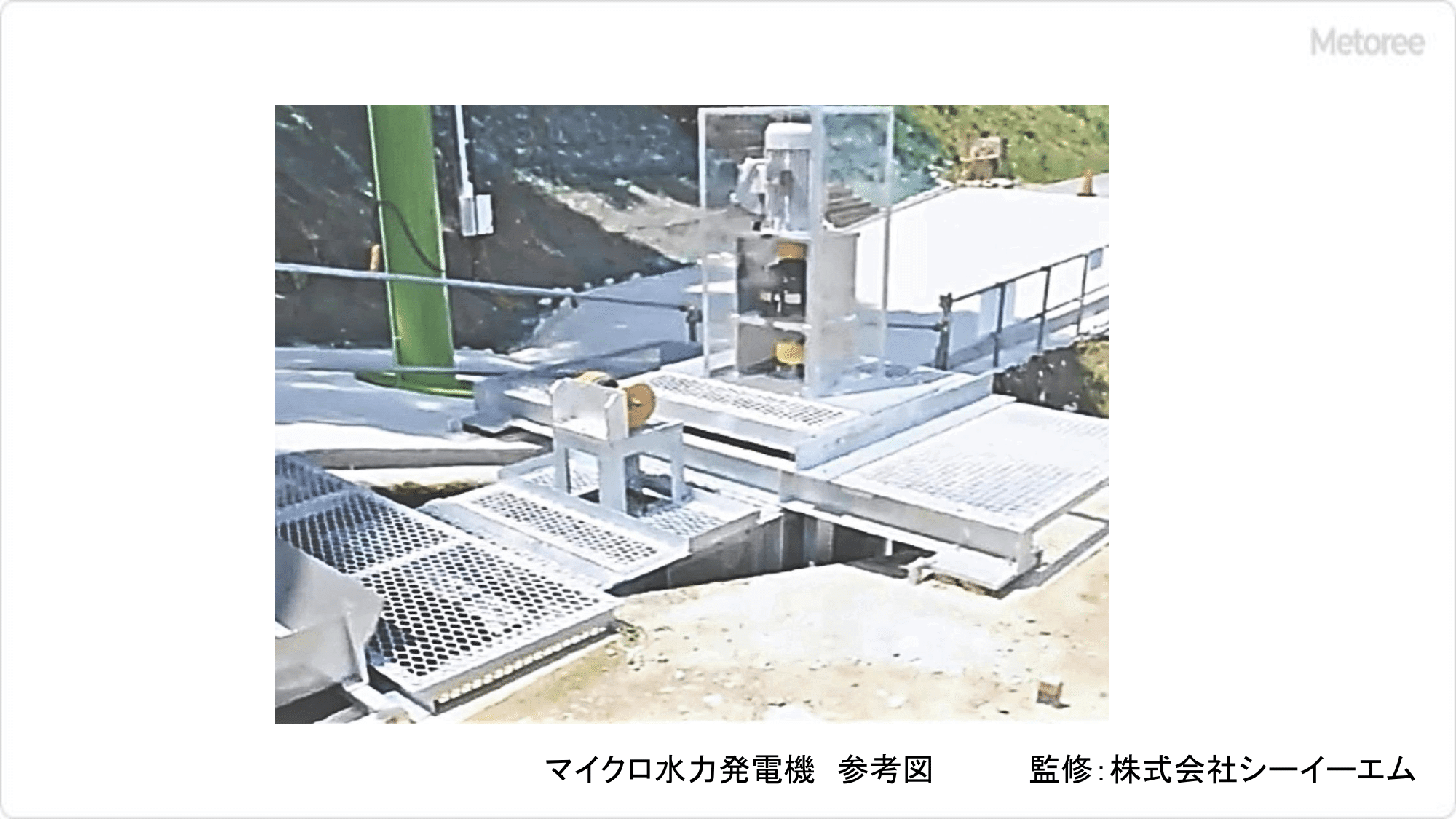監修:アカメディア・ジャパン株式会社
オンライン試験システムとは
オンライン試験システムとは、インターネットを通じて試験を実施するシステムです。
場所や時間に左右されずに、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などで回答を送信できるため、遠方の受験者も受験しやすい点が特徴です。
また、従来のように都度の会場・日程セッティングや講師の負担を軽減できるため、業務の効率化を図ることができます。またAIを利用する本人確認の仕組みが導入されている場合、不正な代行受験を防ぐ効果も見込めます。
オンライン試験システムにはクラウド方式と自社サーバー方式があります。クラウドサービスは導入コストを抑えやすく、必要に応じてサーバーの性能を柔軟に変更できるという利点があります。一方、自社運用の場合はシステムをカスタマイズしやすい反面、管理や保守に手間がかかる点が特徴です。
オンライン試験システムの使用用途
オンライン試験システムは以下のような用途で使用されます。
1. 教育機関
教育機関では、各種資格試験や検定試験などにオンライン試験システムが活用されます。
従来の紙ベースのテストに比べて採点や学習の理解度を集計・計測する手間を減らせるため、教員の負担も軽減されます。
また、遠隔授業との相性が良く、受験者は場所や時間を選ばずに受験できます。
2. 企業・団体
企業や団体が実施する教育研修や採用試験、検定制度でも、オンライン試験システムは活用されます。
試験問題の種類や難易度を柔軟に設定できるため、多様な職種やスキルレベルに合わせた評価が可能です。
業務に必要な知識を定期的にテストし、その結果をデータで管理することで、人材育成を効率化できます。
例えば、新入社員研修では、各種マニュアルの理解度を計測し、足りない部分を強化する指標としても機能します。
本記事はオンライン試験システムを製造・販売するアカメディア・ジャパン株式会社様に監修を頂きました。
アカメディア・ジャパン株式会社の会社概要はこちら