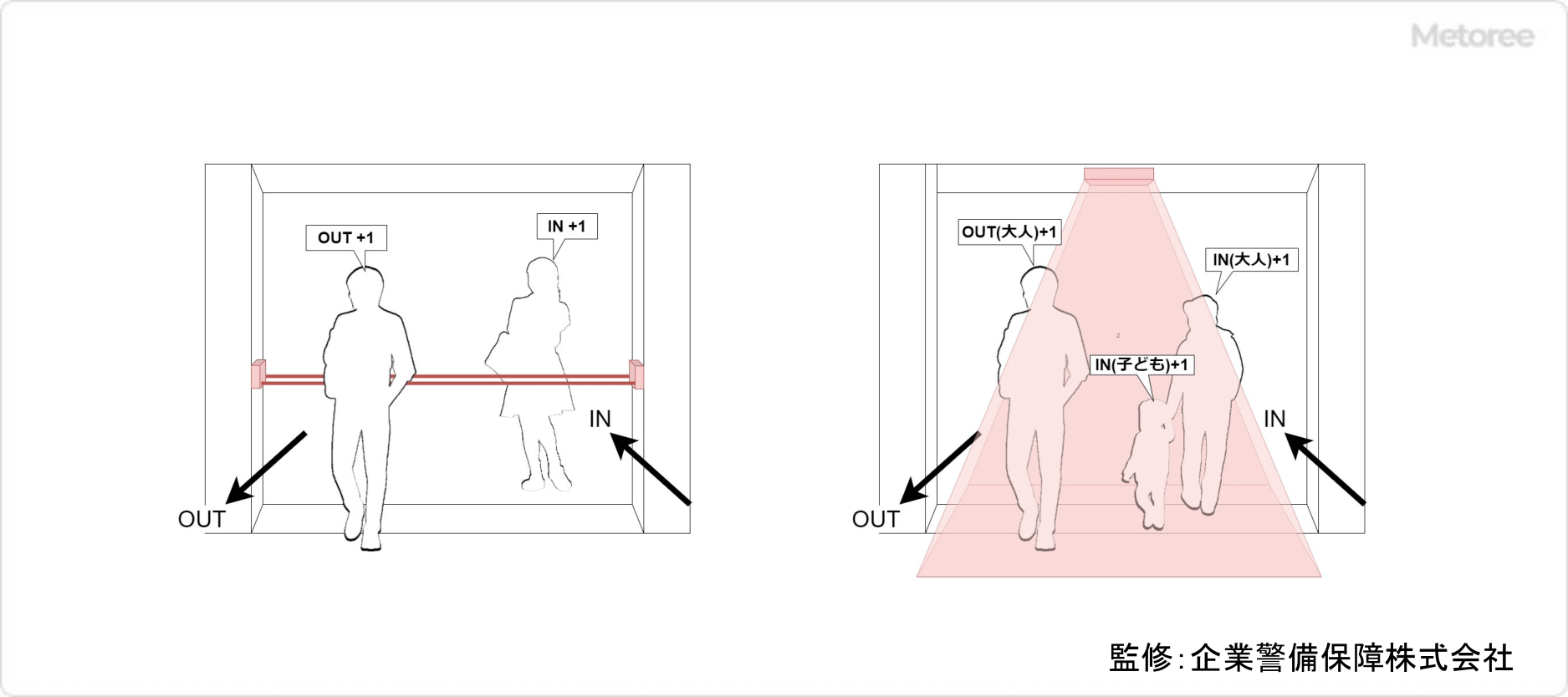監修:日本ユニバーサル電気株式会社
超伝導コイルとは
超伝導コイルとは、超伝導体の線材で作られたコイルを指します。
超伝導体とは、特定の温度以下になると電気抵抗がゼロになり、物質内部から磁場が排除されるマイスナー効果を示す、特殊な電気伝導性物質です。この現象は「超伝導」と呼ばれ、電気抵抗がゼロになるため、電流を流してもエネルギー損失が起こりません。
超伝導コイルには、液体ヘリウム (-269 ℃ ) で冷却されるNbTi (ニオブチタン) や Nb3Sn (ニオブスズ) などの線材が主に用いられていますが、液体窒素 (-196 ℃ ) で超伝導状態になる高温超伝導体の実用化も進んでいます。
通常の電磁石では、電気抵抗による発熱が必ず生じ、その発熱によって抵抗値がさらに上昇するため、流せる電流には限界があります。一方、超伝導コイルは電気抵抗がないため、発熱なく大きな電流を流すことができ、いったん電流を流して回路を閉じれば、電圧降下なく電流が流れ続けることが特徴です。
超伝導コイルの使用用途
超伝導コイルは、強力な磁場を発生する超伝導電磁石として様々な用途で活用されています。下記の主な用途の他にも、シリコン単結晶製造装置、重粒子線がん治療、発電機など、様々な分野で超伝導コイルが利用されています。
1. NMRとMRI
化学・物理分野の分析機器である核磁気共鳴分光法 (NMR spectroscopy) や医療分野の画像診断に利用される磁気共鳴映像法 (MRI) は、超伝導コイルの代表的な応用例です。これらの装置は、磁場内に置かれた原子核が固有の周波数の電磁波と相互作用することを利用したものであり、超伝導コイルは非常に強い磁場を発生させる電磁石として利用されています。
2. 核融合
磁場閉じ込め方式の核融合炉は、強力な磁場を作り出した中に超高温プラズマを閉じ込めて核融合反応を起こす仕組みです。超伝導コイルは、核融合炉においてこの非常に強力な磁場を作り出す役割を担います。
核融合炉に使用される超伝導コイルには、超伝導トロイダルコイル、超伝導中心ソレノイド、超伝導ヘリカルコイル、超伝導ポロイダルコイルなどの種類があり、核融合炉の形状によって異なっています。
3. リニアモーター
リニアモーターカーでは機動力として車両に超伝導コイルが配置されます。この超伝導コイルはN極、S極が交互に配置され、地上側にもN極とS極が交互となるように配置された推進用コイル (通常の電磁石) や浮上用コイルが配置されます。
車両の推進には、推進用コイルと超伝導コイルとの間で引き合ったり反発したりする力が用いられる仕組みです。また、超電導磁石が通過することで浮上用コイルに電流が流れて磁場が発生し、車両側の超伝導コイルとの間に磁力が働いて車両を浮上させることができます。
本記事は超伝導コイルを製造・販売する日本ユニバーサル電気株式会社様に監修を頂きました。
日本ユニバーサル電気株式会社の会社概要はこちら