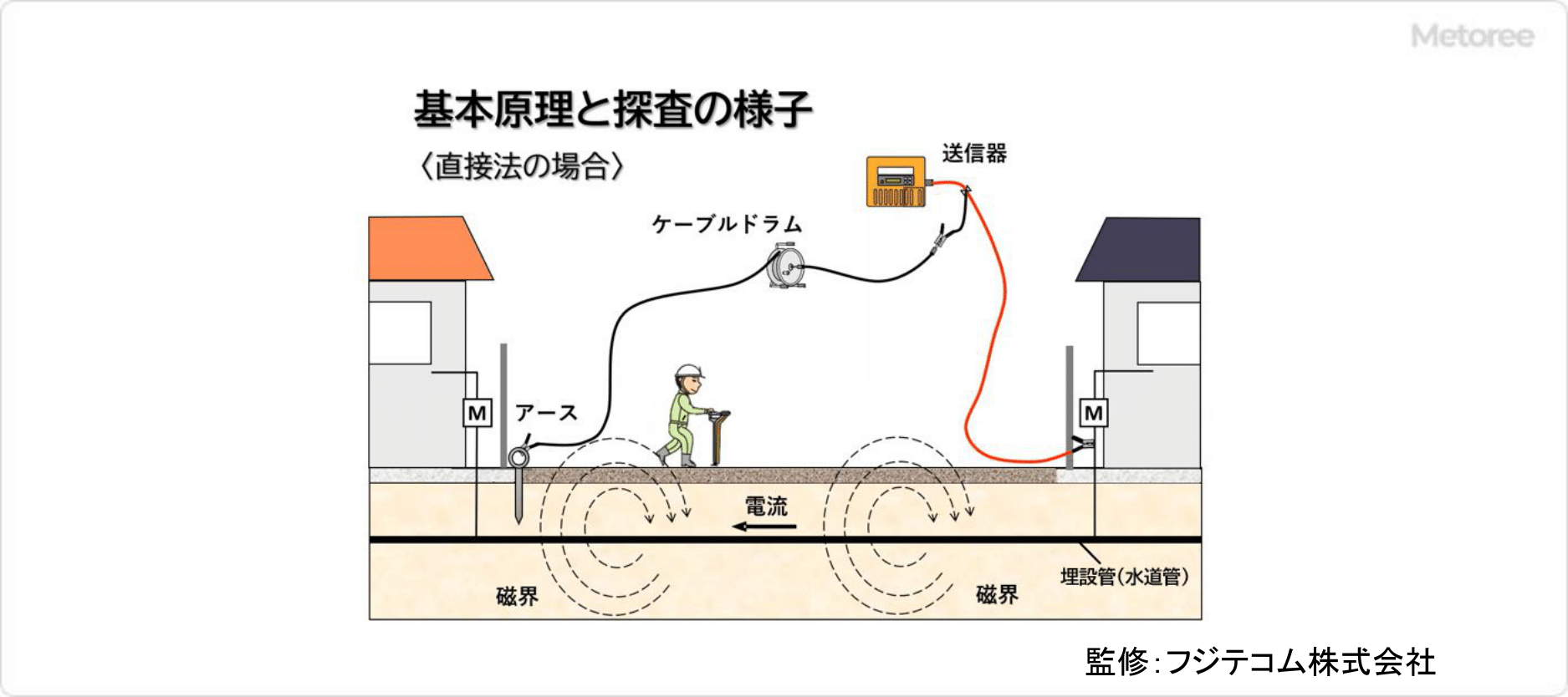鉄骨シェルターとは
鉄骨シェルターとは、地震の倒壊から命や重要物を保護する鋼鉄製の空間です。
鉄骨シェルターは家屋全体を補強する耐震改修工事とは異なり、家の中に潰れない部屋を作り出します。主に鉄骨造の強靭なフレームで構成され、万が一建物が倒壊してもシェルター内部の重要物や人命を保護します。既存の部屋の床や壁を取り払うことなく設置できる製品が多く、建屋を使用しながら工事が可能である点が特徴です。建て替えや大規模な改修が難しい場合に、現実的な選択肢として採用されます。
鉄骨シェルターには断熱性や遮音性を高めるオプションや、内装を洋室や和室の雰囲気に合わせる仕様が存在します。単なる防災設備としてだけでなく、生活・執務空間としての快適性を維持しながら災害時の避難場所へと改造が可能です。
鉄骨シェルターの使用用途
鉄骨シェルターは以下のような用途で使用します。
1. 住宅
旧耐震基準で建てられた木造住宅における現実的な地震対策として活用されます。家屋全体の耐震改修や建て替えには多額の費用と長い工期を要するため、予算の都合で工事を断念するケースが少なくありません。鉄骨シェルターであれば、住みながら比較的短期間で施工できます。特に就寝中の安全を確保する寝室や、家族が集まるリビングをピンポイントで守るために導入が進んでいます。
2. 介護・福祉
自力での迅速な避難が困難な高齢者や要介護者の安全を確保する目的で導入されます。グループホームや小規模な介護施設などでは、夜間のスタッフ数が限られている場合が多く見られます。地震発生時に全員を屋外へ誘導することが物理的に困難な状況が想定されます。居室や共有スペースにあらかじめ強固な空間を設置しておくことで、施設自体が損傷しても入居者の安全を確保できます。
3. 企業
企業活動の現場では、従業員の安全確保や重要資産の保護に使用します。古い工場や倉庫の詰め所または守衛室などに設置し、夜間勤務者の緊急避難場所として活用します。また人命保護だけでなく、企業の心臓部とも言えるサーバーや、顧客情報などの重要書類を保管する書庫として鉄骨シェルターを利用する事例も見られます。