











絶縁コーティング剤
メーカー15社一覧 【2024年】
絶縁コーティング剤についての概要、用途、原理などをご説明します。また、絶縁コーティング剤のメーカー15社一覧や企業ランキングも掲載しておりますので是非ご覧ください。絶縁コーティング剤関連企業の2024年3月注目ランキングは1位:スリーエムジャパン株式会社、2位:ホーザン株式会社、3位:エア・ブラウン株式会社となっています。
絶縁コーティング剤とは
絶縁コーティング剤とは、コーティング加工により絶縁性の皮膜を生成できる製品です。
ポリイミド系、エポキシ樹脂系など、含有する成分にはさまざまな種類があります。コーティング対象の物体に絶縁コーティング剤を用いると、表面に絶縁性の高い膜が生成されます。
この絶縁性の膜によって物体から電気が漏れにくくなるため、漏電による感電事故の防止などに有効です。絶縁コーティング剤の塗装方式としては、スプレーやディップなど一般的な方式以外に、膜厚の均一に優れた静電塗装法や電着塗装法なども普及しています。
絶縁コーティング剤の使用用途
絶縁コーティング剤は、主に自動車や家電製品など、高電圧がかかる製品の部品の絶縁処理に用いられます。絶縁コーティング剤を用いてコーティングすると、電圧に対する耐性を高めることが可能です。
例えば、電気自動車やハイブリッド車は動力として電気を利用しているため、バッテリーやモーターなどの周辺部品に高い電圧耐性が要求されます。電圧に対する耐性が不十分だと漏電が生じる可能性があり、場合によっては火災などの事故の原因となります。事故防止の観点からも、絶縁コーティングは重要な加工です。
絶縁コーティング剤の原理
絶縁コーティング剤は、絶縁性の高い絶縁体を対象物の表面にコーティングする製品です。絶縁体は電気を通さない物質であるため、耐電圧性が要求される対象物に使用できます。物体における電子のエネルギー準位には、価電子帯と禁制帯、そして伝導帯の3つが存在します。
この3つの中では、価電子帯、禁制帯、伝導帯の順に高いエネルギー準位です。一般に電子は、エネルギーが低い価電子帯からつまる性質があります。導電性に大きく影響するのは、エネルギーが高い伝導帯の電子です。金属などの導電体では、一部の電子が伝導帯に存在しています。この伝導帯の電子が自由に動くことによって、電気が通る状態となります。
一方で、絶縁体では、価電子帯に電子が存在しますが、伝導帯には存在しません。電子は光や熱のエネルギーを用いて、低いエネルギー準位から高い準位に励起することが可能です。
絶縁体は価電子帯から伝導帯まで電子を励起するために、多大なエネルギーを必要とする性質を持っています。このため、実質的に電子を伝導帯に励起することが難しく、電気が通らない状態となります。
絶縁コーティング剤のその他情報
1. プリント基板への絶縁コーティング剤の適用
プリント基板において、耐久年数よりも早期に故障の原因となるのが錆です。対策として、防湿絶縁コーティング剤が使用されています。これにより長期間の使用が可能で、安定稼働を実現しました。しかしながら、高い需要があるにも関わらず、様々な要因から安定した生産ができなくなりました。
最も大きい課題は乾燥時間の長さです。防湿絶縁コーティング剤の乾燥時間は24時間とされており、大量生産に適したコーティング剤ではありません。生産性の悪さが需要にマッチしていない状況となりました。その対策として、加熱温度を高める事により乾燥時間の短縮を狙いましたが、設備の増設やランニングコストの増加といった別の課題が生まれました。製品自体への負担も大きい結果となり、実現化には至りませんでした。
その課題を解決し、安定した量産を実現したのがフッ素系コーティング剤です。高い速乾性能を誇り、15分で完全乾燥に至ります。従来の24時間に比べ、大幅な乾燥速度の短縮が可能となり、生産効率の向上が達成されました。
従来より低温かつ低膜厚で性能を発揮できる事から、ランニングコストの削減も見込めます。肝心な皮膜性能も、防湿絶縁性はもちろん柔軟性や防水性、耐熱性で問題の無いスペックとなります。
2. 絶縁コーティング剤の将来性
電気自動車の普及が進む中、その部品形状は複雑化の一途を辿っており、より均一にコーティングできる技術が求められています。電着塗装法においては、コーティング液の組成変更での改善が進められています。
絶縁コーティング剤メーカー 15社
*一部商社などの取扱い企業なども含みます。
絶縁コーティング剤 2024年3月のメーカーランキング
*一部商社などの取扱い企業なども含みます2024年3月の注目ランキングベスト10
注目ランキング導出方法| 順位 | 会社名 | クリックシェア |
|---|---|---|
| 1 | スリーエムジャパン株式会社 |
20.3%
|
| 2 | ホーザン株式会社 |
11.6%
|
| 3 | エア・ブラウン株式会社 |
8.7%
|
| 4 | 株式会社フロロテクノロジー |
8.7%
|
| 5 | 株式会社イチネンケミカルズ |
7.2%
|
| 6 | 株式会社極東商会 |
7.2%
|
| 7 | サンハヤト株式会社 |
7.2%
|
| 8 | TOMATEC株式会社 |
5.8%
|
| 9 | 富士化学産業株式会社 |
5.8%
|
| 10 | ジェフコム株式会社 |
5.8%
|
注目ランキング導出方法について
注目ランキングは、2024年3月の絶縁コーティング剤ページ内でのクリックシェアを基に算出しています。クリックシェアは、対象期間内の全企業の総クリック数を各企業のクリック数で割った値を指します。社員数の規模
- 極東商会: 338人
- TOMATEC: 261人
- イチネンケミカルズ: 248人
設立年の新しい会社
- GAST技研: 2008年
- フロロテクノロジー: 2003年
- ハーベス: 1988年
歴史のある会社
- ホーザン: 1946年
- イチネンケミカルズ: 1948年
- シミズ: 1949年
絶縁コーティング剤の製品 1点
1 点の製品がみつかりました
株式会社シミズ
電着塗料 イミド系樹脂による薄膜絶縁コーティング エレコートTFY
80人以上が見ています
■主な用途 半導体、電子部品、センシング向けの新たな絶縁、放熱対策 ■薄膜絶縁・・・スマートフォン内臓部品、各種センサ 絶縁放熱・...
絶縁コーティング剤のカタログ 3件
Metoreeに登録されている絶縁コーティング剤が含まれるカタログ一覧です。無料で各社カタログを一括でダウンロードできるので、製品比較時に各社サイトで毎回情報を登録する手間を短縮することができます。
カタログを種類ごとに探す
- 全ての種類
- 製品個別カタログ
- 製品総合カタログ
- 会社案内カタログ
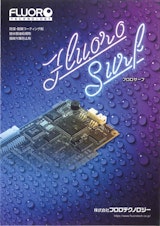
株式会社フロロテクノロジー
フッ素コーティング剤 フロロサーフ
カタログ概要
フッ素コート剤「フロロサーフ」は、表面に形成されるフッ素樹脂皮膜が撥水撥油性を発揮し、強力に水や油をはじきます。油脂類のバリヤ(はいあがり防止)・...
タグ付けカテゴリ
絶縁コーティング剤 フッ素コーティング剤 離型剤 撥水撥油コーティング剤 +12022年10月5日

株式会社フロロテクノロジー
基板用防湿絶縁コーティング剤 フロロサーフ
カタログ概要
電子基板用保護コーティング剤(コンフォーマル コーティング)「フロロサーフFG-3650シリーズ」は、車載用基板や電子部品の防水や絶縁保護、実装基板の防湿...
タグ付けカテゴリ
絶縁コーティング剤 フッ素コーティング剤 防湿コーティング剤2022年10月5日

株式会社フロロテクノロジー
株式会社フロロテクノロジー 会社紹介
カタログ概要
当社 株式会社フロロテクノロジーはフッ素系コーティング剤・コンフォーマルコーティング剤・撥水撥油処理剤・離型剤の専門メーカーです。フッ素系の化合物は...
タグ付けカテゴリ
絶縁コーティング剤 フッ素コーティング剤 離型剤 撥水撥油コーティング剤 +22022年10月5日
